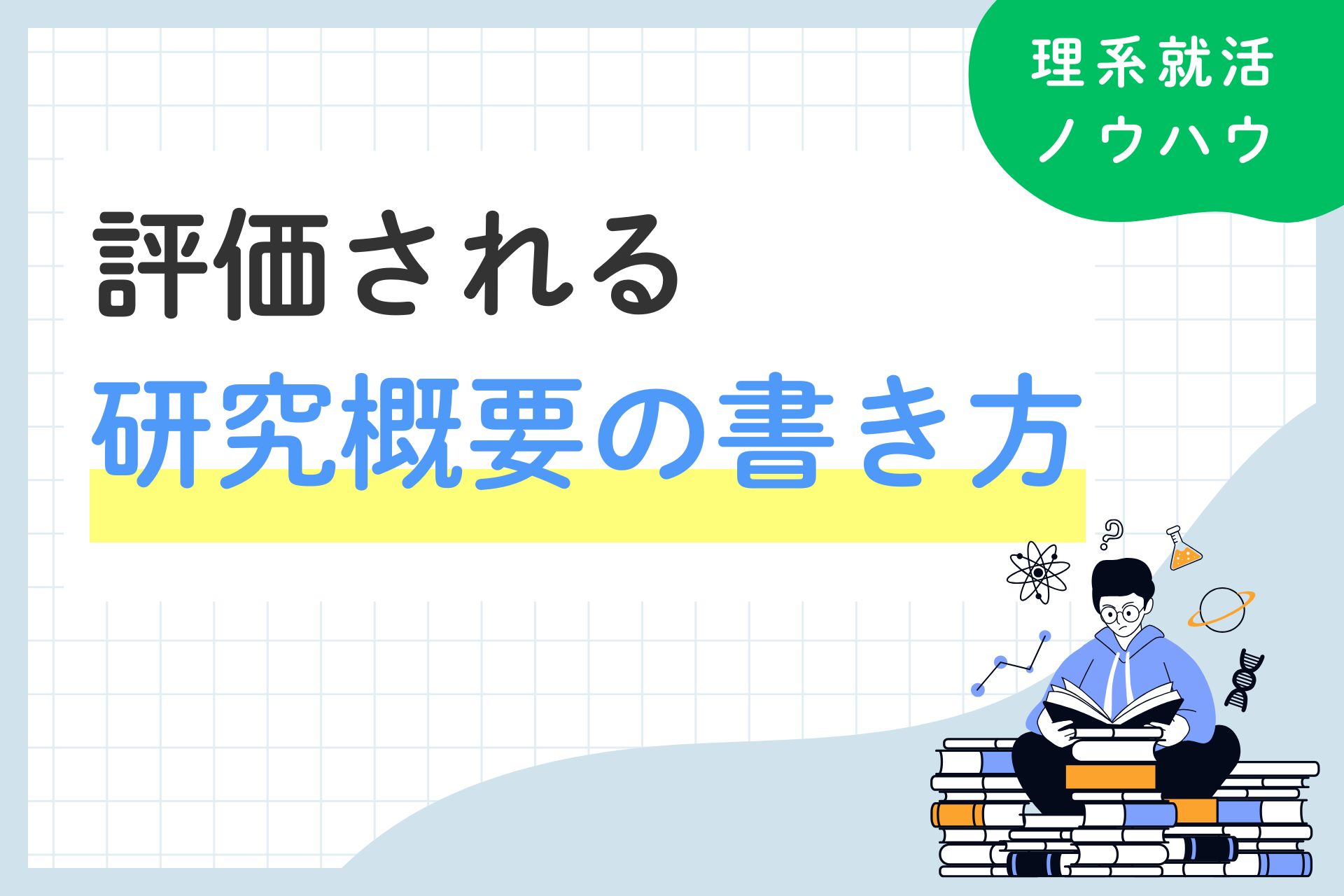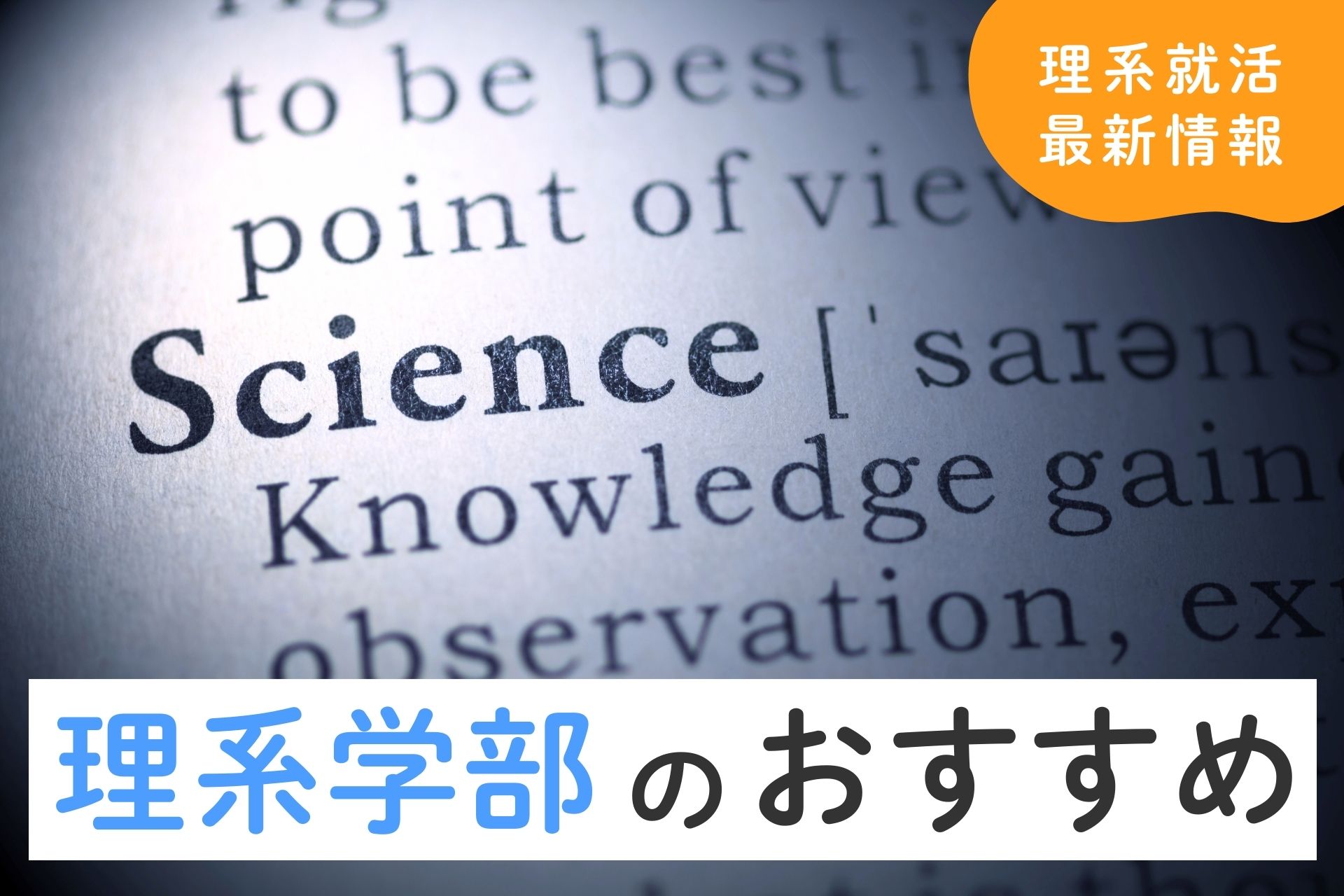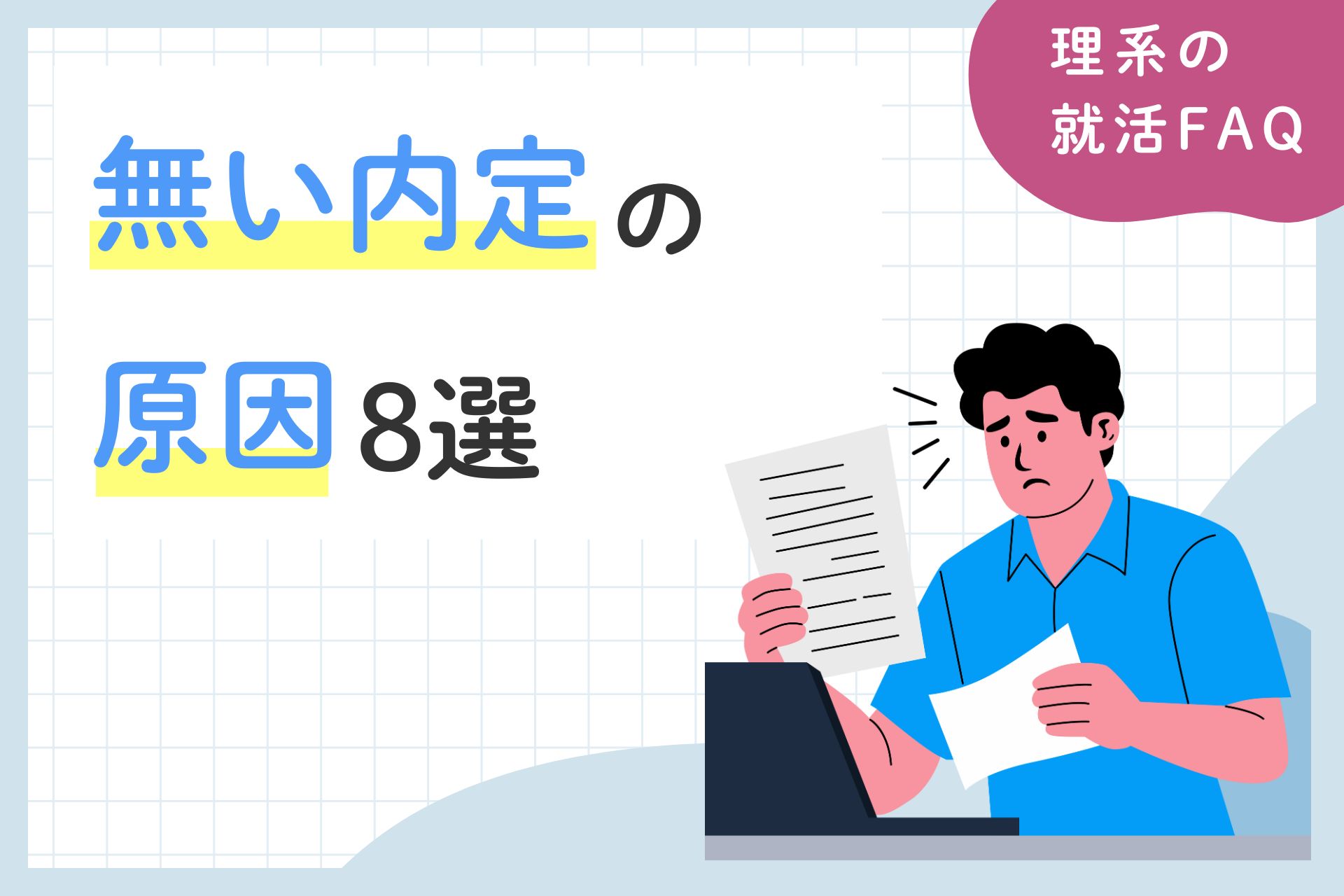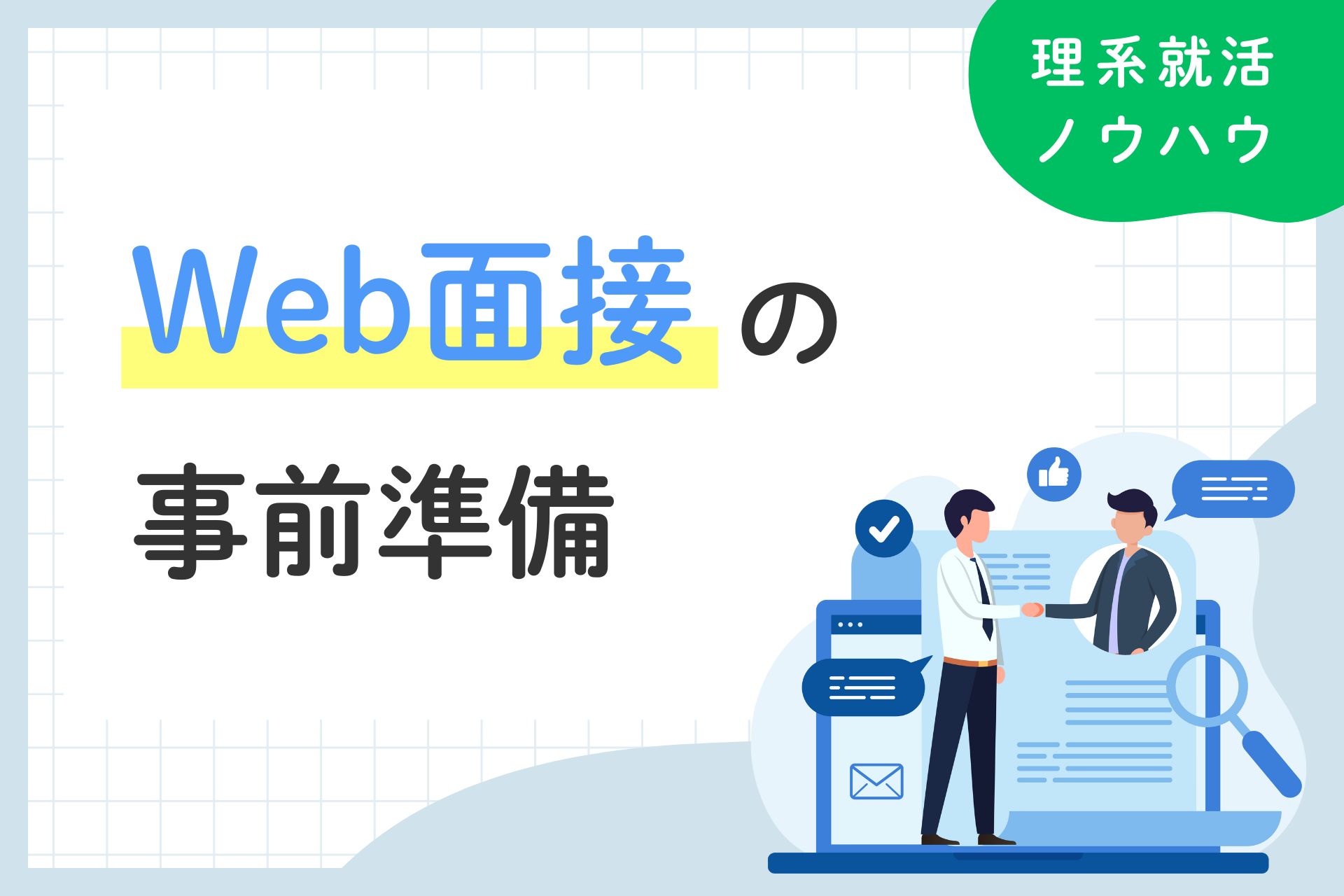こんにちは。理系就活情報局です。
「就活に失敗したらもう終わり......」そんな思いにとらわれている人は少なくありません。
特に、理系の場合は専門性が高い分、うまくいかなかったときの挫折感も大きくなりがちです。
しかし、内定が出なかったからといって人生そのものが否定されたわけではありません。
本記事では、失敗の原因と対策、今からでもできる挽回の道を解説します。
焦らず次の一歩を踏み出すためのヒントを一緒に探していきましょう。
就活に失敗したら負け組?
大卒・大学院卒で就活に失敗したら高学歴引きこもりニート?
大卒や大学院卒で就活に失敗した場合、卒業後の就職は難しく、高学歴ニートしか道はないと考える方もいるかもしれません。
結論からいいますと、就活に失敗して内定がないまま大学・大学院を卒業しても、就職のチャンスはまだまだ多くあります。
昨今はどの企業でも人手不足が深刻化しています。
就活に失敗した原因を振り返り、対策を怠らなければ、昨今の社会情勢を考えると卒業後でも就職は十分に可能です。
自分は高学歴ニートになるしか道はないと諦めず、卒業後も粘り強く就職活動を続けましょう。
就活に失敗しても人生は終わらない
結論、就活に失敗しても人生は終わりません。
「第一志望の企業に落ちてしまった」
「友達はもう内々定が出ているのに、自分だけ最終面接を突破できてない」
こうした状況になると、就活に失敗してしまった……と落ち込む理系就活生もいると思います。もし今失敗だと感じていたとしても、就活を続けていれば、光が見えてくる可能性は充分にあります。今が最終地点と考えず、成功につながる過程だと考えてみましょう。
就活には、秋採用や冬採用もあるため、夏休み明け以降にも採用のチャンスはあります。
また、現在は卒業後3年間は新卒扱いになり、卒業する年に就職できなかったとしても、新卒として就活を続けられます。
「周囲に遅れをとっている」と思うと、焦ってしまうかもしれません。
諦めず、採用情報を集めて就活の準備を着実に進めていきながら、自分だけのゴールを目指しましょう。
(参考:厚生労働省「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」)
就活が失敗だと感じるケースとは
成功や失敗の判断基準は個人で異なるため、同じ結果でも就活に成功したと感じる人もいれば、失敗したと感じる人もいます。
本章では、就活生が就活に失敗したと感じる一般的なケースを解説します。
内定をもらえない
就活が失敗だと感じるケース1つ目は、内定をもらえないことです。
特に、「絶対この会社に入社したい!」と意気込んでいた人ほど、第一志望に落ちた場合に就活に失敗したと感じます。
また、就活が佳境に近づいた時点で内定をひとつも貰えていない理系就活生も就活に失敗したと感じるでしょう。
友達はどんどん内定をもらっていくのに、自分だけが置いていかれていると就活に失敗した感覚を覚えると思います。
内定を獲得しても自分に合うか確信が持てない
就活が失敗だと感じるケース2つ目は、内定を獲得しても自分に合うか確信が持てないことです。
第一志望には落ちたものの、第二志望の企業から内定、苦労の末に得た初めての内定の場合、はたして自分に合う企業なのか悩む方は多いでしょう。
納得のいかない就活となっているため、まだ就職活動を続けるのか、他の内定先に決めるのかを決断できない方は少なくありません。
確信の持てない就活の現状に対して、自身の就活は失敗したと感じる方はいるでしょう。
就活を続けるのか、入社するのかの判断に迷ったときは、企業との相性を確かめるべく、採用担当者と会うなどの行動に出てみることをおすすめします。
内定が取り消された
就活が失敗だと感じるケース3つ目は、内定が取り消された場合です。
内定の取消により卒業後の進路が絶たれたことや内定を取り消すような企業を選択したことに、自身の就活が失敗と感じてしまいます。
「内定をもらって、4月の入社を楽しみにしていたのに、取り消されてしまった。」
「もう就職活動もしていないし、今から応募できる企業があるのかわからない。」
内定が取り消された方は、不安の中にいると思います。
まずは気持ちを落ち着かせて、しっかり睡眠を取りましょう。
気持ちの切り替えができたら、以下の行動を取るなど、少しずつ動き始めることをおすすめします。
・就職活動の再開
・企業側へ内定を取り消す理由の確認
・弁護士や労働局への相談
就活に失敗した人の理由3選
高学歴だからと慢心していた
学歴に自信がある人ほど「どこかには受かるだろう」と準備を怠りがちです。
企業は人柄や志望動機、研究内容の伝え方までを見ており、学歴だけで評価されることはありません。
特に、理系職は専門性と実践力が重視されるため、面接対策や企業研究をしっかり行わないと評価につながりにくくなります。
専門分野での就職にこだわりすぎた
「専門分野で働きたい」と考えることは自然ですが、選択肢を狭めすぎてしまう原因になるケースもあります。
理系のスキルは分野を越えて応用できる場面も多く、柔軟な視点で業界や職種を見直すことが大切です。
専門性に固執しすぎず、自分の力が活かせる道を広く探す姿勢が重要です。
手当たり次第にエントリーしてしまった
エントリー数が多ければ安心というわけではありません。
手当たり次第にエントリーしすぎた結果、志望動機が浅かったり準備が不十分だと面接で印象が薄くなりがちです。
なんとなくエントリーするよりも自分に合った企業を見極めて質を高めることが、選考通過の確率を上げる近道です。
就活に失敗した人の理由3選
就活を始める時期が遅い
就活の早期化が進む現在、スタートが遅くなってしまうと、周りと大きな差が生まれて結果につながらないことがあります。
いざ就活を始めようと思った時には、エントリーが締め切られていたとならないよう、就活スケジュールはしっかり確認しましょう。
多くの学生は学部卒での就職の場合、遅くとも3年の夏頃までに準備を始めており、就活の解禁時には既にOB訪問やESの添削などの準備を進めています。
中には、1年や2年時から準備をしている人もいます。修士卒の場合は、修士1年の夏~秋に就活をスタートするのが理想です。
自己分析・企業分析が足りない
自己分析や企業分析が足りないと、採用担当者に志望度が低いと判断されるため、内定が出にくくなります。
どの企業でも使いまわせる薄い内容の志望理由や自己PRを書いているESは、「この学生はまともに企業研究をしていないな」とすぐに見抜かれます。
例えば、志望動機に企業や業界の特徴を書いただけの文章からは学生の気持ちが全く伝わってきません。
また志望する企業のファンであるような内容では、志望動機としては弱いため、企業の事業に自分がどのように関わりたいかなどをプラスしましょう。
エントリー数が少ない
そもそもエントリーした企業の数が少なすぎると、当然ながらチャンスも限られてしまいます。
特に、理系職は募集枠が小さいこともあるため、ある程度の数は必要です。
とはいえ無理に増やす必要はなく、準備と選考をこなせる範囲で多めに動いておくのがおすすめです。
SPIや面接対策が後回しになっている
自己分析や企業研究、エントリーにかかりきりで、SPI対策がおろそかになっていると、その先の選考に進めません。
SPIは、くり返し問題を解くことで克服できますが、いきなり本番で受けると戸惑いから、うまくいかない可能性があります。基本的な学力があるから大丈夫と慢心せず、隙間時間を使って対策しておきましょう。せっかくエントリーシートが上手く書けていても、SPIでつまずくのはもったいないです。
ほかの理系就活生がやっていることは、自分もきちんとやって、周囲に遅れを取らないようにしましょう。
大手企業ばかり志望している
大手企業は魅力的ですが、その分倍率も高く狭き道となるため、内定が獲得できない可能性が上がります。
「誰もが知っている企業だから」「安定していて給料も良いから」と、安易に志望企業を選んでいませんか?
大手企業は応募者も多く、選考に通過できる可能性は低くなります。
将来の選択肢を狭めないためにも、志望企業は絞りすぎず、範囲を広げましょう。
大手ばかり志望している理系就活生の中には、就活の軸が定まっていない方もいます。
今一度、自分が就職する企業に何を望むのかを考えてみましょう。
身だしなみやマナーに欠ける
学生と社会人ではマナーに対する意識のレベルが全く違います。学生なら許されたことも、社会人にとってはありえないことも少なくありません。
身だしなみやマナーはビジネスマンとしての基本でもあるため、欠けていると判断されれば、選考は落選になります。
自分が取る行動で相手が迷惑することが無いか、不愉快な気持ちにならないかと考えてみましょう。
礼儀とは相手に対して敬意を示すための作法をさす言葉であり、自身の言動に「敬意」が含まれているか振り返ることをおすすめします。
採用担当者は「礼儀を知らない」「マナーがなっていない」と感じた学生を覚えているものです。
「基本だからできている」と思い込まず、今一度自分の身だしなみやマナーを振り返ってみましょう。
選考の振り返りをしない
不合格の通知をもらったあとに振り返りをせず、次の選考へ進んでしまうと、同じミスを繰り返してしまう可能性があります。
何が足りなかったのか、どう改善すべきだったかを都度振り返り、次に活かすことが成長につながります。
落ちた経験を次に活かす意識が重要です。
就活が失敗して人生終了と感じる理由
自分は価値のない人間だと認定されたように感じるから
誰もが人生において多くの失敗を重ねており、失敗から立ち上がってきたでしょう。
一方で同じ失敗でも、就活の失敗は人生終了と感じるほどダメージを受けます。
就活に失敗した場合、以下のことが頭によぎるため、多くの方が人生終了と感じます。
選考に落ち続けると、自分そのものが否定されたように感じるかもしれません。
ですが企業が見ているのは「今のあなた」と「その企業に合うかどうか」であり、人間としての価値とは別です。
一時的な評価に過ぎないことを忘れず、自己否定に引きずられないことが大切です。
新卒カードを無駄にしたから
「新卒じゃないともう選べない」と焦る声も多いですが、近年は卒業後3年以内なら既卒枠で応募できる企業も多数あります。
一度失敗したからといってすべての可能性が閉ざされるわけではないため、新卒カードを活かすためにも、冷静に再スタートを切る準備が重要です。
将来が見えず先行き不安だから
就活が思うように進まないと「この先どうなるんだろう」と将来が不安になるものです。
ただ、今の段階で人生のすべてが決まるわけではなく、軌道修正のチャンスは何度もあります。視野を広げることで新たな選択肢が見えてくることも多いです。
生活費などの金銭的不安があるから
内定がない状態で卒業を迎えると、家賃や生活費の問題も現実的な悩みになります。
金銭面の不安が大きくなる前に支援制度やアルバイト、親への相談など現実的な対策を早めに考えておくことが大切です。
就活が失敗だと感じた時に取りたい対策
就活に失敗したと感じた場合、多くの方は落ち込み傷ついていることでしょう。
しかし、気持ちを切り替え、対策を打てれば、就活の失敗を挽回するチャンスは十分にあります。
本章では就活が失敗だと感じたときに取りたい対策を解説します。
気持ちを切り替えて就活失敗の原因を探す
就活が失敗だと感じた時は、まず現状に落ち込むことから抜け出しましょう。
一度就活から距離を置いて、しっかりと睡眠をとり、息抜きに趣味を満喫するなどがおすすめです。
少し気持ちが上向いてきたら、次は今までの失敗を振り返ってみましょう。
勉強で予習と復習をするように、就活にも振り返りが大切です。
・どうしてESが通過しなかったのか?
・どうして面接でうまく話せなかったのか?
・どうしていつも二次面接止まりなのか?
上記の疑問を自分にぶつけると、徐々に改善点が見えてくるため、メモに書き残しましょう。
失敗の原因と思われる内容を調べる、もしくは人にアドバイスを求めるなどで、同じ失敗をしないことが重要です。
自己分析を再度実施する
「なぜうまくいかないのか」が見えないまま動いても成果は出にくくなるため、就活が失敗だと感じたら自己分析をやり直してみましょう。
いま一度自分の強みや価値観、やりたいことを整理し直せば、企業選びやアピール内容に一貫性が生まれます。
就活は自分を知ることから始まると捉えて、振り出しに戻るのも有効です。
企業選びの軸を見直す
自己分析をして自分の望みを再確認できたら、次は企業選びの軸を見直しましょう。
自己分析をやり直すと、企業を選ぶ基準にも変化が生まれます。
今まで自覚していなかった望みが見つかったなら、以前とは違う基準で志望企業を選べるはずです。
企業選びの軸がなかなか思い浮かばない人は、先輩理系就活生の意見を参考に見てみるのもおすすめです。
就職エージェントを利用する
自力だけで動くのがつらくなったら、プロのサポートを受けるのもひとつの方法です。
自分では気づけなかった強みや相性の良い企業を提案してもらえることもあります。
就職エージェントは非公開求人を持っていることもあり、就活の選択肢を広げる手段になります。
逆求人型サイトを利用する
就活に失敗したと思う理系就活生には、大手ナビサイトしか使っていない方も少なくありません。
大手ナビサイトは規模が大きい分、大手企業や有名企業に埋もれてしまうことを危惧して、あえて利用しない企業もいます。
一つの就活サイトに限定していては、優良企業へのエントリーを逃してしまう可能性があります。
理系就活生には、理系に特化した逆求人型サイト「TECH OFFER」がおすすめです。
大手ナビサイトと異なり、理系就活生が応募するのではなく、あなたのプロフィールを見た企業から、インターンや選考案内などのオファーが届くサイトです。
もしかすると、今まで知らなかっただけで、あなたと相性の良い優良企業との出会いがあるかもしれません。
理系に特化した逆求人型サイトを活用して、失敗を挽回するチャンスを手に入れましょう。
就活で内定が出なかった場合の選択肢
卒業まで就活を続ける
卒業までに内定が出なかった場合でも、卒業時点で採用活動を行っている企業はまだあります。
中小企業やベンチャー、通年採用を行っている企業など、春以降も選考機会は存在します。
卒業までの数カ月を有効に使って自己分析を見直し、応募企業の幅を広げることで挽回は十分可能です。
焦らずに「今できること」を着実に積み重ねていくことが、新しい出会いにつながります。卒業間際でも内定を得た例は多く、最後まで諦める必要はありません。
大学院進学・留学
より専門性を高めたいなら大学院進学も有効な選択肢で、研究を深めるだけでなく就職先の幅も広がります。
また、留学で視野を広げることも、新しいキャリアのヒントになるかもしれません。
就職浪人
就職浪人は翌年の就活に再挑戦する選択肢の一つで、時間がある分、準備をじっくり進められるメリットがあります。
ただし、卒業後に発生する空白期間の説明が必要になるため、資格取得やアルバイトなどを通じて行動していたことを示せるようにしておきましょう。
派遣で実績を積む
派遣社員として実務経験を積むのも手で、未経験OKの技術職や研究補助など理系人材の派遣案件も多くあります。
職歴を作ることで正社員への道が開けることもあり、自分の適性を確認する場としても有効です。
公務員を目指す
安定した働き方を望む理系学生にとって、公務員は有力な選択肢のひとつです。
国家公務員や地方公務員の中でも、技術系区分で理工系の知識を活かせる職種は数多くあります。
環境、土木、機械、電気、農業、化学など幅広い分野で理系人材が求められています。
筆記試験や面接対策には一定の準備が必要ですが、スケジュールが明確なため計画的に進めやすいのが特長です。
民間との併願も可能で、早めに検討を始めれば複数の進路を視野に入れた就活ができます。
就活に失敗したときの心構え
同じ失敗を繰り返さないように準備する
落ちた理由を放置したまま次の選考に進んでも、また同じ壁にぶつかることがあります。
同じ失敗を繰り返さないためには、選考ごとに面接内容や企業研究の精度、自己PRの伝え方を振り返り、「何を改善すべきだったか」を確認することが大切です。
過去の失敗から学び、次の行動に反映することで就活力は着実に高まります。
人と自分を比較しない
友人が内定をもらった話を聞くと、つい焦ってしまうかもしれませんが、就活のペースや相性の良い企業は人それぞれです。
比較すればするほど、自分にとって大事な軸がぶれてしまうケースもあります。
大切なのは「どこに決まるか」より「どこで納得して働けるか」で、他人のスピードに振り回されず自分に合った道を探すことが何よりも大切です。
自分だけで頑張らず人に頼る
大学のキャリアセンター、友人、OBOG、エージェントなど、自分以外の人や機関を頼りましょう。
就活に行き詰まったときに自分だけで抱え込んでしまうと、どうしても精神的な負担が大きくなります。
大学のキャリアセンターや友人などから客観的なアドバイスを受けることで、新しい視点やヒントが得られるケースもあります。
人に話すことで気持ちが整理されることも多く、孤立しないためにも誰かに相談する習慣を持つことが大切です。
焦って内定だけを目標にしない
「とにかく早く内定を決めたい」という気持ちが強くなると企業選びが雑になり、入社後のミスマッチにつながるリスクが高まります。
焦って妥協してしまうよりも自分の希望や価値観に合った企業をじっくり見つける方が、結果的に長く続けられる仕事につながります。
失敗を新しい企業と出会うチャンスと捉える
就活がうまくいかなかった経験があるからこそ、自分に本当に合った企業に出会えるケースも少なくありません。
就活での失敗は、ただの「落選」ではなく自分の視野や選択肢を見直すきっかけになります。
失敗は痛みを伴いますが「合わなかっただけ」と切り替えることで、次の選択に柔軟性が生まれます。
選考での経験も積み重ばって面接力や企業研究の質も上がっていき、うまくいかなかった経験も出会い直すチャンスと捉えれば、就活を前向きに進められます。
就活に失敗しても人生を終わらせないために知っておきたいこと
新卒の条件は大学卒業後3年以内
「卒業したらもう新卒扱いされない」と思う方も多いかも知れませんが、実は多くの企業が“大学卒業後3年以内”であれば新卒として応募可能です。
上記は厚生労働省も認める方針で、大学卒業後3年以内であれば既卒でも新卒枠で選考を受けられます。
そのため、卒業後すぐに無理やり進路を決めなくても就活の方向を見極める時間は残されています。
焦って選んだ仕事で後悔するよりも、自分に合った道をじっくり探すことが大切です。
内定は就活のゴールではない
内定はあくまで社会人としてのスタートラインに立つための“通過点”で、ゴールではありません。
本当に大切なのは、どんな企業に入ったかより「どんな働き方をするか」「自分の価値をどう発揮するか」です。
内定を取ることに必死になりすぎて、就職後にミスマッチに気づいて離職するケースも少なくありません。
就活の最終目的は納得のいくキャリアを築くことで、目先の結果にとらわれずに自分らしい道を選び取る意識が未来を変えます。
まとめ
就活でうまくいかないことがあっても、人生が終わるわけではありません。
新卒扱いでの再挑戦も可能ですし、大学院進学や派遣、公務員などの道もあります。
何より大切なのは「失敗を経験に変える姿勢」と「自分に合った選択を見つける視点」です。
焦らず腐らず、必要なら誰かを頼って、自分らしい人生をじっくりと歩んでいきましょう。