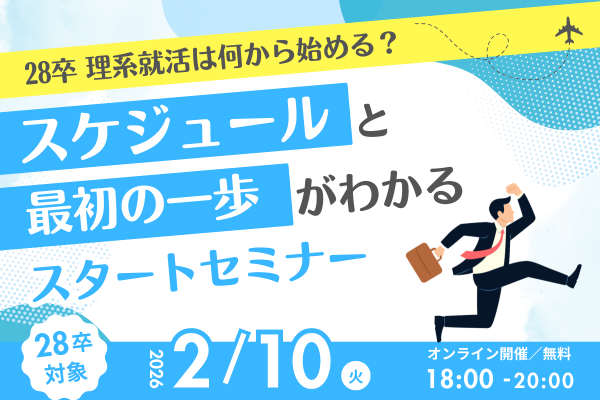こんにちは。理系就活情報局です。
理系就活生なら、一度は「研究職」として活躍する未来を想像したことがあると思います。
一方で、
「研究職に興味があるけれど、自分に向いているかわからない…」
「研究職に付いた場合、一日のスケジュールや求められることは何だろう?」
と感じている方も多いのではないでしょうか。
入社してからのミスマッチを防ぐために、本記事では研究職とは何か、仕事内容や研究職の種類、向いている人の特徴、一日のスケジュールなどを紹介します。
研究職を目指している理系就活生の方は、ぜひ参考にしてみてください。
研究職の種類
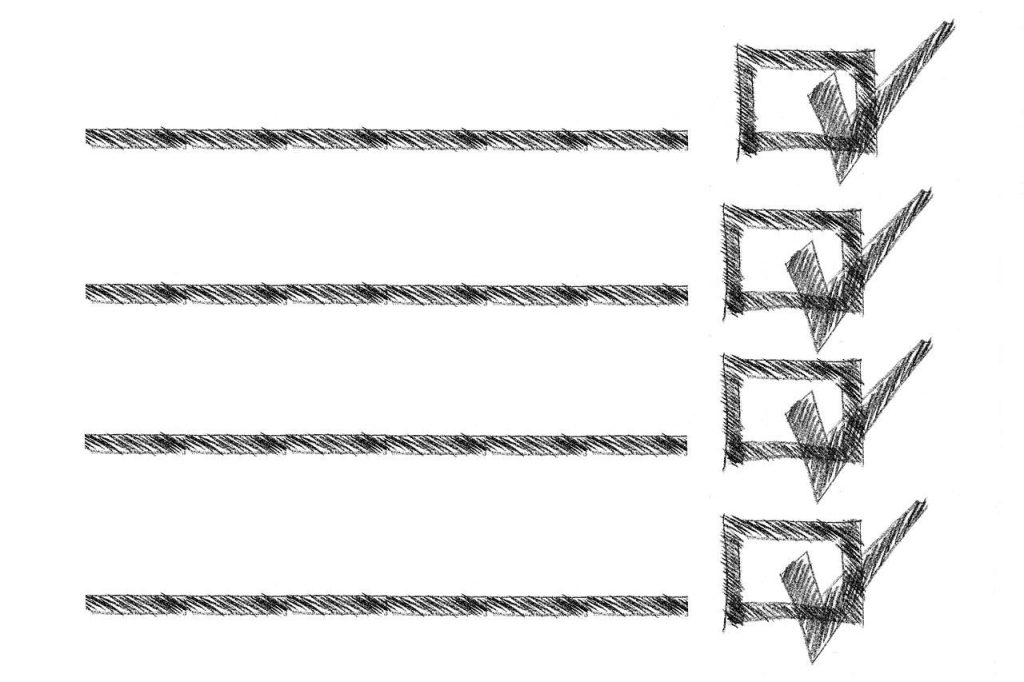
就職活動で使われる「研究職」という言葉は、実は一つの職種を指しているわけではありません。企業の研究活動は大きく分けると、以下のような役割の異なるプロセスで成り立っています。
・何もないところから知見を生み出す研究=基礎研究
・その知見を使える技術に育てる研究=応用研究
・製品として世に出せる形に仕上げる研究=開発研究
まずは、「研究の種類=研究の目的と立ち位置の違い」であることを押さえておきましょう。
基礎研究
基礎研究は0から1を生み出す研究で、研究プロセスの最も上流に位置する分野です。
まだ世の中で明らかになっていない現象や仕組みを解明し、新しい理論や知見そのものを生み出すことを目的とします。
「この物質にはどんな性質があるのか」などの問いに向き合い、将来的な応用可能性はあってもすぐに実用化を前提としない点が特徴です。
応用研究
応用研究は、実用化を目指す研究で基礎研究で得られた知見をもとに「どう使えば価値になるのか」を探る研究です。
研究プロセスの中間地点にあたり、理論を現実の条件下で検証し、技術として成立するかを見極めていきます。
「基礎研究で分かった原理で、こういう性能が実現できるのではないか」などの仮説を立て、実験・検証を経て実用化へつなげます。
開発研究
開発研究は製品化・量産化につなげる研究で研究プロセスの最下流に位置し、実際に市場へ出すことを前提としています。
応用研究で確立された技術をもとに、性能・コスト・安全性・量産性などを満たす形に仕上げ、製品・サービスとして完成させることが目的です。
研究職の仕事内容

研究職の仕事は、ひらめきだけで進むものではありません。
企業でも大学でも、研究は一定のフローに沿って進められる知的生産活動です。
企業研究の場合は、事業・製品・技術戦略と結びついた研究テーマを再現性と根拠をもって前に進めることが求められます。
以下では、研究職の基本的な仕事内容を4つのステップに分けて解説します。
研究テーマの設定
研究の出発点となるのが、研究テーマの設定です。
大学では学生自身がテーマを提案するケースもありますが、企業では以下のような組織の目的に基づいてテーマが与えられます。
・事業課題
・技術的なボトルネック
・中長期的な研究戦略
重要なのは、「何を明らかにしたいのか」「その研究がどんな価値につながるのか」を言語化できる状態でスタートすることです。
文献や先行研究の調査
テーマが決まったら、まず行うのが文献調査・先行研究の確認です。
企業研究における文献や先行研究の調査では特に以下の点も重要になります。
・すでに解決されていないか
・他社や他分野で類似技術が存在しないか
・特許として押さえられていないか
既存研究を把握し、「何が分かっていて、何がまだ分かっていないのか」を明確にして無駄な研究を避ける役割を果たします。
実験と検証
文献調査を踏まえて、仮説を立て、実験・検証を行います。
企業研究では、以下のような実用を見据えた視点が強く求められます。
・再現性があるか
・条件が変わっても成立するか
・スケールアップが可能か
単に「うまくいった」ではなく、なぜそうなったのかを説明できるデータを積み上げなければなりません。
研究成果の報告
研究は、成果を共有・説明して初めて価値になる仕事です。実験結果は社内報告資料や技術レポートとしてまとめられ、上司やチーム、関連部署に向けて報告されます。
企業研究では、「専門外の人にも分かる説明力」「結論と根拠を簡潔に示す力」が特に重視される点が特徴です。
報告内容が、次の研究テーマ設定や、応用研究・開発研究への展開につながっていきます。
企業の研究職と大学の研究職の違い
研究職と聞くと、大学での研究生活をそのまま延長したイメージを持つ学生も少なくありません。しかし、企業と大学の研究職は、同じ研究でも役割が大きく異なります。
以下に、企業と大学の研究職の主な違いをまとめました。
| 企業の研究職 | 大学の研究職 | |
| 研究の目的 | 事業・製品・技術競争力への貢献 | 学術的価値の創出・知の蓄積 |
| テーマ設定 | 会社の戦略・事業課題に基づく | 研究者の関心・専門性が中心 |
| 成果の評価 | 実用性・再現性・事業への影響 | 論文数・被引用数・学会評価 |
| 研究期間 | 数か月〜数年(比較的短中期) | 数年~長期 |
| 自由度 | 制約が多い(コスト・納期など) | 比較的高い |
| 必要な力 | 研究力+説明力・調整力 | 専門性・探求力 |
| 対象読者 | 社内の非専門家も含む | 同分野の研究者 |
就活で重要なのは、どちらが良いかではなく、自分がどちらに適性があるかを理解することです。
自分の適性もですが、キャリアの方向性なども踏まえて選択しましょう。
研究職の1日の流れ
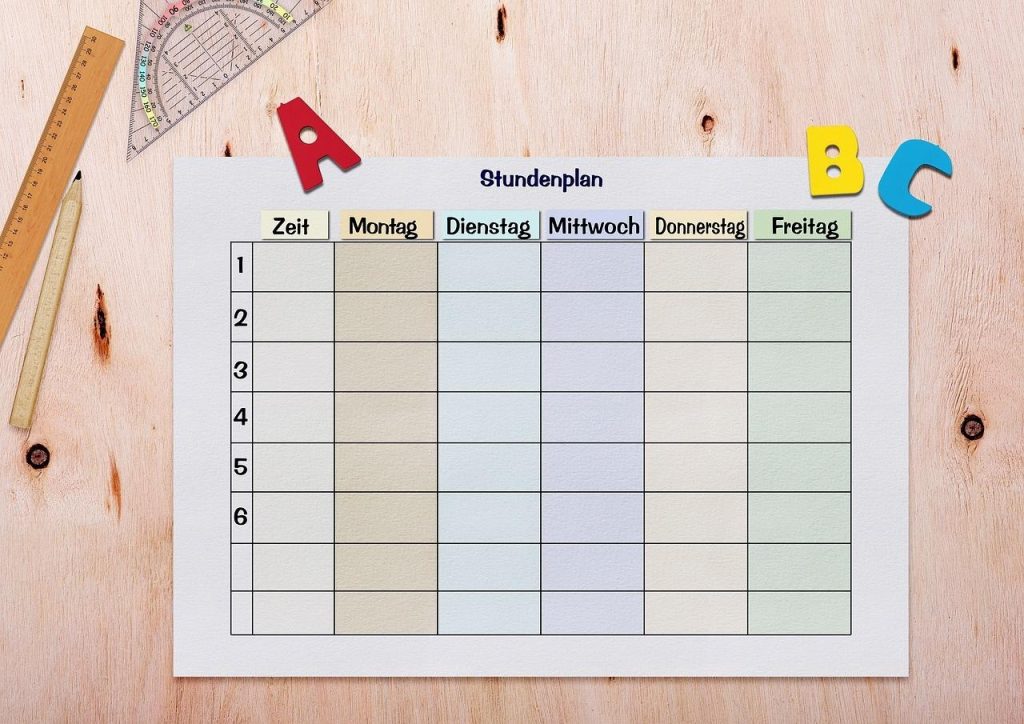
研究職の働き方は、専攻分野によって大きく異なります。以下では、就活生から質問の多い4分野を例に1日の流れを紹介します。
化学系研究職の1日
| 時間帯・項目 | 内容 |
| 午前 | ・実験準備(試薬・装置の確認) ・安全確認・実験条件の最終調整 |
| 日中 | ・合成・分析などの実験 ・データ取得・途中経過の記録 |
| 午後 | 実験結果の整理・考察 ・条件変更や次回実験の検討 |
| 特徴 | ・実験時間が長く、計画性が重要 ・安全管理・再現性が強く求められる |
機械系研究職の1日
| 時間帯・項目 | 内容 |
| 午前 | ・設計検討・シミュレーション ・試作仕様の確認 |
| 日中 | ・試作品の評価試験 ・測定・不具合分析 |
| 午後 | ・データ整理・改善案の検討 ・他部署(生産・設計)との打ち合わせ |
| 特徴 | ・デスクワークと実機評価の両立 ・チームでの調整・議論が多い |
IT系研究職の1日
| 時間帯・項目 | 内容 |
| 午前 | ・アルゴリズム検討・実装 ・データ前処理 |
| 日中 | ・プログラム開発・検証 ・モデル評価・改善 |
| 午後 | ・結果の共有・レビュー ・次の検証テーマ整理 |
| 特徴 | ・実験=コード検証が中心 ・進捗が速く、試行回数が多い |
食品系研究職の1日
| 時間帯・項目 | 内容 |
| 午前 | ・試作準備・原料確認 ・官能評価の段取り |
| 日中 | ・試作・分析 ・味・食感・保存性の評価 |
| 午後 | ・データ整理・改良検討 ・品質・法規関連部署との確認 |
| 特徴 | ・技術と「人の感覚」の両立 ・法規・品質制約を強く意識する |
【業界別】研究職の仕事内容の違い

研究職といっても、所属する業界によって研究の目的・進め方・求められる力は大きく異なります。そのため、「何を研究したいか」だけでなく「どの業界で研究したいか」の視点も重要です。
以下では、就活生から志望の多い主要業界について研究職の仕事内容と特色を整理します。
化学
化学業界の研究職は、新規化合物の探索、反応プロセスの開発、機能性材料の設計などを担います。基礎研究から応用・開発研究まで幅広く存在し、他業界の技術基盤を支える役割も大きいのが特徴です。
| 項目 | 内容 |
| 主な研究内容 | ・新規化合物・触媒の開発 ・反応条件・製造プロセスの最適化 ・物性評価・機能性検証 |
| 特徴 | ・実験・分析が中心 ・安全性・再現性が重視される ・研究成果が他業界へ展開されやすい |
製薬・バイオ
製薬・バイオ業界の研究職は、創薬・診断・再生医療など生命科学を基盤とした研究を行います。長期的な研究が多く、1つの成果が出るまでに年単位の時間を要するケースも珍しくありません。
| 項目 | 内容 |
| 主な研究内容 | ・新薬候補物質の探索 ・細胞・遺伝子レベルでの作用解析 ・非臨床試験に向けた基礎検証 |
| 特徴 | ・規制・倫理の制約が厳しい ・博士人材の比率が高い ・社会的責任が大きい |
食品
食品業界の研究職は、味・食感・香りといった感覚評価と、科学的データの両立が求められます。消費者に近い位置で研究が行われる点が特徴です。
| 項目 | 内容 |
| 主な研究内容 | ・新商品・改良品の試作 ・保存性・品質劣化の検証 ・原料・製造条件の最適化 |
| 特徴 | ・官能評価が重要 ・法規・品質管理との連携が多い ・社会へのアウトプットが早い |
自動車・電機
自動車・電機業界の研究職は、機械・電気・情報を組み合わせた技術開発が中心です。製品化を強く意識した研究が多く、開発研究の色合いが濃くなります。
| 項目 | 内容 |
| 主な研究内容 | ・新技術・新機構の検証 ・性能・耐久・安全性評価 ・次世代製品に向けた技術探索 |
| 特徴 | ・チーム・部署連携が多い ・試作・評価の比重が高い ・スケールの大きい研究テーマ |
素材・材料
素材・材料業界の研究職は、金属、樹脂、セラミックスなどの基礎性能を高める研究を行います。最終製品には直接見えにくいものの、製品性能を左右する重要な役割を担います。
| 項目 | 内容 |
| 主な研究内容 | ・材料組成・構造設計 ・強度・耐熱・耐久評価 ・製造プロセス検討 |
| 特徴 | ・長期視点の研究が多い ・実験・分析の積み重ねが重要 ・他業界との接点が多い |
IT・AI
IT・AI分野の研究職は、アルゴリズム開発やデータ解析を通じて新たな価値を生み出す研究を行います。他業界と組み合わさることで、応用範囲が急速に広がっています。
| 項目 | 内容 |
| 主な研究内容 | ・機械学習モデル・アルゴリズム開発 ・データ分析・評価 ・実装・検証 |
| 特徴 | ・実験=プログラム検証 ・技術進化が非常に速い ・学会・論文との距離が近い |
研究職の主な就職先

民間企業の研究部署
民間企業での研究職は、主にメーカーなどでの商品開発などに携わる仕事です。研究内容は部署やメーカーの方針に沿って行われ、多くの場合はチームで研究を進めます。他の部署との連携が必要な場合もあるため、一定のコミュニケーション能力は必要です。公的機関に比べ、収入が比較的高いことなどがメリットとなります。
また、三菱総合研究所など民間の研究施設への就職も可能です。民間の研究機関であるため利益追求ではなく、専門性の高い研究に携われます。特徴をしっかりと把握したうえで、自身の専門性を活かせる進路をみつけることが必要です。
大学の研究室
大学教員として採用される、大学研究職は代表的な就職先のひとつです。博士課程を修了したうえでポストドクター(ポスドク)をまずは目指します。ポスドクの任期は約2〜3年程。その間に研究の成果を残せれば、准教授などに就くことが可能です。
教授になるには大学によっても異なりますが、博士課程修了後から15年前後は必要になります。その間は教授の研究サポートが中心になるため、教授の方針への理解と相性が良いことが大切なポイントです。
公的機関
公的機関の研究職とは、各省庁や地方公共団体の研究所にて勤務する研究職です。具体的な勤務先としては、〇〇産業技術研究所などのような名称の公設試験研究機関などです。厳しい試験に合格すれば、警視庁や全国の警察本部にある科学捜査研究所などでも研究に携われます。
公的機関の研究職は化学・物理・法律・心理学など、さまざまな知識が求められるのも特徴のひとつです。国や地域のためになる研究が多いため、やりがいを感じながら働き続けられます。
研究職の魅力・やりがい

研究職の魅力は、単に専門知識を使えることだけではありません。
企業研究では、自分の研究が社会や人の生活とどのようにつながっているのかを実感できる場面が多くあります。
ここでは、押さえておきたい研究職の代表的なやりがいを3つ紹介します。
社会貢献できる
研究職の大きな魅力の一つが、社会課題の解決に研究を通じて関われることです。医薬品・食品・エネルギー・ITなど、多くの分野で研究成果が人々の生活を支えています。
企業研究では、「この技術でどんな課題が解決できるのか」「誰の役に立つのか」を意識しながら研究が進められます。そのため、研究と社会のつながりを実感しやすい点が特徴です。
成果を目で感じられる
研究職では、自分が関わった成果が以下のような具体的な形として世に出るケースがあります。
・製品
・技術
・サービス
大学研究では、論文やデータが成果の中心になりがちです。しかし、企業研究では「実際に使われる」「売られる」場面に立ち会えるケースも多く、成果を目で見て実感できる達成感があります。
業務を通じて成長を実感できる
研究職で身につくのは、専門知識だけではありません。
業務を通じて、以下のようなどの分野でも通用する汎用的な力が鍛えられます。
・課題設定力
・仮説構築力
・論理的説明力
・他部署との調整力
特に、企業研究では「分かりやすく伝える力」「制約条件の中で最適解を探す力」が求められます。そのため、研究者としてだけでなくビジネスパーソンとしての成長も実感しやすい仕事です。
研究職の年収

研究職の年収は、「研究職だからこのくらい」と一律で決まるものではありません。所属する組織やキャリアの段階によって大きく差が出るのが実情です。
就活の段階では初任給や新卒年収に目が向きがちですが、研究職の場合は長期的なキャリア設計も含めて理解しておきましょう。
なお、本記事で紹介する年収額はあくまで一般的な目安で実際の支給額は企業規模や役職、個人の成果により異なります。そのため、厚生労働省の賃金構造基本統計調査や各社の採用情報もあわせてご確認ください。
研究所:年俸制で600万円以上
企業内研究所や独立系研究機関では年俸制が採用されているケースも多く、修士・博士修了者を前提に600万円以上からスタートします。
600万円以上と高水準で給与は、以下のような能力を期待されていることの裏返しでもあります。
・高度な専門性
・即戦力としての研究遂行能力
成果や役割に応じて評価されるため、プレッシャーや成果責任が大きい点も理解しておく必要があります。
民間企業:新卒で300万円~400万円
多くの民間企業では、研究職であっても新卒時点の年収は300万~400万円程度から始まります。上記の給与は、他の技術職・総合職と大きく変わらない水準です。
ただし、研究職は以下の要素によって中長期的に年収が伸びやすい傾向があります。
・昇進
・専門職制度
・成果評価
就活の段階では初年度の年収だけでなく、5年後・10年後のキャリアパスを見る視点が重要です。
なお、理系職種全体の給与事情について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて参考にしてください。
大学:800万円~1,000万円
大学の研究職(教員)の場合、800万円~1,000万円という年収は主に教授クラスに到達した場合の水準です。
一方で、以下のような若手〜中堅層では高年収と言えない時期が長く続くケースも少なくありません。
・助教
・講師
・准教授
また、任期付きポストや競争的資金への依存など、雇用の安定性の観点ではリスクもある点を理解しておく必要があります。
研究職に向いている人

探究心が旺盛な人
研究職は、新しい商品や技術を生み出すために、先の見えない目標に挑戦し続ける仕事です。
そのため、研究職には、研究を楽しむ探求心が求められます。
ものごとに対して「なぜそうなるのか」「目標を達成するためにはどうしたらいいのか」と常に考えながら、挑戦し続けられる探求心を持っている人は、研究職に向いています。
研究職は、自分の興味のある分野だけを研究できるとは限りません。
興味のない分野が仕事になることも念頭に置いて、研究職を目指すのか検討してみてください。
粘り強く一つのことに取り組める人
研究で成果を上げるためには、長い時間と試行錯誤が必要です。
数年がかりの研究に携わることもあるため、最後まで諦めず、根気よく一つのことに取り組める人は研究職に向いています。
根気強く研究に取り組み、成果を上げたときには大きなやりがいを感じられるでしょう。
飽きることなく最後まで責任を持ってものごとに取り組める人は、研究職でも結果が出せるはずです。
失敗しても前向きに考えられる人
研究では、自分が立てた仮説に対してさまざまな検証を繰り返します。
仮説がすぐに立証されるとは限らないため、粘り強く取り組まねばなりません。
それでも、何度も同じことに取り組み、失敗を繰り返すうちに、気持ちが沈んでしまうこともあるでしょう。現実を受け止めることも大事ですが、意識をポジティブに保つことも必要です。
そんな時、失敗は失敗として受け止め、前向きに気持ちを切り替えられる人は研究職に向いています。
コミュニケーション能力がある人
もしかすると、「研究職はコミュニケーション力があまり必要ない」と考えている理系就活生もいるかもしれません。ですが、それは大きな間違いです。
研究職にも、コミュニケーション力は重要です。
というのも、研究は1人で黙々と行うのではなく、チームで協力し合って1つの研究を行うからです。
他の研究者と情報共有し、密に連携を取れなければ研究職は難しいでしょう。
また、同じ研究者だけでなく、他部署や社外の人とのコミュニケーションも求められます。
研究職でない人に自分たちの研究について、専門用語を交えずわかりやすく説明し、理解してもらわなければなりません。
さまざまな分野の人とコミュニケーションを図ることで、研究に役立つ情報が得られるケースもあるでしょう。
そのためにも、コミュニケーション力は欠かせないスキルです。
研究職に向いていない人

研究職は専門性の高い魅力的な仕事ですが、誰にとっても最適な職種とは限りません。
以下では、研究職で苦労しやすいタイプを3つ紹介します。
飽き性な人
研究職の仕事は、1つのテーマに数年単位で取り組むケースも珍しくありません。思うような結果が出ない期間も長く、同じ実験や検証を何度も繰り返す場面があります。
常に新しい刺激がないとモチベーションを保ちにくい人は、研究職の進め方にストレスを感じやすい傾向があります。
短期間で次々と環境を変えたい人
研究職の仕事は一つのテーマで成果が出るまでに長い時間がかかるケースが多く、じっくりと腰を据えて取り組む姿勢が求められます。
そのため、数年単位で環境を変えてステップアップしたい方は長期的な積み重ねが必要な研究職とマッチしにくい場合があります。
研究職は、特定の技術や社内環境に深く精通していることが評価につながりやすい職種です。そのため、頻繁に環境を変えるよりも一つの場所で専門性を深めていくことに価値を感じる人の方が向いています。
閉鎖的な環境が苦手な人
研究職は機密情報・特許・未公開データを扱うことが多く、情報共有の範囲が限定されがちです。
また、研究所内や特定チームでの業務が中心となり、外部との接点が少ない時期もあります。
人との関わりが多い環境やコミュニケーションを重視した働き方を求める人にとっては、閉鎖的に感じられるかもしれません。
研究職を志望するなら

研究職は就職難易度が高いことを理解する
研究職は理系の花形的存在ですが、採用のハードルが高いのも事実です。
研究職の募集は、その企業や大学が求める専門性を持っていることが前提です。
また、研究職の募集では通常の選考過程に加えて論文やレポートの提出を求められる場合もあります。
そのため、研究職の採用は「専門的な知識を身に付けているか」という点で、ほかの職種よりもシビアに判断されます。
研究には成果が求められる
研究職の仕事は一朝一夕で結果が出るものではありません。
中には、数年〜10年以上かかって、ようやく成果が出る研究もあるでしょう。同時に、どれだけ熱心に時間をかけたとしても、思うような成果が出ない場合も予想されます。
研究職はやりがいのある仕事ですが、だからといってかけたコストを無視することはできません。成果が出ない場合はコストをかける必要がないとして、研究を打ち切られてしまうケースもあるのです。
目指していた研究職になれたとしても、やりたい研究が打ち切りとなれば、別の研究を進めることになります。
「必ずしも自分がやりたいことだけができるわけではない」と理解した上で、研究職を目指しましょう。
ES作成や技術面接に向けて対策を行う
研究職志望の就活では研究内容よりも、「どう考え、どう進め、どう伝えたか」が評価されます。そのため、ES作成と技術面接はセットで対策することが重要です。
【ES作成のポイント】
エントリーシートでは、専門用語を並べるよりも研究の背景・課題・工夫・結果を論理的に説明できているかが見られます。
特に意識したいのは以下の点です。
・研究テーマの背景(なぜその研究が必要か)
・自分が担った役割と工夫した点
・困難にどう向き合い、どう乗り越えたか
・得られた結果・学びをどう次に活かせるか
研究が高度であるかよりも、思考プロセスが伝わるかどうかが評価の分かれ目になります。
なお、研究職特有のガクチカの書き方や例文については、以下の記事で詳しく解説しています。
【技術面接のポイント】
技術面接では研究内容について深掘りされるケースが多く、「理解してやっているか」「再現性や限界を把握しているか」が確認されます。
対策としては、以下のような準備が有効です。
・研究内容を非専門家にも説明できるレベルで整理する
・仮説を立てた理由を言語化する
・うまくいかなかった点と改善策を説明できるようにする
【ESと面接は同じ軸で準備する】
ESと技術面接は別物ではありません。ESに書いた内容が面接での質問材料にもなるため、一貫したストーリーで説明できる状態を目指しましょう。
研究経験を研究室内だけで通じる話で終わらせず、企業で働く研究者としての視点で語れるかどうかが選考突破の鍵になります。
なお、技術面接でよく聞かれる質問や回答例については以下の記事もチェックしておきましょう。
TECH OFFERに登録する
研究職は狭き門だからこそ、自分から応募するだけでなく企業から見つけてもらう待ちの姿勢も併用するのが賢い戦略です。
そして、企業から自身を見つけてもらう方法の一つが理系学生向けスカウト型就活サービスであるTECH OFFERです。
TECH OFFERでは研究内容や専攻、スキルを登録しておくと企業の研究部門・技術部門から直接オファーが届く仕組みになっています。
特に、「自分の研究内容がどの業界・企業に評価されるのか分からない」と感じている学生にとって、視野を広げるきっかけになります。
研究職の仕事内容に関するよくある質問

研究員は何をする職業ですか?
研究員は新しい知見や技術を生み出し、社会や企業の価値につなげる職業です。
具体的には研究テーマの設定や文献調査、実験・検証、結果の分析、報告など一連の研究プロセスを担います。
大学の研究員は学術的価値の創出が中心ですが、企業の研究員は事業・製品・技術戦略への貢献が求められる点が大きな違いです。
研究職に向いている人は?
研究職に向いているのは、以下のような特徴を持つ人です。
・一つのテーマに粘り強く取り組める
・結果がすぐに出なくても試行錯誤を続けられる
・論理的に考え、説明することが苦にならない
・専門性を深めることにやりがいを感じる
研究が好きな気持ちに加え、地道な積み重ねを仕事として続けられるかが重要なポイントになります。
メーカー研究職の難易度は?
メーカーの研究職は、全体的に採用枠が少なく、難易度は高めです。
特に、基礎研究寄りのポジションでは修士・博士が前提となる場合も多く、研究内容と企業の技術領域のマッチ度が強く見られます。
一方で、開発研究に近い研究職では学部卒・修士卒でも採用されるケースがあります。企業ごとの研究職の位置づけを見極めることが、応募する上で重要です。
研究職の年収はいくらですか?
研究職の年収は、所属先とキャリア段階によって大きく異なります。
・民間企業(新卒):約300万〜400万円
・研究所(年俸制):600万円以上の場合も
・大学教員(教授クラス):800万〜1,000万円程度
就活の段階では初年度の年収だけでなく、中長期的な昇進・専門職制度も含めて確認することが大切です。
研究職の女性の割合は?
研究職における女性比率は業界・分野によって差がありますが、全体としてはまだ男性比率が高い傾向にあります。
一方で、近年は「女性研究者の採用強化」「産休・育休制度の整備」「研究職の働き方改革」に取り組む企業・大学も増えています。
女性が長期的に研究を続けられる環境は、少しずつ整いつつあるのが現状です。
まとめ
研究職は、専門性を活かしながら社会や技術の発展に貢献できる、やりがいの大きな仕事です。
一方で、研究の種類や業界、働き方、年収、向き・不向きなど事前に理解しておくべきポイントも多い職種でもあります。就活では、研究が好きだからだけで判断するのではなく、自分の価値観・キャリア観と研究職の特性が合っているかを丁寧に考えましょう。
研究内容の整理やES・技術面接対策、就活サービスの活用を通じて自分に合った研究職・企業を見つけることが納得のいく就活につながります。