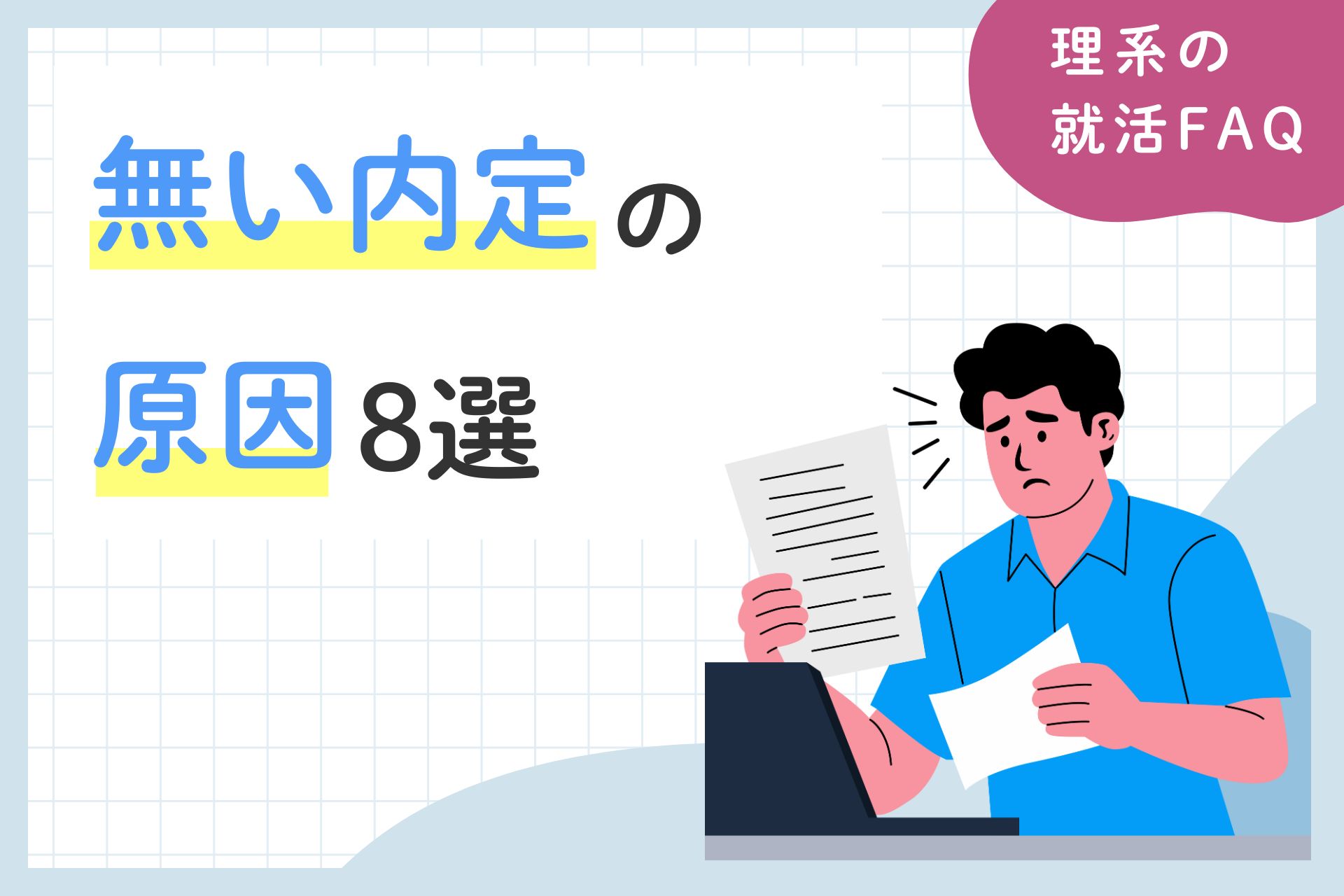こんにちは。理系就活情報局です。
今回は、理系学生の平均エントリー数や理系学生におすすめの就活方法について解説します。
3年の春休み、4年生の0学期といわれる時期から企業のエントリーが始まり、本格的に就活が始まります。
就活が本格化する時期に周りの学生が、どのくらいエントリーを出しているか気になりませんか?
この記事では理系学生がエントリーする企業数の平均や、エントリー数を増やすと生じるメリット&デメリットを紹介します。
就活で落ちるのは当たり前?
就活の進み具合は人それぞれ
理系学生における就活の進み方は、運やタイミングにも左右されます。
早く内定が決まる人もいれば、納得のいく企業に出会うまで時間がかかる人もいるため、周囲のペースと比べすぎず、自分に合った進み方を大切にしましょう。
全落ち経験のある学生が最終的に第一志望に受かることも珍しくなく、1つの結果で落ち込むより次に活かす意識が大切です。
内定の平均時期を目安に就活の見直しを
文系よりも理系は内定の時期が少し遅れる傾向にありますが、それでも6月末までに7〜8割の学生が内定を獲得すると言われています。
もし7月を過ぎても進展がない場合は、就活の進め方を見直す良いタイミングです。
自己分析や選考対策、企業の幅などを点検して、今の方法が自分に合っているかを一度整理してみましょう。
理系就活生・院生は平均何社受けるのか?
本章では理系学生の平均エントリー数を解説します。
これから就活を迎える理系学生のみなさんは、同期の就活生たちが何社くらい受けるのか気になると思います。
不安に思っている方も、ある程度絞り込めている方も是非ご覧ください。
理系学生の平均エントリー数は約7社
公益社団法人全国求人情報協会「2024年卒学生の就職活動の実態に関する調査」によると、理系学生のエントリーに関しては以下の結果が判明しています。
・プレエントリー11.5社
・エントリー7.2社
理系学生は文系学生と比較すると、受ける企業数をかなり絞り込む学生が多いことが分かります。
理系学生は3年次になると課題研究や勉強でスケジュールが忙しくなるため、ESを作成する時間を削られることが要因だと考えられます。
人によって受ける数はそれぞれ
人によって就活のスタイルは異なるため、理系学生の平均エントリー数を基準にする必要はありません。
例えば内定を1社でも多く獲得したい学生はエントリーを増やしますが、第一志望の企業に集中するためにエントリー数を増やさない学生もいます。
みなさんが希望するスケジュールで就活を進めていただければと思います。
エントリー数を増やすメリット
本章ではエントリー数を増やすことで生じるメリットを紹介します。
エントリー数は就活の要となってくるため、企業選びはかなり慎重になっていきます。
エントリーを増やすと、就活生にどのような影響が起こるのかを解説します。
気持ちに余裕ができる
エントリーを増やすと、企業を比較する機会が増えます。
万が一志望する企業に落ちたとしても他に内定を獲得できれば、最終的に余裕を持って就活を終えることができます。
また各面接やWEBテストに対する精神的負担も分散されるため、仮に納得のいかない結果だとしても切り替えて先に進むことができます。
場数を踏める
複数の企業で面接を経験すると、だんだんと自分の型が定まり話し方が上達します。
第一志望の企業の前にある程度面接慣れをしておけば、第一志望の企業の面接ではしっかりと自分をアピールできます。
しかし注意していただきたいのは、ただ数をこなせば上達するわけではないことです。
毎度面接が終わった後に自分の発言を思い出し、改善点を分析することが重要です。
また自分だけでは分析が難しい場合には、家族や友人、大学のキャリアセンターで模擬面接を行ってもらい、第三者の意見を参考にしてみましょう。
本当に自分にあった企業を選べる
エントリーの数を多くすれば、単純に内定数も増える可能性があります。
内定を頂いた企業同士を比較しながら、本当に自分と合う企業かを考える時間を設けることは、ミスマッチを防ぐ方法として有効的です。
また多くの選択肢の中から、企業を決められない方もいるでしょう。
改めて自分のキャリアを考える機会となるため、就活生にとって複数の企業から内定を得るのはメリットといえます。
エントリー数を増やすデメリット
エントリーを増やすことで得られるメリットもありますが、もちろんデメリットもあります。
本章ではエントリーを増やしすぎると起こる問題を解説します。
企業研究に時間をかけられない
エントリーを増やした分、限られた就活スケジュールでは1つの企業に費やせる企業研究の時間は少なくなります。
複数受ける企業を受ける場合には、優先順位を決めて本命の企業に十分な時間を割きましょう。
複数の企業を研究していると面接前に混乱するため、企業別にノートにまとめておいて要点をおさえることをおすすめします。
ESを書くためにかなり労力を使う
就活の鬼門となるのがES(エントリーシート)です。
ほとんどの企業ではESを起用しているため、企業を受ければ受けるほどESを書く枚数も増えます。
効率的にESを書くポイントは、以下の2つになります。
・自己分析をおこなっておく
・自分が頑張ったことや挫折した経験などのエピソードを用意しておく
スケジュール調整が難しくなる
エントリー開始から本面接までの就活スケジュールは、基本的にどの企業も同じです。
受ける企業が多いと、1日に面接が連続するケースが増えます。
オンライン面接も増えているため、移動の時間を省くことはできますが、対面面接が多いと一日に何度も移動する可能性が増えます。
ハードな就活を乗り越えるには、体力面も鍛えておくことが必要であると同時に強い精神力を持っておくことが大切です。
理系就活で何社を受けるのか効率的に決めるポイント
就活で受ける企業の数は、就活スタイルの違いから個々人で異なります。
一方で自分が何社を受けるのか決めるポイントがわかれば、参考になる方は多いでしょう。
本章では、理系就活で何社を受けるのかを効率的に決めるポイントを解説します。
自己分析を軸に決める
自分に合う企業を見極めるには、自己分析から判明した就活の軸を用いるとよいでしょう。
就活の軸を条件化していけば、企業を絞ることが可能です。
気になる企業は数多くあるかもしれませんが、自分にマッチしていることを基準にすれば、受ける企業数も自然と決まります。
自己分析から判明した条件に、合致する企業が15社だとします。
15社であれば就活も無理なく進められる企業数のため、スケジュール管理をしたうえで就活を進めるとよいでしょう。
インターンシップに参加する
選考を受けるか否かを見極めるには、実際に企業と接触した際の感触も参考になります。
特にインターンシップに参加をすると、企業の内部を見ることができるため、自分に合うか否かの判断が可能です。
就活の軸には合致するが、インターンシップに参加した結果、自分に合わないとわかれば、受ける必要はなくなります。
関連記事:https://techoffer.jp/rikeishukatsu/intership-itsukara/
選考スケジュールを確認する
自分が何社を受けるのか決めるポイントには、選考スケジュールや選考対策にかかる時間も挙げられます。
企業の選考スケジュールが重複している企業は、条件に合致している企業が複数社ある場合でも、受けられる数が1社に限定されます。
気になる企業があっても、選考スケジュールから自分が受ける企業数が限定可能です。
またESを書き上げるスピードや面接対策に要する時間がわかると、一定期間内に自分が対策できる企業の数がわかります。
選考スケジュールがわかる場合には、対策できる企業の数から受ける企業数が絞れます。
数字に捕らわれず無理のない範囲でエントリーする
就活では「○社は受けないと危ない」と言われることもありますが、エントリー数が多すぎると準備が追いつかず、就活の質が下がる恐れがあります。
大切なのは、自分がしっかり対策できる数に絞りながら、もしものための余裕も持たせること。
最初は多めに受けて、徐々に本命に注力していく形が負担も少なくおすすめです。
全落ちしたくない!選考に通過する人がやっていること
業界・企業研究を徹底する
就活では、業界・企業研究を徹底しましょう。
「受ける企業がどんなビジネスをしているか」「求める人材像はどのようなものか」を理解すれば、説得力のある志望動機が書けます。
なんとなく受けた企業よりも情報を深掘りして受けた企業の方が通過率が高くなり、業界の流れや競合比較なども押さえておくと面接でも一歩差をつけられます。
適性検査対策をおろそかにしない
適性検査対策をおろそかにしないことも、大切なポイントです。
SPIや玉手箱などの適性検査は書類選考の前に足切りされるケースも多く、意外と見落とされがちです。
適性検査で苦手な分野がある場合は、早めに練習して慣れておきましょう。
専用のアプリや問題集を使って、毎日少しずつ取り組むだけでも本番での精度とスピードが上がります。
ESのフィードバックをもらっている
選考がうまくいかない理系就活生は、キャリアセンターなどでESのフィードバックをもらいましょう。
自分だけでESを書いても見落としや曖昧な表現に気づけないことがあり、なかなか通らない人は客観視が足りていないのかもしれません。
キャリアセンターや先輩、OB訪問でESを見てもらうことで改善のヒントがもらえます。
実際の選考に通ったESを参考にしたり、自分の文章を読み返す習慣をつけたりすると質がぐんと上がります。
模擬面接で選考の対策をしている
あまり緊張しないという人も、必ず模擬面接をしておきましょう。
「面接で緊張して話せなくなる」「質問にうまく答えられない」のは準備不足のサインです。
模擬面接で人に見てもらいながら練習すれば、内容だけでなく伝え方の改善もできます。
話す順番を整理するだけでも印象が変わるため、選考前には一度実践の場を作っておくと安心です。
選考に落ちた時はどうする?メンタルリセット法
振り返って改善したら気持ちを切り替える
落ちた理由がある程度わかったら、そこで反省は終わりにし、必要以上に引きずらず次の企業に気持ちを向けることが大切です。
完璧な人はいないので、1社ごとに改善点を拾っていければOKで、前より少しでもよくなっていれば確実に前進しています。
好きなことをする時間を作る
就活でストレスが溜まりすぎると、判断力も鈍ってしまいます。
好きなことをする時間をあえて確保することは、気分転換だけでなく集中力の回復にもつながります。
思い切って一日休むのも、長い就活では立派な戦略です。
成長のチャンスだとポジティブに考える
選考に落ちた経験は、実は自分を知るための貴重なヒントです。
「何がうまくいかなかったのか」「次はどう伝えれば良いのか」を学ぶことで、就活力は確実にアップします。
「選考に通らなかった=失敗」ではなく、「次の成功につながる成長のチャンス」と考えることで前向きに就活を続けていけます。
理系就活のエントリー数でよくある質問
エントリー数を絞るのは危ない?
最初から本命数社に絞って就活を進めるのは、リスクが高いと言えます。
面接や適性検査など就活は実際に受けてみないと気づけない点も多く、本命でいきなり全力投球するのは危険です。
練習も兼ねて、ある程度の数を受けることで本志望の企業で上手く自己PRできるようになり、安心感につながります。
全落ちを考えるとエントリー数を増やすべき?
不安だからといってエントリーを増やしすぎると、対策が浅くなって逆に通過率が下がるケースもあります。
大切なのは「通りやすい数」ではなく「しっかり準備できる数」で、手が回る範囲で、種類の異なる企業をバランスよく選ぶのが理想的です。
理系学生はオファー型サービスで手札を増やそう
オファー型の就活サービスでは、プロフィールを充実させることで企業側からスカウトが届きます。
特に、理系学生は研究テーマやスキルを通じて技術力を評価されやすく、就活の幅を広げるうえで有効です。
理系就活生におすすめの就活サイトは、理系に特化したオファー型サイト「TECH OFFER」です。
TECH OFFERは隙間時間に研究内容などを登録しておけば、専門性とマッチする理系企業からオファーが届きます。
労力をかけずに優良企業と接点が持てるため、忙しい理系就活生にぴったりです。
TECH OFFERを活用して、将来の自分が気持ちよく働ける職場を見つけましょう。
まとめ
理系でも就活で落ちるのは普通のことです。
全落ちを防ぐには、対策を重ねながら冷静にエントリー数を調整し、メンタルを保つことが大切です。
焦らず着実に改善していけば、どこかで必ず巻き返せて結果がついてきます。
自分のペースで、納得のいく未来をつかみにいきましょう。






の書き方とは?書き方のコツや例文を紹介-150x150.jpg)