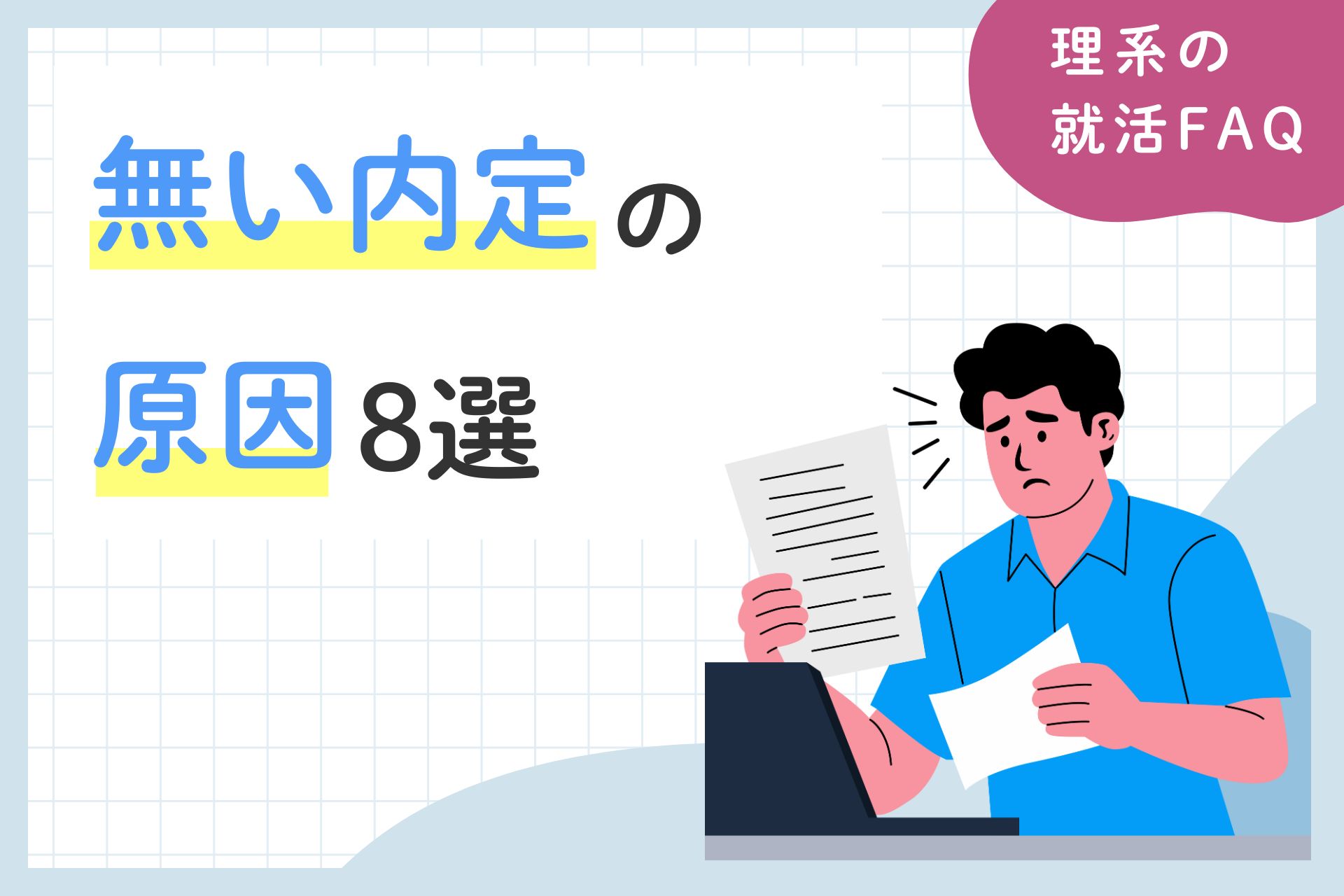こんにちは。理系就活情報局です。
今回は、理系学生は就活で何社受けるべきかについて解説していきます!
就活を始めて、それらの準備を進めていくうちに、一社出すのに時間がかかるけど、出した方がチャンスは多い。
「どうすれば理想のエントリー数になるんだろう。」というのは理系就活生が立ち向かう課題だと思います。
本記事では、「理系の就活は何社受けるべき?安心できて無理のないエントリー数とは?」というテーマで解説します。
エントリー数に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
○社しか受けてないのはやばい?
3社~10社しか受けてないと全落ちの可能性も
もし3〜10社程度しかエントリーしていない場合、リスクが高くなります。
エントリーから内定までは複数のステップがあり、思っている以上に通過率は低いのが現実です。
たとえ志望度の高い企業でも、面接の相性や倍率の高さによっては落ちてしまう可能性もあります。
エントリー数が少ないと極端な話、全落ちしてしまう恐れがあります。
何社受けて何社受かるのかは誰にもわからない
就活は運や相性の影響も大きく、何社受けても結果はやってみないとわかりません。
第一志望にすんなり通る人もいれば、20社以上落ちてようやく内定が出る人もいます。
事前に確実な数を読めないからこそ、ある程度余裕を持ったエントリーが必要です。
気になる企業は早めにエントリーして選考が進む中で選択肢を絞っていくと、焦らず就活を進められます。
理系就活生のエントリー数って?
理系就活生にとって周りがどれくらいエントリーシートを出しているかについて気になると思います。
そこで今回は理想のエントリー数を解説する前に、理系就活生が平均してどれくらいエントリーシートを出しているか解説していきます。
平均プレエントリー数
プレエントリーは企業の採用情報ページに登録したり、資料請求したりすることです。
そして、一般的な理系学生のプレエントリー数は20社を超える程度になります。
プレエントリーは20社程度でもES提出は5社程度といったデータもあり、プレエントリーはES提出よりも難易度が低くなっています。
そして、プレエントリーは個人情報と簡単な自己PRや志望動機だけでいいので、就活生にとっても比較的簡単にできるものになってます。
そのようなプレエントリーは企業の説明会や選考の情報を知ることを目的としていますが、本エントリーでは実際に企業に就職することを目的としています。
理系の学生の平均エントリー数は文系学生と比べて少なく、文系学生のプレエントリー数は約30社にもなります。
理系のエントリー数が少ないのは専門分野が固まっていることや学校推薦があると言えましょう。
平均本エントリー数
本エントリーはエントリーシートなどを提出して実際に選考を受けることです。
一般的な理系学生の本エントリー数は5社以下となっています。
理系女子は文系就職をする割合も多いため、男子よりエントリー数が多くなっている傾向があります。
文系と比べても学校推薦があって就職が決まる可能性があることなどで本エントリー数の平均も少なくなっていると考えられます。
エントリー数が多い時のデメリットとメリットとは?
エントリー数の平均について解説してきましたが、自分はエントリー数が多すぎるのではないか?といった悩みもあるでしょう。
そしてエントリー数には、エントリー数が多い時のメリットとエントリー数が多い時のデメリットがあります。
そこで今回は、そのエントリー数が多い時のメリットとデメリットについて解説していきます。
エントリー数が多い時のメリット
エントリー数が多い時のメリットとして、視野を広く持ち経験を積めるという点があります。
就活に理解が深まった後に、「絞ってた業界とは別の業界の方が向いていそう」と後悔する就活生は少なくない中で、いろいろな業界の企業説明会に参加したり選考を受けることは視野を広め、そういった後悔をしにくくなることにも繋がります。
そして、あまり知られていないけれど業界内では有名な、業界トップのホワイト企業を知るきっかけにもなります。
エントリー数が多いとESの作成数や面接回数も多くなるので、経験を積むことにも繋がり、
エントリー数が多いことでそれに応じて内定率が上がることもエントリー数が多いことのメリットの一つです。
エントリー数が多い時のデメリット
エントリー数が多い時のデメリットの一つは、やはり一つの企業にかける時間が少なくなることです。
エントリー数を増やすと、多くの企業を調べなければならないので、企業研究にかける時間も多くなります。
企業研究を疎かにすることは志望動機も疎かになることに繋がるので、エントリー数が多いときは企業研究を丁寧にしながら多くの企業にエントリーする必要があります。
そして、スケジュール管理が難しくなることもデメリットとして挙げられます。
企業によって提出期限も異なる上、面接日程も重なることがあるので、無理をしない程度のエントリーが大事です。
エントリー数が少ない時のデメリットメリット
「自分のエントリー数は少なめにしようと思ったんだけど、エントリー数が少なめだとどうなるんだろう」と感じる理系就活生の方もいると思います。
エントリー数が少ない時もまた、エントリー数が少ない時のデメリットとメリットもあります。
そこでエントリー数が少ない時のメリットとデメリットについて下で解説します。
エントリー数が少ない時のメリット
エントリー数が少ない時のメリットは、目標を絞って就活ができることです。
ずっといきたい企業や本命の企業がある場合は、必然的にエントリー数も少ないので短期間で就活を終わらせることができます。
そして、エントリー数が少ないことのメリットとして一社に掛けられる時間が増えることが挙げられます。
一社ごとの企業研究や対策をより深められるため、選考を突破する可能性を高められます。
エントリー数が多いとスケジュール管理も大変になりがちですが、エントリー数を絞ることで、余裕を持ってESを作成したり、OB訪問をすることにも繋がります。
エントリー数が少ない時のデメリット
エントリー数が少ない時のデメリットとして、手持ちの駒が少ないことが挙げられます。
エントリーした企業に全て落ちてしまうリスクもあります。
エントリーした企業に全て落ちた後に違う企業にエントリーをし始めても、最初の選考より難しくなる可能性も高いです。
そして、企業研究を進め、内定をもらった後に「もっといろんな企業を見ておけば良かった」「自分には合わないんじゃないか」と後悔する可能性もあります。
面接の経験回数も少なくなることで面接慣れをする機会も限られてくるデメリットもあります。
エントリー数が少ないことは視野が狭くなることにも繋がり、志望する業界や業種をあらかじめ絞って就活することになるので、後々行きたい企業に出会う可能性もあります。
エントリー数が少ないとこのようなこともあるため、エントリー数が少ないことにはデメリットも伴います。
理想的なエントリー数って?
エントリー数が多い時と少ない時のメリットデメリットについて解説していきましたが、どうしたら、多すぎず少なすぎない理想のエントリー数になるのでしょうか。
そこで次では理想的なエントリー数について紹介していきます。
第一志望群は約5社
第一志望群のエントリー数は目安として5社ほどです。
大手に絞る場合には、想定倍率を考慮する必要があり、大手志向によりますます大手は狭き門になっていることも考慮しなければなりません。
第一志望群では大手に絞ることはリスクが大きいことを予め把握した上でエントリーする企業を決めることと、その他のエントリー数をどうやって増やしていくかが重要になってくるでしょう。
第二志望群は約10-20社
第二志望群の理想のエントリー数は10-20社だと言えます。
第一志望群はもちろん、この第二志望群が就活の鍵になってくるでしょう。
理想的なエントリー数の担保のためには、「第一志望群の企業にいくつかエントリーしつつ、無理のない範囲でエントリー数を増やしていく」ことが基本的な鉄則となってきます。
エントリー後の通過率の目安
エントリー後実際にESを出すのは5割
エントリーしたすべての企業の選考に進む人は意外と少なく、エントリー数のうち約半数しかエントリーシートを提出していないケースが多いです。
エントリー後に興味が薄れたり、日程が合わなかったりと理由はさまざまです。
だからこそ最初から多めにエントリーしておくことで取捨選択ができ、本当に志望する企業に注力しやすくなります。
絞るのは後でできますので、最初は自分の選択肢を広げるためにエントリー数を増やしてみましょう。
面接まで通過するのは3割
ESを出した企業のうち、実際に面接に進めるのは平均して3割前後と言われており、10社にESを出しても3社面接に進めれば順調です。
面接が苦手な人や高倍率の企業ばかりを選ぶと、さらに通過率は下がる傾向にあります。
ある程度エントリーしておくことは自分の選考通過率を知る意味でも大切で、選考の感触を確かめながらエントリー数を調整していきましょう。
後で後悔しない!就活を効率的に進めるコツ
自己分析で就活の軸を決める
効率よく企業を選ぶためには、自己分析をして自分が大切にしたい価値観や働き方を明確にすることが第一歩です。
何を基準に企業を選ぶのかがはっきりすれば、数に振り回されずに済みます。
興味がある業界や自分の強みが活きそうな職種など、自分なりの軸をもとに企業を比較すると納得感のある選択ができるようになります。
インターンや早期選考に参加する
インターンや早期選考に参加すると企業とのマッチ度を事前に確認できるだけでなく、内定への近道になる場合があります。
特に、理系職種ではインターン参加者限定の選考フローが用意されていることも多く、優先的に選考が進むケースもあります。
本選考前に企業と接点を持つことで、志望動機の説得力も増しやすくなる点もインターンに参加するメリットです。
定期的に自己分析と企業研究を見直す
就活は長期戦になりやすいため、最初に決めた就活の軸も時間が経ったことでズレてくる可能性があります。
選考を受ける中で自分の優先順位が変わることはよくあるため、定期的に立ち止まって、自己分析と企業研究を見直す時間を取りましょう。
就活中にエントリーを増やすのを検討する
最初にエントリーした企業だけで内定が出なかった場合、エントリー企業の追加を検討しましょう。
スケジュールが詰まりすぎていないタイミングを見計らって新しい企業を加えれば、就活の選択肢を増やせます。
エントリー先を検討する時に押さえたいポイント
数と質のバランスを考慮する
エントリーは、数と質のバランスを考慮することが重要です。
たくさんエントリーすれば安心というわけではなく、一社ごとの対策が雑になれば本末転倒です。とはいえ数が少なすぎると、万が一のときに選択肢がなくなってしまいます。
最初は広くエントリーし、選考を進めながら質を高めていくスタンスが理想です。
自分のキャパに合わせてバランスを調整し、無理なく進められるエントリー数を意識しましょう。
一つひとつの選考にきちんと取り組む
「数多くエントリーすれば1社は内定を取れる」というやり方では通用しないことも多く、丁寧に準備した志望動機や自己PRが結果を分けます。
特に、興味のある企業に関しては、しっかり時間をかけて一つひとつの選考にきちんと取り組む姿勢が重要です。
数をこなしながらも、一つひとつの選考でベストを尽くすことで結果として第一志望に受かる可能性も高くなります。
スケジュール管理に気をつける
エントリー数が増えてくると、選考の締切や面接日程の調整で混乱しやすくなります。
特に、複数社の選考が同時に進行しているとスケジュールが重なってしまうこともしばしばです。
リマインダーや就活管理アプリを使って管理を徹底し、焦らず対応できる体制を作っておきましょう。
逆求人サイトで就職の選択肢を増やそう
逆求人サイトは、プロフィールやスキルを登録することで企業側からスカウトが届く仕組みです。
自分では思いつかなかった企業や職種に出会えるきっかけにもなり、労力をかけずに選考チャンスが広がる点が魅力です。
特に理系学生は技術スキルや研究内容を評価されやすく、逆求人サイトとの相性が良いです。
就活後半の追加エントリー先を探す手段としても活用できます。
理系就活生におすすめの就活サイトは、理系に特化した逆求人サイト「TECH OFFER」です。
TECH OFFERを活用することで、自分に合った理系企業とのマッチングがスムーズになり、より効果的な就職活動が可能になります。
まとめ
就活では目安となるエントリー数はありますが、自分の通過率や負担に合わせて柔軟に調整することが大切です。
自己分析をもとにエントリーする企業の質を高めつつ、最初は幅広く視野を持っておくことが後悔しない就活のコツです。