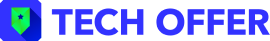こんにちは。理系就活情報局です。
「人と話すことが得意じゃないし、グループディスカッション苦手だな…」
「周りに圧倒されて積極的に意見が言えない…」
「テーマは当日にならないとわからないし、対策の仕様がないよな…」
こんな悩みを抱えていませんか?
理系就活生の中には、グループディスカッションに苦手意識を持っている方も多いと思います。
今回は、グループディスカッションの進め方や問題別の対策について解説します。
グループディスカッションの対策に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください!
企業がグループディスカッションを行う2つの目的
就活生の思考力を見たい
企業がグループディスカッションを行う目的の1つ目は、就活生の思考力を見たいからです。
仕事をしていく上では、課題を見つけ主体的に解決していく力が重要です。
そこで、企業側はグループディスカッションの取り組みを通じて、
・論理的思考力
・課題解決力
・発想力
などの思考力を見ています。
結論から話すことはもちろん、日頃から考えるクセをつけておくと、思考力が鍛えられます。
日頃の練習としておすすめなのは、ニュースを見たときに、「自分だったらどうするか」考えることです。
就活生の対人力を見たい
企業がグループディスカッションを行う目的の2つ目は、就活生の対人力を見たいからです。
仕事をしていくうえでもう1つ重要なのが、周りを巻き込んでチームで課題を解決していくことです。
企業はグループディスカッションを通して、就活生の立ち回りを見ることで、
・協調性
・コミュニケーション力
・リーダーシップ、積極性
などの対人力を判断しています。
話すことが得意なら積極的に意見を出して雰囲気をつくったり、逆に苦手なら意見をまとめる書記を引き受けたりしてもいいでしょう。
自分なら何ができそうか1度考えてみてください。
グループディスカッションの問題の種類
選択型
選択型のグループディスカッションは、いくつかの選択肢の中から答えや優先順位を選ぶために議論をする問題です。
【選択型のテーマ例】
・無人島に行く時に何を持っていくか
・仕事・趣味・家族・お金の優先順位をつけてください
課題解決型
課題解決型のグループディスカッションは、提示された課題の解決策を議論する問題です。
【課題解決型のテーマ例】
・売上を倍にするにはどうすればいいか
・自社サービスの認知度を上げるにはどうすればいいか
ディベート型
ディベート型のグループディスカッションは、対立する意見を互いに主張しながら議論を進めていく問題です。
【ディベート型のテーマ例】
・就職先を選ぶ上で大切なのは、やりがいか給与か
・大学院へ行くべきかどうか
自由討論型
自由討論型のグループディスカッションは、明確な答えのない抽象的なテーマについて、自由に議論を進めていく問題です。
【自由討論型のテーマ例】
・就活生にとって必要な能力とは何か
・10年後の未来では、スマートフォンはどのような進化をとげているか
グループディスカッションの進め方
グループディスカッションの基本的な進め方
グループディスカッションの基本的な進め方は以下の通りです。
1.スケジューリングや役割分担をする
まずは、スケジューリングや役割分担を行いましょう。
時間内に議論をまとめるために「時間配分」を決め、時間を管理する「タイムキーパー」を設定することをおすすめします。
2.置かれている状況や解決すべき課題を確認する
全員が同じ認識を持つことで、議論の方向性を共有できたり、論点がズレたときにわかりやすかったりします。
3.アイデアを出し合う
意見を言うときには、以下の3点を意識しましょう。
・結論ファーストで分かりやすく説明する
・裏付けとなる根拠を具体的に示す
・他の人のアイデアを否定せずにどんどん出していく
4.アイデアをまとめる
一通りアイデアを出したら、結論を出す前に1度整理しましょう。
意見をグループ分けすることで、類似する部分や対立する部分が明確になるので、その後の議論が進めやすくなります。
5.結論を出す
まとめた意見をもとに結論を話し合う時に重要なのは、いかにお互いの意見を尊重しあい結論に達するかです。
その過程が評価ポイントとなります。
間違っても多数決で決めるようなことはしないでください。
上手く結論をまとめるためには、以下の3点を意識しましょう。
・評価基準を設定する(例:「問題解決のスピード」「費用」「効果」など)
・アイデアのいいところをまとめる
・意見の対立点を解消する
6.発表する
発表は論理的に分かりやすくを意識しましょう。
ディスカッションが上手くいっていても、発表が悪いとイメージダウンに繋がってしまいます。
発表を分かりやすくまとめるためには、「PREP法」を用いるのがおすすめです。
以下の順番に当てはめて、誰が聞いてもわかりやすくなるよう心がけながら発表しましょう。
1.Point(結論)
2.Reason(理由)
3.Example(具体例)
4.Point(結論)
選択型
選択型のグループディスカッションには、複数の選択肢があります。
そのため、選択肢を比較検討するための基準の設定が重要です。
何を基準にするのかを明確に決めなければ、何がメリットで、何がデメリットになるのかがわからず、結論が出せないまま議論が終わってしまいます。
必ず評価の基準となる要素を設定し、全員が共通の認識を持つようにしましょう。
グループ内で意見が分かれた場合は、多数決ではなく話し合いで決める必要があります。
それぞれの主張を聞き入れながら議論を進めて、最終的には全員が納得できる答えを導き出すことが重要です。
課題解決型
課題解決型のグループディスカッションでは、まず問題の本質を明確にしてから、目標を設定します。
現状を分析しながら解決に向けて検討を進めていきましょう。
テーマの中には、「売上を2倍増やす」といった企業の課題だけでなく、時事問題が取り上げられる場合もあります。
ディベート型
ディベート型のグループディスカッションでは、2つの意見が衝突し合うため、時に熱烈な議論が生まれることがあります。
自分の意見を強制するのではなく、お互いの主張を注意深く聞きましょう。
意見をまとめながら議論を進めて、最終的にどちらを選ぶかを判断することが重要です。
自由討論型
自由討論型のグループディスカッションには明確な枠組みがないため、議論が自由に展開していきます。
ただし、自由さゆえに話題が逸れやすくなるため、テーマを見失わずに議論を進めていくことを念頭に置きましょう。
グループディスカッションの役割別の立ち回り方
司会(リーダー)
司会(リーダー)の役割は、メンバーから意見を引き出して、議論を活発に進めていくことです。
意見を引き出すためには、以下の4点を意識しましょう。
・発言できていないメンバーに話を振る
・相手の目を見て頷きながら聞く
・相手の話を遮らない・否定しない
・議論の足りない部分(欠点)を指摘し、発言を促す
注意しなければならないのは、司会だからといって自分の意見を無理やり通さないということです。
司会(リーダー)は、あくまでも意見を引き出し、議論を円滑に進めていくことに注力しましょう。
序盤に意見が出づらい時は、最初に意見を口にして、メンバーが安心して発言ができる雰囲気を作れると高評価が得られます。
その後、「皆さんはどう思いますか?」と周りに広げる流れを作ると、スムーズにアイデア出しが進みます。
タイムキーパー
時間内に結論が出せるように働きかけることが、タイムキーパーの役割です。
グループディスカッションにおいて、タイムキーパーは重要なカギを握る存在です。
議論を進める司会やメモをとる書記、話し合いに熱中する他のメンバーは、自分の役割に集中すると、時間を忘れがちになってしまいます。
タイムキーパーは、ただ時間を管理するだけではなく、結論まで導くことを意識しましょう。
たとえば、「盛り上がっているところ申し訳ないんだけど、時間が迫っているのでアイデアを整理して、結論をまとめましょう」と口を挟み、議論を進めていきましょう。
書記
書記は、意見をまとめるときに力を発揮する役割です。
ただ意見をメモするだけでなく、以下の2点を意識するとグループディスカッションにさらに貢献できるでしょう。
・同種の意見をグループ化してまとめる
・意見の対立関係を明確にする
ただし、メモに夢中になって議論に参加しなくなってしまうと本末転倒です。
書記をすることで、独自の気づきが得られるはずなので、気づいたことは積極的に発言していきましょう。
監視役
監視役は、グループディスカッションの論点がズレてしまわないよう、進行を見張る役割です。
司会のように進行はしませんが、全員の発言を聞きながら議論の流れをコントロールすることを心がけましょう。
監視役はタイムキーパーと似ているため、兼務することが多い役割です。
アイデアマン
アイデアマンは、議論が活発になるように、さまざまな観点からアイデアを出す役割です。
アイデアマンの役割がない場合は、役割のない人がアイデアマン的役割を担い、意識して発言を行うと良いでしょう。
アイデアマンは、1つの意見に固執せず、複数のアイデアを出すことで議論を活気づけます。「この意見は正しいだろうか」と考え込みすぎず、積極的に発言しましょう。
発表者
発表者は、グループディスカッションで話し合った議論を発表する役割です。
発表をする時は、書記がまとめた内容をただ読み上げただけにならないよう、注意しましょう。
発表者には、抑揚をつけて話したり、順序立ててわかりやすく説明したりするなど、プレゼンテーション能力が求められます。
役割を持たない場合
役割を持たない場合は、その分積極的に議論に参加できるので、そこで評価を得られるように立ち回りましょう。
相槌を打って話しやすい空気をつくったり、司会やタイムキーパーなど他の役割のフォローをしたりするほか、積極的に意見を出して議論を活発化させることも、立派な貢献です。
ここで気をつけなければならないのは、クラッシャーと呼ばれるグループディスカッションを台無しにしてしまう学生にならないことです。
自分が以下のような行動を自分がとっていないか、振り返ってみましょう。
・人の意見を聞かずに自分の意見を押し通す
・テーマ自体を否定する
・議論を妨げ雰囲気を悪くする
グループの中にクラッシャーがいた場合は放置したりせず、論点を整理したり他のメンバーに意見を求めたりすることで対処しましょう。
理系就活のグループディスカッションのコツ
自分ができる役割で貢献する
グループディスカッションは、司会や中心になって意見を言う人だけが評価されるわけではありません。
チームの中でいかに価値を発揮するかが評価ポイントになります。
そのため、ディスカッションに苦手意識のある人でも十分突破が可能です。
気配りが得意なら決まった役職ではなく周りのフォローに回る、まとめるのが得意なら書記というように、自分の強みを活かして議論に貢献していきましょう。
結論から話す
意見は結論から話すようにすると、周りも理解しやすくなり、高評価がついてきます。
併せて、根拠を具体的に説明できると説得力が増すでしょう。
PREP法に当てはめると、簡単に説得力の高い意見になるのでおすすめです。
PREP法はグループディスカッションだけでなく、ESや面接など使える場面が多いので覚えておきましょう。
グループ全体で議論を良い方向に導く
グループディスカッションでは、チーム全体の働きが見られています。
そのため、自分をアピールするためにチームメンバーを貶めるような言動は評価に繋がりません。
「その考え方は違うだろう」と思っても意見の1つとして受け入れて、議論を円滑に進めていきましょう。
チームメンバーはライバルではなく仲間であるという意識で協力しあい、一緒に議論を作り上げていく存在であることを忘れないようにしてください。
まとめ
今回は、グループディスカッションについて解説しました。
グループディスカッションの対策と併せて、「TECH OFFER」に登録しておきましょう。
「TECH OFFER」は、理系に特化した逆求人型サイトです。
あなたの強みや専門性を凝縮したプロフィールをもとに企業とマッチングを行い、あなたという人材に魅力を感じる企業からオファーが届きます。
自分の強みや魅力を打ち出した就活で、内定を獲得しましょう!
▼あなたに合った企業の情報が届く▼
TECH OFFERで優良オファーを受け取る