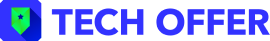「最終面接は入社意思の確認だけで落ちることはない」と考える方も多いでしょう。
しかし残念なことに、最終面接まで通過しても内定をもらえないケースも存在します。
そんな中、最終面接の面接官がどのような反応をすれば合格・不合格なのか気になる方も多いのではないでしょうか?
今回は最終面接で落ちるフラグや合格するフラグについて解説します。
これから最終面接を迎える理系就活生は、ぜひ参考にしてください!
▼あなたに合った企業の情報が届く▼
TECH OFFERで優良オファーを受け取る
最終面接とは?
企業と理系就活生の最後の摺り合わせ
最終面接は、一次・二次面接の評価をふまえつつ、経営者や役員目線で「今後自社に貢献してくれる人材か」を見極める場です。
最終面接でほかの理系就活生よりも抜きん出るためには、経営者や役員が内定を出したいと思う決め手を作らねばなりません。
この記事では、最終面接で落ちるフラグの礼や、「我が社に欲しい!」と思ってもらえる人の特徴、最終面接で落ちたと感じた時の対処法を解説していきます。
「内定まであと一歩」のチャンスを逃さないよう、フラグを見分けながら対策していきましょう。
最終面接で落ちる確率
最終面接で落ちる確率は、企業によって異なります。
例えば、最終面接を役員や社員が担当し、入社意思を確認するだけというケースではほとんどの応募者が合格することもあります。
一方で、最終面接での評価が採用可否に大きく影響を与える場合、最終面接まで通過しても不合格者が数多く出る場合もあるでしょう。
入社後すぐに退職されてしまうと、採用コストが無駄になってしまうため、企業は採用を慎重に検討するケースが多いです。
そのため、最終面接まで進めたとしても不採用になる確率があることを念頭においておきましょう。
最終面接に落ちるフラグの例
面接官の反応や雰囲気が悪い
応募者の発言に対する面接官の反応が薄い場合、最終面接で落ちた可能性があります。
基本的に好印象で共感できる回答を得られた場合、うなずきなどのリアクションを行うのが自然です。
反応が薄かったり、発言への否定や反論が多い場合は、面接官が思った回答を得られていないことや会社とのミスマッチを示しています。
企業側が求める回答ができていない可能性があり、面接の評価が低くなる可能性があります。
入社後の話が一切ない
最終面接で入社後の話が一切ない場合も、最終面接で落ちる可能性が高いでしょう。
不採用が決定した応募者に対して、面接官が入社後の話をすることはありません。
反対に、採用したい理系就活生には、内定後のスケジュールの話をすることがあります。
そのため、入社後の業務内容や配属希望部署など、今後の話が一切ない場合は採用の可能性が低いです。
面接時間が予定より短い
面接時間が予定よりも短い場合、最終面接が不合格になる確率が上がります。
本当に採用したい人材であれば、応募者への質問も多くなる上、自社のアピールも増えるため、面接時間が長くなる傾向にあります。
そのため、面接が短時間で終わった場合、早々に不合格と判断された可能性があります。
ただし、最終面接で入社意思の確認だけを行う場合は、面接が短時間で終わったとしても合格するケースもあります。
メールで内定連絡をすると言われる
面接結果をメールで送ると言われた場合も、最終面接は不合格の確率があります。
内定の場合は、承諾後の必要書類の案内などを行うため、電話で直接伝える企業もあります。
一方で、不合格者の場合はその後の確認事項もないため、メールで連絡を済ませるケースが多いです。
ただし、応募者が多い場合などはメールで内定通知し、追って電話連絡する場合もあります。
最終面接に合格する人の特徴
結論から回答する
最終面接に合格する人の特徴1つ目は、結論から回答することです。
どんなに入念に準備をしたとしても、面接の場で話の内容が響かなくては良い結果に結びつくことはありません。
企業の経営層に「採用したい」と思わせるためには、まず最初に結論を述べ、何を伝えたいのかを明確にしましょう。
また、事前に想定される質問の答えをある程度準備しておけば、落ち着いて回答できます。
会話のキャッチボールが成立する
最終面接に合格する人の特徴2つ目は、会話のキャッチボールが成立することです。
面接は、ただ質問されて答えるだけの場ではありません。
最終面接になかなか受からない人の中には、自分がアピールすることでいっぱいになってしまって、コミュニケーションが取れていないケースがあります。
最終面接では緊張してしまいがちですが、できるだけ落ち着いて、面接官の話を最後まで聞いてから質問に答え、聞き取りやすいように配慮しながら受け答えをしましょう。
ひたすら壁に向かってボールを投げるのではなく、会話のキャッチボールをすることを意識して、スムーズなコミュニケーションを取りましょう。
志望理由に一貫性があり社風と合う
最終面接に合格する人の特徴3つ目は、志望理由に一貫性があり社風と合うことです。
面接を重ねていくうちに、「毎回同じ志望理由を答えても大丈夫?」と心配になる方もいると思います。不安になるかもしれませんが、発言には一貫性を持たせましょう。
面接官は、これまでの面接の評価を共有しています。
これまでの選考で評価されていた志望理由と違う発言をしてしまえば、最終面接の場で「思っていたよりも志望度が低いのかもしれない」と判断されかねません。
また、社風とのマッチ度も重要です。
最終面接の前には企業研究を振り返って、自分をその企業に合う人材として打ち出しましょう。
最終面接に落ちる人の特徴
発言に一貫性がない
最終面接に落ちる人の特徴1つ目は、発言に一貫性がないことです。
自分が最終面接の面接官だと想定してみてください。
これまでの面接での評価を見て、会うのを楽しみにしていた理系就活生と話していて、「これまでの面接と発言が違うな」と思ったら、どう思うでしょうか?
最終面接は、内定を出すか出さないかを決める、最後の摺り合わせです。
発言に一貫性がなければ、「この理系就活生はうちで何がやりたいのだろう? 」とマイナスな印象を持たれてしまいます。
失礼な態度を取っている
最終面接に落ちる人の特徴2つ目は、失礼な態度を取っていることです。
面接では、発言内容だけでなく、マナーや身だしなみも評価の対象になります。
せっかく最終面接まで進んだのに落とされてしまわないよう、今一度自分の言動が良い印象を与えるものなのか、確認してみましょう。
入退室のマナーや丁寧な言葉遣い、服装の乱れや清潔感は、ビジネスでは最低限のマナーです。一度、キャリアセンターや友達に客観的にチェックしてもらうのもおすすめです。
企業研究や逆質問の準備が不十分
最終面接に落ちる人の特徴3つ目は、企業研究や逆質問の準備が不十分であることです。
二次面接までは何とか突破できたとしても、最終面接では事前の準備不足が合否を大きく左右します。
きちんと企業研究ができていなければ、経営層の興味を引く深い発言はできません。企業ホームページを一通り眺めただけで企業研究をしたつもりでいれば、痛い目に遭うでしょう。
また、逆質問は、面接の印象を底上げする最後のチャンスです。
面接に好印象を与える質問を理解して、「特にありません」で終わらせることがないよう、下準備をしておきましょう。
最終面接で落ちたと感じた時の対処法
失敗を振り返る
最終面接で落ちたと感じた時の対処法1つ目は、失敗を振り返ることです。
試験が帰ってきた後、振り返りをするように面接でも失敗から学ぶことが大切です。
最終面接をなかなか突破できない人は、十分に振り返りをしていない可能性があります。
だめだった時に気持ちを切り替えることも必要ですが、まずは何がいけなかったのかを振り返り、次に活かせるポイントを見つけてみましょう。
面接練習を重ねる
最終面接で落ちたと感じた時の対処法2つ目は、面接練習を重ねることです。
最終面接を突破できない人は、自分のどういう点がネックになっているのか自覚のある人も多いと思います。
緊張して上手く話せない、受け答えに自信がない、逆質問ができない……。
そうした不安は、すべて練習を重ねることで軽くなります。
大学のキャリアセンターを活用して、大丈夫だと思えるまで面接練習をしてみましょう。
逆求人型サイトを利用する
最終面接で落ちたと感じた時の対処法3つ目は、逆求人型サイトを利用することです。
就活のアクションは、必ずしも理系就活生から起こすものではありません。
ここ数年で浸透した逆求人型サイトは、企業の方からアプローチをする就活方法です。
理系就活生には、理系に特化した「TECH OFFER」がおすすめです。
どんなに入念に対策をしても内定をもらえない場合、企業とのミスマッチが原因かもしれません。
独自のシステムによって、プロフィールをもとに企業とマッチングできる「TECH OFFER」なら、あなたを評価する企業と出会えます。
▼あなたに合った企業の情報が届く▼
TECH OFFERで優良オファーを受け取る
まとめ
最終面接まで通過しても、不合格になる可能性はあります。
内定を獲得するためには、事前準備を徹底して望むことが大切です。
最終面接に落ちるフラグが見られた場合も、面接内容によっては合格できる可能性もあるため、一喜一憂せず、最後までしっかりと受け答えしましょう。
今回の内容を参考に、志望企業の最終面接を突破し、内定を勝ち取ってください!