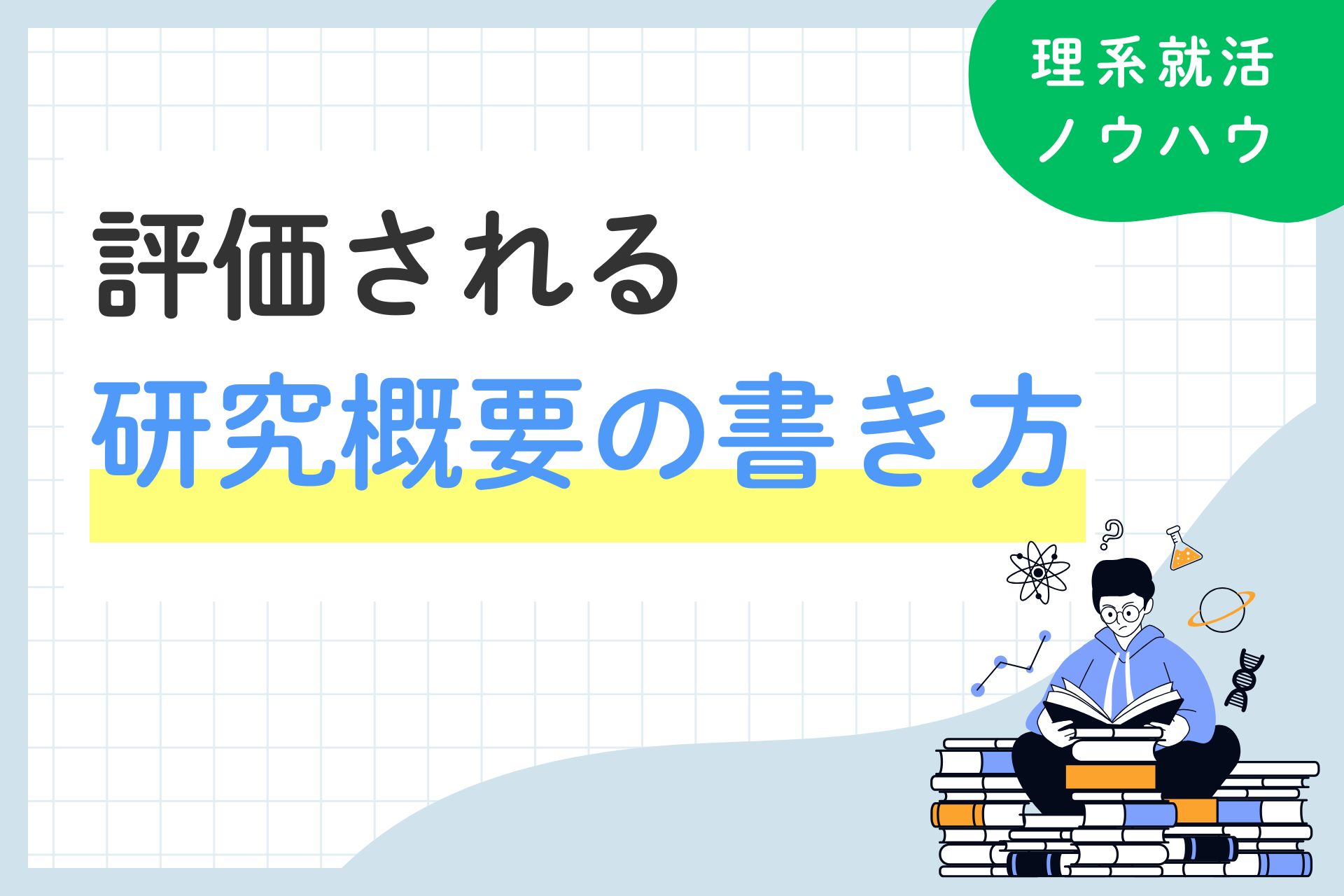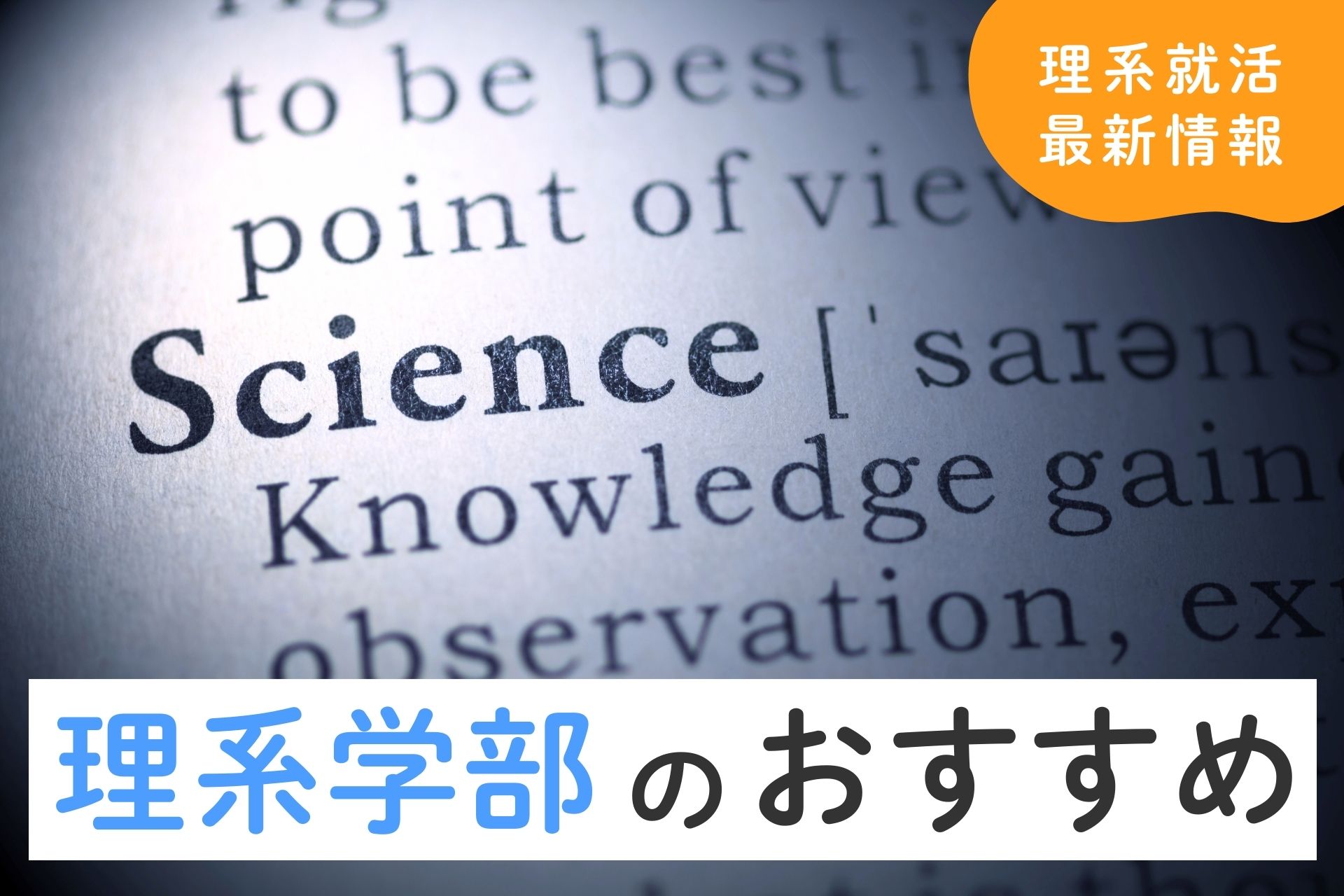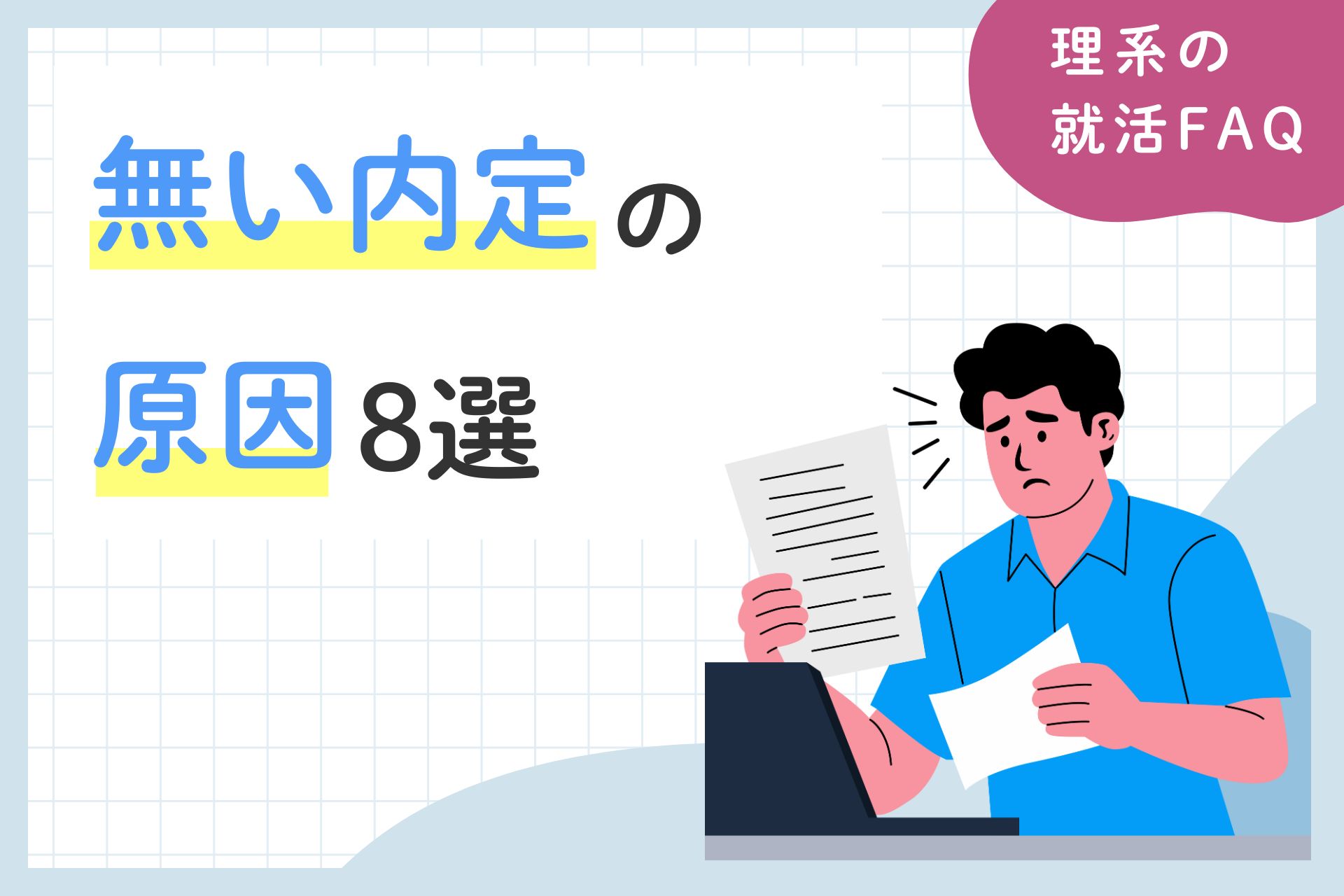こんにちは。理系就活情報局です。
理系の就職は安定しているという印象がある一方で、実際には企業ごとの競争率や求められるスキルに大きな差があります。
そこで、今回は「就職偏差値」を用いて理系就活の実情を紹介し、効率的な就活のヒントを解説します。
就活偏差値とは?
企業への入社難易度を示す目安
就活偏差値とは、企業への入社の難しさを数値化した指標です。
就活偏差値とは企業ごとの「入社のしやすさ」を数値化したもので、就活界の“人気+難関度”ランキングです。
「エントリー数の多さ」「選考フローの厳しさ」「採用人数の少なさ」「学生からの評価」などをもとに作られており、偏差値が高いほど「狭き門」となります。
とはいえ、就活偏差値は公的機関のデータではなく就活生の口コミや民間調査によるものです。
目安としての活用は有効ですが、すべてを鵜呑みにするのではなく自分に合った企業を探す視点を忘れないことが大切です。
就職偏差値が高くても自分に合わない職場もあれば、ランク外でも居心地の良い企業はたくさんあります。
【2025年最新版】理系企業の就職偏差値ランキング
日本企業格付センター「【2025年】ホワイト企業・就職偏差値ランキング」から、化学業界の就職偏差値トップ10をまとめました。
| ランク | 就職偏差値 | 企業 |
| SSランク | 70 | ドコモ(中央)・ 新日鐵住金・ INPEX ・TV局・ 武田薬品 |
| Sランク | 69 | MRI・NTT持株・豊田中研・鉄研・電中研・産総研 |
| 68 | 上位金融(数理専門)・ NHK(放送技術) | |
| 67 | JXエネルギー・JR東海・Microsoft | |
| A級ランク | 66 | ドコモ(中央)・ 新日鐵住金・ INPEX ・TV局・ 武田薬品 |
| 65 | JR東・サントリー・味の素・アサヒ・キリン・東京ガス・昭和シェル・旭硝子・ ANA(技術)・ 日揮・ 三菱重工・ 第一三共・キーエンス・トヨタ | |
| 64 | JR西・日清製粉・三菱化学・東燃・信越化学・日産・JFE・アステラス・エーザイ・任天堂 | |
| 63 | 】JT・電源開発・日清食品・大阪ガス・中電・出光・住友鉱山・住友電工・JX金属・コマツ・日立(非SE) ・KDDI・東レ・住友化学・千代田化工・キャノン・ホンダ・ JAL(技術) ・川崎重工・富士フィルム | |
| 62 | ニコン・資生堂・ユニチャーム・東邦ガス・関電・豊田自動織機・ファナック・花王・SCE・HP・日本IBM(SE)・ NTTデータ・ソニー・ 三井化学・旭化成 ・ゼロックス・IHI・ 明治 ・三菱マテリアル・ 三菱電機・デンソー | |
| 61 | 昭和電工・板硝子・東洋エンジ・ NTTコミュニケーション・大手ゼネコン ・帝人・JSR・東京エレクトロン・ヤフー・サッポロ・王子製紙・古河電工・三井金属・神戸製鋼・NRI・日東電工 | |
| 60 | NTT東西・HOYA・ダイキン・日本製紙・コニカミノルタ・富士通(非SE)・住友重機械・カシオ・DIC・大日本スクリーン・宇部興産・積水化学・マツダ・森永製菓・ソニーモバイル・クラレ・大陽日酸・リコー・パナソニック |
(引用:日本企業格付センター「【2025年】ホワイト企業・就職偏差値ランキング」)
SSランク
SSランクの企業は、ドコモ(中央)・ 新日鐵住金・ INPEX ・TV局・ 武田薬品など、理系学生にとっての憧れともいえる超難関企業です。
選考では専門知識だけでなく論理的思考やプレゼン力も試され、インターンからの選考ルートも多いため、早期対策が必須です。
Sランク
Sランクの企業は、MRI・NTT持株・豊田中研・鉄研・電中研・産総研・Microsoftなどがあります。
安定した経営基盤と最先端技術への取り組みが魅力で、志望者も多く競争は激しめです。技術職の中でも特に高度なスキルが求められるため、専門分野のアピールがカギになります。
ESや面接でも自己分析と企業研究の深さが問われます。
Aランク
Aランクの企業には、サントリー・味の素・アサヒ・キリン・東京ガスなどの実力派企業が入っています。
知名度や働きやすさで人気があり、理系の学生にとってはバランスの取れた選択肢で、エントリー数は多くても準備次第で十分に内定が狙えます。
インターン参加や研究テーマとの関連性をアピールすると、通過率が上がる傾向があります。
理系メーカーの就職偏差値ランキング
就活市場「メーカー業界の就職偏差値ランキング」から、トップ10をまとめました。
| ランク | 就職偏差値 | 企業 |
| SSランク | 65 | トヨタ |
| Sランク | 64 | サントリー / gs / ユアサ |
| 63 | 新日鐵 / 味の素 / キリン | |
| 62 | 三菱重工業 / アサヒビール / 任天堂 旭硝子 | |
| 61 | 日産 / JFE / ホンダ / 信越化学 | |
| 60 | デンソー / コマツ / JT / 日清製粉G本社 / 花王 / キーエンス / 富士フイルム / 住友化学 | |
| Aランク | 59 | 日東電工 / 旭化成 / 日立製作所 / 東レ / 住友電工市外国語大学 |
| 58 | 住友鉱山 / JX金属 / 三菱ケミカル / 明治 / サッポロビール | |
| 57 | 三井化学 / 三菱マテ / 川崎重工業 / 三菱電機 / 豊田自動織機 / ソニー | |
| 56 | 住友重機 / 積水化学 / カルビー / キッコーマン / 三菱ガス化学 / クラレ / 武田薬品 / クボタ / 古河電工 / 日清食品 / パナソニック / 島津製作所 / キヤノン / 富士ゼロックス / 村田製作所 | |
| 55 | 王子製紙 / オムロン / TDK / リコー / イスゞ / 日立化成 / JSR / 宇部興産 / 大陽日酸 / 日本触媒 / ブリヂストン / IHI / 帝人 / 東ソー / アイシン精機 / 昭和電工 |
(引用:就活市場「メーカー業界の就職偏差値ランキング」)
SSランク
SSランクに入るのはトヨタ自動車で技術力と収益性で突出した企業であり、倍率が非常に高く論理的な思考と先端技術への理解が求められます。
業界研究と実際の製品に対する知識を持ったうえでの志望動機が重要で、早めの情報収集とOB訪問が選考突破のポイントです。
Sランク
Sランクにはサントリーや味の素、キーエンスなどがあります。
Sランクのメーカーは採用規模は広めですが、成績や研究内容がしっかり見られるため気は抜けません。
メーカーでは技術だけでなくチームワークや課題解決力も評価対象になるため、大学生活での実績を論理的に伝える準備をしておきましょう。
Aランク
Aランクには旭化成やソニー、パナソニックなどの業績の安定した有力企業が入ります。
選考では特定分野に対する専門性や、長期的なキャリアの意欲が問われるケースが多いです。
地道に取り組んできた研究やアルバイト経験なども、表現次第では高評価につなげられます。
就職偏差値を見る時に気をつけたいポイント
就職偏差値が高い=勝ち組ではない
「就職偏差値が高い=勝ち組」ではありません。
就職偏差値が高い企業に内定しても、すべての人にとって理想の職場とは限らないからです。
偏差値にとらわれすぎると、自分に合った企業を見失う場合があります。偏差値で入社先を決めるのではなく企業との相性や働き方、自分がやりたいことが実現できるかどうかを判断基準にしましょう。
公的な情報ではないため参考程度に考える
就職偏差値は就活サイトや個人がまとめたもので、公的なデータではありません。
更新頻度や評価基準もバラバラなため、就職偏差値は参考データの1つとして考えましょう。
実際の企業の社風や成長性は、説明会やOB訪問で得られるリアルな情報で判断することをおすすめします。
情報をわかりやすくまとめたランキングは便利ですが、ソースの正確性抜きに信用してしまうと入社後に「こんなはずではなかった」と後悔しかねません。
就職偏差値はあくまで目安として認識し、ほかの情報も深掘りしながら企業研究をしてください。
就活偏差値の高い企業だけ志望するのは避ける
就職偏差値が高い企業ばかり狙ってしまうと、倍率と難易度が高い選考に落ち続けて自信を失うこともあります。
「就職偏差値が高いから」「大手だから」と深く考えずにエントリーしていると、気づけば選考に進めないまま取り残されてしまうかもしれません。
就活偏差値だけで志望先を判断せず、自分の専門性や希望条件に合った企業に背伸びせず等身大で挑むことも大切です。
ランキング外にも優良企業は多い
ランキングに載っていない企業や就活偏差値が低い企業の中にも、働きやすくやりがいのある職場は多く存在します。
知名度だけに惑わされず、説明会やインターンを通じて自分の目で確かめていくことが理想のキャリアへの近道になります。
理系が就職に強いとされる3つの理由
SNSの情報や周囲の就活状況から、何となく理系は就職に強いという印象を抱いている方もいるでしょう。
本章では理系が就職に強いとされる理由を3つ紹介します。
就職率が高い
文部科学省の「令和5年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査」によれば、文系の就職内定率が97.9%であるのに対し、理系の就職内定率は98.8%です。
数値としては僅差ですが、理系の就職率が安定して高いことがわかります。
専門性が就職に直結しやすい
理系の就職率の高さには、理系学生の最大の特徴である専門的な知識や技術が就職に直結しやすいことが影響しています。
専門的な知識や技術を学んだ理系学生の場合、企業の募集が専門性に限定されている場合があります。
例えば、
▼技術部:機械系、電気系、電子系、通信系
▼システム管理部:IT系、通信系、情報系
などのように、募集する部門において学部が指定されています。
このように、理系就活生は募集の段階から専門性別に振り分けられることも珍しくなく、自分の学んだことを発揮しやすく、将来へのルートを思い浮かべやすいという特長があります。
理系の素養が幅広い業界で活かせる
理系の就職率の高さには、理系の素養が専門分野を問わず幅広く活かせることも影響しています。
たとえば、理系就活生は数字に強い傾向にあります。
単に数学ができるだけでなく、数字に基づいたデータを分析するスキルを身につけている理系就活生は、理系の素養を幅広いビジネスで活かせるでしょう。
企業では、日々の売上やKPIと呼ばれる組織・個人の目標を達成するための業績評価指数など、毎日数字にもとづいてさまざまな仕事を進めます。
また、理系就活生には、普段行っている勉強や研究で培った論理的な思考や逆算思考という武器があります。
論理的な思考は、ビジネスにおいて信頼性のおける発言や、行動のもととなります。
逆算思考は、売上やKPIを扱う上で重要なスキルであり、仕事の効率性や生産性に良い影響を与えることができます。
ビジネスで活かせる思考を学生の時から備えている理系学生は、企業にとって魅力的な人材です。
就職先を検討する時には、専門性を活かせる道とは別に、理系としての素養を活かせる道があることを念頭においてみましょう。
理系学生の就活の特徴
理系学生の就活の特徴として、以下の2点が挙げられます。
・自由応募・推薦応募の2種類が利用できる
・卒業年度の夏場までには内定を決める学生が多い
文系学生と大きく異なる点もあるため、理系就活の特徴を把握してスムーズに進めましょう。
自由応募・推薦応募の2種類が利用できる
理系学生の就活では一般的な自由応募に加え、推薦応募の選択肢があります。
推薦応募とは、大学・教授から企業に推薦状が出されて選考の機会が与えられる制度です。
すぐれた研究・学業成績を持つ学生が対象となり、自由応募と比較して短い工程で終わる点が特徴です。大学・教授からの推薦をもって選考を受けるため、内定率は自由応募と比べて高い傾向にあります。推薦応募を利用できる点は、理系就活の大きなメリットです。
卒業年度の夏場までには内定を決める学生が多い
理系学生の場合、卒業年度の夏ごろまでに内定を決める学生が多いです。
卒業研究がピークを迎える前の5月〜6月にかけて就活を本格化させることが、理由として考えられます。
理系学生は卒業研究が単位の取得条件となっているケースが多く、研究に比重を置いてしまうと就活に費やせる時間が制限されがちです。
早期の内定を得ることで、研究に専念できるメリットがあります。
難易度が高い企業に受かりたい!理系就活の堅実な進め方
理系学生は就活に強いですが、適切に取り組まなければ、強さが生かせません。
本章では理系就活の基本的な進め方を4つのSTEPに分けて解説します。
STEP1:自己分析・業界研究などの就活準備
就活を進めるにあたって、まず必要なのが自己分析です。
改めて自身を振り返り、以下のポイントを確認するようにしましょう。
・どのような仕事に就きたいのか
・どのような場合にはモチベーションが高まるのか
・どのような働き方がしたのか
・どのようなキャリアを歩みたいのか
就活において、自己分析から生み出された"自分像"は軸となる存在となります。
企業選びや志望動機は自己分析を軸にするため、自己分析は丁寧におこなうとよいでしょう。
自己分析と並行して、業界研究も必要な準備作業です。
以下のポイントを中心に業界研究を進めるとよいでしょう。
・どのような仕事をしている会社が集まっている業界か
・業界の成長率はどれくらいか
・業界が縮小傾向なのか、拡大傾向なのか
・業界を代表する企業はどこか
STEP2:インターンシップへ参加
自己分析や業界研究を通して目星の業界や企業を見つけたら、インターンシップに参加しましょう。
インターンシップは企業や業界への理解が深まるため、後の就活に大いに役立ちます。
特に志望動機を作る際には、インターンシップで企業に携わった経験は志望動機の深掘りにつながります。
STEP3:企業研究
業界研究やインターンシップを通じて進むべき業界・企業が定まったのであれば、選考に向けた企業研究を始めましょう。
企業研究の主な目的は志望動機づくりです。
企業研究は主に以下の内容をチェックして、志望動機につながる材料を探します。
・企業の基本情報(本社地や代表取締役社長、創業年など)
・事業内容
・企業の動向(過去3年を含めた売上高や利益、ビジネスニュースに掲載された内容など)
・業界内の企業との比較
STEP4:企業の選考へエントリー
企業への選考開始時期がきましたら、選考へのエントリーを開始しましょう。
複数の企業へエントリーをする場合には、スケジュール管理が重要になります。
ブッキングをしないことはもちろん、選考対策の時間を取ることも忘れないようにしましょう。
また企業の選考がスタートすると、実際に企業で働く方と会う機会もあります。
企業で働く方々の印象や話を、事前の企業研究とすり合わせて、より深い志望動機につなげると、さらに有利に選考を進められるでしょう。
理系就活における3つの選択肢とスケジュール
理系学生は専門性と素養の高さから、専門分野はもちろん、専門外や文系企業へ就職する選択肢もあります。
本章では就活において、理系学生が取り得る3つの選択肢を解説します。
また各々の選択肢を選ぶ際に参考となる就活スケジュールも併せて解説するので、ぜひ参考にしてください。
専門性を活かす道
理系就活の選択肢1つ目は、専門性を活かす道です。
理系就活生の多くは、自分の研究や専門性を就職後も活かしたいと思います。
就職活動をスタートする時は、大学で勉強している内容が実際の業務にどのように活かせるのかを知るところから始めましょう。
「自分の専門が活かせる道は明確だ」と思っていたとしても、理系の業界は密接です。自分の専門性と領域が重なり合う業界で就職することもできるでしょう。
専門性を生かした就職をする場合、就活のスタートはインターンシップへの参加も考慮して、夏前からスタートしましょう。
インターンシップを通じて、業界や企業への理解を深め、本格的なエントリーに備えます。
また専門性を生かす場合、専門性を生かして、学校推薦を受けられるケースもあります。
学校推薦は卒業前年度の12月におこなわれるので、推薦を考えるのであれば準備を進めましょう。
専門分野外の道
理系就活の選択肢2つ目は、専門分野外の道です。
理系就活生には、自分が学んできた専門分野以外の業種に就く道もあります。
研究をしていたことで身についたデータ解析力をもとに、別分野で活躍する理系就活生も少なくありません。
理系就活生が持っている素養を活かせる道は、思っているよりも広く存在しています。
専門性が細分化している理系の場合、専門分野によっては、自分の研究が直結する業界や職種が少なく、募集自体が限られている場合があります。
その場合、自分の専門分野にこだわりすぎてしまうと、就活の選択肢はかなり狭くなってしまうでしょう。そうした危険も踏まえた上で、一度自分の専門分野以外での就職も検討してみることをおすすめします。
専門分野外に進むため、より一層業界や職種への理解を深める必要があります。
就活のスタートは夏のインターンシップとするため、自己分析や専門外に進む理由を整理するために、卒業前年度の4月からスタートしましょう。
より理解を深めるために、冬季のインターンシップに参加する方法もあります。
文系企業の道
理系就活の選択肢の3つ目は、文系企業への道です。
専門分野外の道の中には、文系の就職先もあります。
銀行や保険会社などの金融関係や、コンサルティングは、理系が活躍できる業界です。
もし文系就職を目指す場合は、比較される対象に文系学生が加わることを念頭に置きましょう。
理系のみの募集よりも間口が狭くなる可能性が高いため、選考対策をしっかり行い、なぜ志望するのかを明確にしておく必要があります。
専門分野外に進むという点では、文系企業に進むケースと同じであるため、就活のスケジュールは専門分野外に進むケースと同じと考えてよいでしょう。
夏のインターンシップへの参加を一つの目途として捉えて、就活を進めることをおすすめします。
理系就活生の専門分野による就職先の違い
理系の専門分野によって、就職先が大きく異なります。自身の専攻した学問領域と関連の深い企業・業界を選ぶ傾向があるためです。理系就活生の専門分野による就職先の違いを、以下の2つの観点から解説します。
・専攻別の主な就職先
・学部卒・大学院卒の違い
専攻別の主な就職先
理系学部の中でも、専攻によって主な就職先が分かれます。専攻ごとの主な就職先をまとめると以下の通りです。
| 専攻 | 主な就職先の事業分野 |
| 電気・電子・機械系 | 自動車、電機メーカー、工作・建設機械、重機・造船、産業電子機器、電子部品、産業用ロボット、宇宙、原動機・タービン・汎用機 |
| 化学・生物・農学・数学・物理・情報系 | 素材(繊維・石油・ゴムなど)、化学、電気・ガス、油脂・塗料、食品・飲料、種苗・飼料、バイオ関連、農業・林業・水産業 |
| 材料・エネルギー系 | 素材(鉄鋼・非鉄金属)、家庭用品、電気・ガス |
| 建築・土木系 | 建築会社、建材メーカー、住宅メーカー、設計事務所 |
上記のように、理系就活生は自身の学んだ専門性を活かせる企業・職種を意識して就職先を選ぶ傾向があります。
学部卒・大学院卒の違い
理系就活生の就職先は、学部卒・大学院卒でも異なる面があります。
学部卒の場合は、研究開発職はもちろん、技術職や生産・製造現場を含めた幅広い分野を選択肢として検討する学生が多いです。
一方、大学院で修士号・博士号を取得した人は高度な専門知識・スキルを持つ研究者・開発者としての評価が高まります。
この場合、大手企業の研究所・製薬会社の開発部門で活躍するケースが多いです。上記以外にも、大学・公的研究機関の研究職を志す人もいます。
専門分野以外で理系が活躍できる業種・職種
理系出身者が専門分野外で活躍できる業種や職種は意外に多岐にわたります。
理系の学生が身につけた論理的思考力・分析力・問題解決能力は、多くの職場で求められる資質だからです。具体的な専門分野外で活躍できる業種・業界の例として、以下が挙げられます。
金融業界
一見すると文系のイメージが強い金融業界は、理系人材のニーズが増しています。
特に、データサイエンスやリスク管理、金融工学の分野では理系出身者が中心となって活躍しています。
メガバンクや証券会社、保険会社では、AIや統計を活用した業務が増えており、理系の強みを発揮しやすい土壌があります。
理系だからといって金融知識が必須というわけではなく、入社後の研修でキャッチアップできる仕組みも整っています。
研究で培った仮説検証力や論理的な思考がそのまま武器になる業界です。
関連記事:https://techoffer.jp/rikeishukatsu/kinyugyo-kai/
コンサルティング業界
コンサルティング業界は、理系の「問題解決力」と「論理的な構築力」が重宝される分野です。
文系・理系問わず採用される業界ですが、特にIT系コンサルや戦略系コンサルでは、システム構築や技術理解の観点から理系人材の活躍が目立ちます。
理系ならではの冷静なデータ分析力や、課題を構造的に捉える力は、クライアントの課題解決に直結します。
さらに、研究でのプレゼン経験や資料作成能力も業務に直結しやすく、研究室での日々が無駄になることはありません。
柔軟な思考と専門外のフィールドに飛び込む勇気があれば、大きなチャンスが広がる業界です。
就職難易度が高い就活を成功させるポイント
早期から念入りに就活対策をする
難関企業を目指す場合、就活のスタートダッシュが内定への鍵となります。
特に理系学生は研究が忙しくなりがちなので、学部3年・修士1年の夏前には自己分析や企業研究を始めておくのが理想的です。
先に動くことで、インターンやOB訪問など貴重な機会に余裕をもって臨めます。
出遅れると人気企業の選考に間に合わない可能性もあるため、学業と並行して少しずつ準備することが重要です。
スケジュールを可視化し、研究とのバランスを取りながら進めましょう。
SPIと面接対策を早めに始める
SPIは多くの企業が一次選考で導入している筆記試験で、理系であっても文系問題が出題されるため油断は禁物です。
SPIの練習は早めに始め、特に言語分野の弱点を補強しておきましょう。
さらに、面接対策も同時進行で進めることが大切です。
理系の学生は研究内容ばかり話してしまいがちですが、企業が見ているのは「一緒に働きたいか」という点です。自己PRや志望動機を相手目線で練り上げて、納得感のある話し方を身につけましょう。
インターンで早期選考ルートに乗る
難関企業の多くは優秀な人材を確保するために、インターン参加者を対象に早期選考ルートを用意しています。
夏・冬に実施されるインターンに参加する方法で、選考フローを一部免除されたり、本選考よりも有利な条件で内定を狙えたりする可能性が高いです。
理系の場合、技術系インターンだけでなく企画やコンサル系の短期インターンも視野に入れておくと選択肢が広がります。
研究との兼ね合いでインターンに参加するか迷うかもしれませんが、スケジュールを工夫して少しでも参加しておくと情報収集と経験値の両面で大きな差がつきます。
逆求人サイトでオファーをもらう
逆求人サイトは、プロフィールを登録するだけで企業から直接オファーが届くサービスです。
逆求人サイト自分では気づかなかった企業や職種に出会えるチャンスが広がり、効率よく企業研究を進められる点も魅力です。
特に理系学生は研究や専門性が評価されやすく、スカウトの質が高い傾向があります。
企業側も志望度の高い人材にアプローチしてくるため、選考も比較的スムーズに進みやすいです。早い段階で登録しておくことで、思いがけない選択肢が広がる可能性があります。
理系就活生におすすめの就活サイトは、理系に特化した逆求人サイト「TECH OFFER」です。
TECH OFFERの利点は、理系を求める企業が利用しているため、専門性を活かした就職が叶いやすい点にあります。
TECH OFFERを活用して、自分の能力を最大限に活かせる職場を見つけましょう。
就職難易度が高い就活に対するよくある質問
学部生と院生はいつから就活を始める?
学部生は大学3年の春~夏、院生は修士1年の春頃から準備を始める人が多いです。
特に、インターンのエントリーは早く、夏インターンは6月〜7月に締切が集中します。
研究で忙しい理系学生は、早めにスケジュールを立てることが重要です。
就活の流れを早期に把握し、自己分析・業界研究を少しずつ進めておくことで無理のない形で本選考に入れます。
TOEICなどの資格はアピールとして有効?
TOEICスコアは企業によって評価のされ方が異なりますが、600〜700点以上あれば基礎的な英語力の証明になります。
外資系企業やグローバル展開している大手メーカーでは、800点以上が望まれるケースも多いです。
技術職であっても海外拠点とのやり取りがある場合、英語力が選考に影響する可能性があります。
英語以外にも情報系なら基本情報技術者、機械系ならCADなどの資格も評価対象になるため、アピールポイントの1つとして持っておくと安心です。
何社受けるのが普通?落ちる平均は?
就活では10〜30社にエントリーするのが一般的で、人気企業を多く狙う場合は30社以上になるケースもあります。
内定獲得の平均社数は1〜2社、選考に落ちる回数は10社以上にのぼる人も少なくありません。
特に、難関企業を受ける場合は「落ちるのが当たり前」くらいの気持ちでいた方が精神的にも楽になります。落ち込むより1社1社の経験を次に活かす姿勢が大切で、選考の通過率は人によって大きく異なるため、自分のペースで進める意識を持ちましょう。
専攻に関係ない企業・職種を受けても問題ない?
専攻に関係ない企業・職種を受けても問題ありません。
理系の専門性が活かせる企業も多い一方で、文理問わず理系の素養が活かせる職種も多く存在します。
たとえばIT、コンサル、営業、企画職などは専攻に関係なくチャレンジ可能です。
ただし、専攻とは異なる企業・職種を受ける場合は「なぜこの職種なのか」を明確に語れるようにしておきましょう。
専攻とのつながりが薄くても、納得感のある動機があれば評価は十分に得られます。
まとめ
理系の就職は「専門性があるから有利」と言われがちですが、実際は情報収集と準備の早さが成功のカギになります。
就職偏差値を参考にしつつも、自分の価値観やキャリアの軸に合った企業選びを心がけましょう。
難易度の高い就活を乗り越えるには、戦略的に動く力と柔軟な発想が求められます。
SPI対策や面接準備、インターン活用などの基本を押さえながら、自分に合った企業と出会える就活を目指しましょう。