こんにちは。理系就活情報局です。
就活では、書類選考や面接で様々な質問を受けることになります。面接では定番の質問から変化球の質問まで、多くの質問が出てくるでしょう。
定番の質問は自己紹介・志望動機が挙げられますが、挫折した体験を聞かれるのも珍しくありません。
「挫折体験って、一体どんなことを答えたらいいのだろうか」
「挫折体験の回答から、企業はどんなことを知りたいと思っているのだろうか」
「挫折体験の答え方や内容のポイント」について知りたいと考えている理系就活生に向けて、今回は挫折体験の上手な答え方のポイント・例文について解説します!
これから挫折体験の答え方について知りたいと考えている理系就活生は、ぜひ参考にしてください。
【この記事を読めば分かること】
- ・評価される「挫折経験」の伝え方が分かる(独自の6文型テンプレート付き)
- ・理系学生に特化した例文10選(研究・実験・プログラミング等)を参考にできる
- ・「挫折経験がない」と悩む人向けの答え方が見つかる
- ・面接官を納得させるNG例の改善方法が学べる
- ・ESと面接での伝え方の違いや深掘り質問への対策ができる
就活で聞かれる挫折体験とは

就活で聞かれる挫折体験には、主に以下の2種類があります。
- ・今までの人生で経験した失敗談
- ・希望が叶わず落ち込んだ経験
今までの人生で経験した失敗談
今までの人生で、「何も失敗したことがない」人はいません。
面接では、「今までの人生でどんな失敗があり、その内容や経験からどう感じたのか」を聞きたいと考えています。
希望が叶わず落ち込んだ経験
誰しも、全て希望通りの人生を送ってきたということはあり得ません。
何かしら希望が叶わず、落ち込んだりショックを受けたケースがあるはずです。
受験や部活などの大会での失敗したり、何かの選抜に落ちたりした経験があるのではないでしょうか。
人生を左右する大きな挫折である必要はなく、学生自身にとって「挫折である」と感じた内容を企業は聞きたいと考えています。
挫折と失敗の違い
挫折と失敗の違いを、簡潔にまとめました。
| 観点 | 失敗 | 挫折 |
| 定義 | ある行動や試みが、意図した成果につながらなかった状態 | 失敗をきっかけに「自分の限界や壁にぶつかり、うまく進めなくなる状態」 |
| 特徴 | 一時的な出来事として捉えられる | 心理的な停滞や落ち込み(傷ついたり、ショックを受ける等)を伴うことが多い |
理系的挫折の特徴(研究・実験・開発)
理系的挫折の特徴である研究・実験・開発における挫折体験になりうるものをまとめました。
| 種類 | 特徴 | 就活で語れるポイント |
| 研究での挫折 | ・理論や仮説通りに進まず、成果がすぐに出ない・文献との違いや、予想外の現象に直面して行き詰まる・自分の努力だけでは突破できず、長期間停滞することも多い | 「粘り強い探究心」や「問題を細分化して考える姿勢」を示せる |
| 実験での挫折 | ・装置の不調や条件設定の難しさで、思い通りのデータが取れない・同じ手順を繰り返しても再現性が得られず、原因が特定できない・膨大な試行錯誤や地道な作業に耐えなければならない | 「原因分析力」「課題を一つずつ検証する姿勢」「忍耐力」を伝えられる |
| 開発での挫折 | ・チームでの役割分担や進め方において調整が難しい・限られた時間・予算・資源の中で、理想を実現できない・メンバー間の意見の対立や設計上の制約に直面する | 「協働力」「リーダーシップ」「制約の中で工夫する力」を示せる |
企業が挫折体験を聞く理由

挫折体験からどんなことを学んだのかを知るため
挫折体験は内容にもよりますが、自信があるのにも関わらず他人との競争で負けたり、体調不良などでうまくいかなかったりしたなどの体験です。
「挫折を経験した際、どのように感じたのか」「なぜ挫折したのか」を話してもらうことで企業は学生が経験から学んだこと・感じたことを知ろうとします。
また、苦手なことが何かを知り、配属の参考にしたいと考えている場合もあります。
挫折をどのように乗り越えたのかを知るため
企業は「挫折体験をした後、どうやってその場面を乗り切ったのか」「克服するために努力したのか」を知りたいと考えています。
上記の過程には、精神的な強さ・心境の変化・学生なりのアイデアが潜んでいるためです。
仮に同じような挫折体験がある人がいたとしても、感じた気持ちや立ち直り方は人によって違います。
企業はその人ならではの乗り越え方から、人となりを知りたいと思っています。
挫折体験の中でどんな行動をとったのかを知るため
挫折体験の中で、どんな行動をとるかは学生によってまったく違います。
挫折体験とどう向き合い、解決するための手段を考える過程は、似たような方法を取った人がいたとしても決して同じではありません。
行動の過程を聞くことで、学生が持っている問題解決能力を測りたいと考えています。
評価観点チェックリスト
挫折体験を考えるにあたり、評価項目となりうる観点からチェックリストを作成しました。
| 項目 | 評価観点 | 具体例 |
| 挑戦度 | どのくらい本気で取り組んだか | ・難易度の高いテーマ・課題に挑戦したか・自分にとって「簡単」ではない挑戦であったか・研究・実験・学外活動などで努力を積み重ねたか |
| 原因分析 | 失敗の理由をどう捉えたか | ・挫折の要因を客観的に説明できるか・自分の力不足/環境要因を冷静に整理しているか・感情論にとどまらず、論理的に振り返れているか |
| 再現性 | 学びを次に活かしたか | ・挫折から得た教訓を明確に言語化できるか・その後の研究・活動で改善策を試し、成果につなげたか・社会人になっても応用できる姿勢が示せているか |
| ストレス耐性 | 折れずにどう行動したか | ・困難や失敗に直面した際、粘り強く取り組んだか・一時的に落ち込んでも再起できたか・チームや指導者と協力しながら打開を図ったか |
テックオファーに登録しておくと意外な企業が自分を評価してくれる
テックオファーのようなスカウト型の就活サイトに登録することで、自分の特性や考え方に近い企業からオファーが来ることがあります。
特に、学業と就活の両立が大変な理系学生は、窓口を増やしておくと効率よく就活を進めることが可能です。
学生が一人で見つけられる企業には、物理的な限界があります。
就活の可能性を広げるためにも、スカウト型就活サービスを活用してみましょう。
面接でアピールするのにふさわしい挫折体験

研究で成果が出ない
研究の方向性が定まらず、成果に結びつかなかった経験は専攻問わず多くの理系学生が経験しやすい挫折体験です。
| 内容例 | ・何度も仮説を立て直しても成果が出なかった・文献と結果が一致せず、方向性を見失った |
| 乗り越え方 | 試行錯誤を続け、テーマを再定義して研究を前進させた |
実験トラブル
装置や条件の問題で実験が思うように進まなかった経験も、経験として多い挫折になります。
| 内容例 | ・装置の不具合や条件設定の難しさでデータが取れなかった・失敗が続き原因特定に時間がかかった |
| 乗り越え方 | 手順を細かく検証し、先輩・教員と相談しながら改善した |
ラボ人間関係
研究室内の協働やコミュニケーションでつまずいた経験も珍しくありません。
| 内容例 | ・研究室内での役割分担や情報共有がうまくいかず停滞した・先輩や同僚との意見の食い違いに苦労した |
| 乗り越え方 | コミュニケーションを増やし、合意形成を図る工夫をした |
プログラミング障害
プログラム開発や解析でコードが動かず、前進できなかった経験などが該当します。
| 内容例 | ・コードのエラーやバグが解決できず開発が進まなかった・複雑なアルゴリズムが理解できず壁にぶつかった |
| 乗り越え方 | 基礎に立ち返り、分解して調査・改善を繰り返した |
ロボコン敗退
ロボコンに限らず、チームで挑戦した競技で思うような成果を得られなかった経験が該当します。
| 内容例 | ・チームで挑んだ大会で期待に反して敗退した・設計上の不備や練習不足、時間管理の甘さが原因 |
| 乗り越え方 | 原因分析を行い、次回に向けて改善策を共有・実行した |
高評価につながる効果的な挫折体験の伝え方

挫折体験など面接で効果的な伝え方としてよく使われる型に、「STAR法(Situation/Task/Action/Result)」があります。そして、「CAR法(Challenge/Action/Result)」を掛け合わせ、さらに「学び」と「活用」まで加えた6ステップ構成にするとより相手に伝わりやすくなります。
STAR法とCAR法を組み合わせた構成を図解すると、次のとおりです。。
| 項目 | 内容 | 例文 |
| 結論(Challenge) | どんな挫折・課題に挑んだか? | 私は◯◯という課題に挑戦し、当初は△△で挫折しました。 |
| 要因(Situation/Task) | なぜ挫折したのか?原因は? | 原因は□□にあり、状況を分析して理解しました。 |
| 対策(Action) | どう工夫し、どんな行動をとったか? | そこで私は◇◇の工夫を行い、具体的に××を実践しました。 |
| 成果(Result) | その結果どうなったか? | 結果として、▽▽を達成することができました。 |
| 学び(Reflection) | 挫折から何を学んだか? | この経験から、●●の重要性を学びました。 |
| 活用(Application) | 学びを今後どう活かすか? | 今後はこの学びを活かし、貴社でも★★に取り組んでいきたいです。 |
結論(Challenge)
結論では、出来事の概要と感じたことを説明するのが大切です。同じような出来事に遭遇しても、どう感じるかは学生によって違います。
結論の部分は学生自身の個性や性格を端的に表せる上、採用担当者も知りたいと思っているところです。しっかりと自分の言葉で語れるようにしておきましょう。
要因(Situation/Task)
要因のセクションでは、出来事に対し、自分なりの解釈を説明するのが効果的です。
分かりやすさも重要ですが、自身がどう捉えているのかを説明すれば、自分にしかできないアピールとなります。
対策(Action)
「挫折体験に対してどのような対策を打ち、どんな経過で立ち直り、変わっていったのか」を表す一番重要な部分です。
「どんな工夫をして乗り越えたのか」「どんなことを試行錯誤したのか」をしっかり話すと自分らしいアピールとなります。
成果(Result)
今までの経緯から、どんな成果(結果)を得たのか、客観的な視点と感情的な成長を盛り込み、説明しましょう。
学び(Reflection)
挫折体験から学んだことも、大切な部分です。
自分なりの言葉で説明し、成長したことをアピールしましょう。一つではなく、多くのことを学んだと言えるようにしておくのをおすすめします。
活用(Application)
「今後、どのように生かしていこうと考えているのか」について、志望企業の仕事と絡めて伝えられるとベストです。
仮に、志望企業の仕事と絡めることができなくても「社会人としてこんな風に活用していきたい」と未来志向で語るようにしましょう。
「挫折経験がない」時の答え方
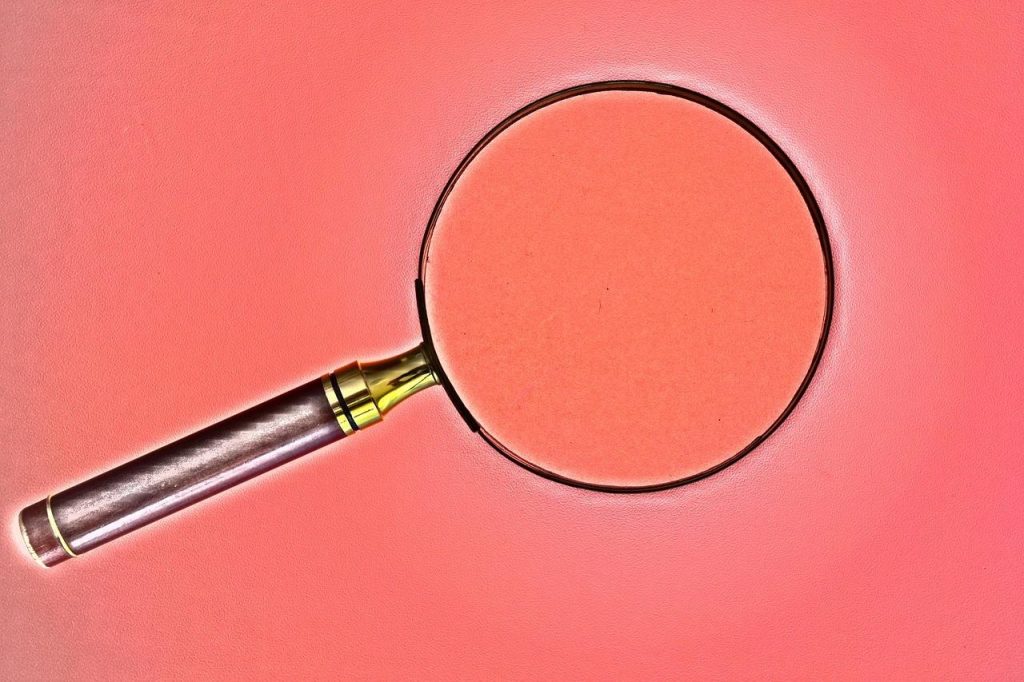
挫折経験の見つけ方
挫折経験が思い浮かばないときは、以下の視点で探すと見つけやすくなります。
| 種類 | 具体例 |
| 小さな失敗 | 研究や実験でのミス、アルバイトでのミスなど |
| 挑戦の経験 | 大会や資格試験、学外活動に挑戦して思うようにいかなかったこと |
| 自問の経験 | 将来や研究テーマに悩み、自分の考えを整理するのに苦労したこと |
大切なのは「挫折の大きさ」でなく、壁をどう乗り越えたかを語れることです。
挫折経験の回答例
・例1:小さな失敗からの学び
研究で初めて実験を任された際に、操作ミスでデータを無駄にしてしまいました。原因を整理し、マニュアルを自作して以降は安定した実験ができるようになりました。この経験から、準備と再現性を意識する習慣が身につきました。
・例2:挑戦を通じた挫折
プログラミングコンテストに参加した際、時間内に成果物を完成させられませんでした。原因は作業分担の甘さにあると気づき、その後の学習ではタスク管理を徹底するようにしました。この経験から、計画性と協働の大切さを学びました。
注意点
挫折経験を語る際には、以下の点に注意が必要です。
| ポイント | 説明 |
| 他責にしない | 環境や他人のせいにせず、自分がどう考え、どう動いたかを語る |
| 未来志向で締める | 過去の失敗や挫折で終わらず、「その学びを社会人としてどう活かすか」で結論づける |
| 全体としての効果 | 「失敗した学生」ではなく、「失敗から成長できる人材」として印象づけられる |
NG例と改善例

ここでは、よくあるNG例と改善例を表にまとめました。
| NG例 | 改善例 |
| 諦めただけ例;研究が難しくて途中で投げ出しました。 | 挑戦と行動を強調研究が難航し一度は行き詰まりましたが、原因を再分析しテーマを絞り直すことで前進できました。 |
| 学び無し例:ロボコンで負けました。悔しかったです。 | ロボコンで敗退しましたが、原因は練習不足と分担の曖昧さだと気づき、翌年は役割を明確化して改善しました。 |
| 私的すぎる例:実験で手順を間違えて失敗し、1人で落ち込んでいました。 | 理系向けに具体化実験で手順を誤りデータが取れなかったことがありましたが、原因を分析し手順書を作成、再現性を高める工夫をしました。 |
挫折体験の例文集
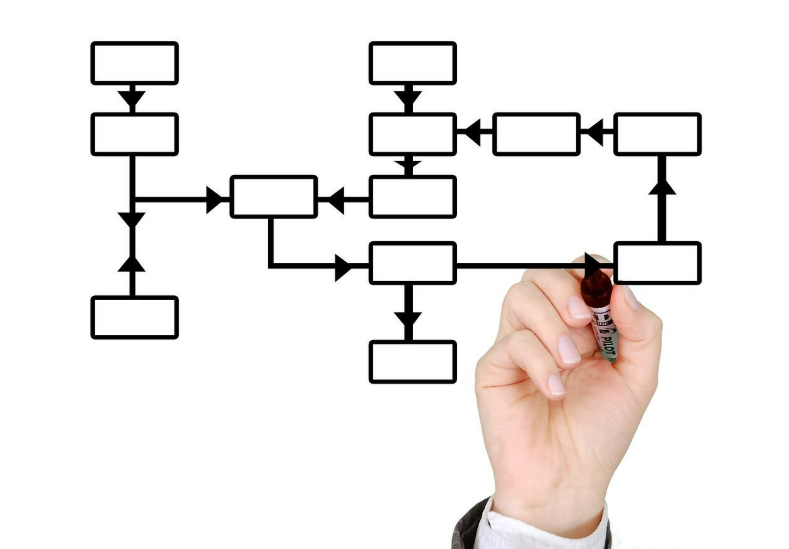
学業
私は専門科目で理解が進まず成績が伸び悩みました。原因は基礎知識の不足と勉強方法の偏りにあった状況です。そこで、過去問分析とグループ学習を取り入れ、学習方法を改善しました。その結果、次の試験で成績が大幅に向上しました。この経験から、学習方法を見直すことの重要性を学び、今後も未知の課題に直面した際は効率的なアプローチで取り組む姿勢を活かしていきたいです。
受験
大学院入試で一次試験に不合格となりました。原因は専門知識の深堀り不足と時間配分の失敗です。そこで、参考書を精査し、模試で時間管理を徹底しました。その結果、二次試験で合格できました。この経験を通じて計画的学習と自己分析の大切さを学び、今後は研究職として研究や業務でも計画性を意識して取り組みたいです。
サークル
大会の運営でリーダー役を務めましたが、最初は混乱が生じました。原因は役割分担が不明確で、連絡ミスが重なったことです。そこでタスク表を作成し、定期的に進捗確認を行いました。その結果、大会は無事成功しました。この経験から組織内の情報共有の重要性を学び、今後貴社でチームで業務に取り組む際、計画と確認を徹底して取り組みたいです。
アルバイト
新メニュー導入時に調理ミスを連続して起こしました。原因は手順の理解不足と確認不足です。そこで手順書を作成し、先輩に確認を依頼する習慣を導入しました。その結果、ミスが減りスムーズな業務運営が可能になりました。この経験から、確認の重要性と手順の標準化の価値を学び、職場や研究での手順改善に活かしていきたいです。
留学
海外での授業についていけず、最初は成績が伸びませんでした。原因は言語力と事前知識不足です。そこで自主学習と現地学生とのディスカッションを積極的に行いました。その結果、成績が向上し、学内発表で評価されました。この経験から、課題に対して主体的に取り組む姿勢を学び、今後は貴社の海外事業部でも積極的に挑戦していきたいです。
研究で成果が出ない
研究テーマが思うように成果につながらず、進め方に悩みました。原因は仮説設定の不十分さと実験計画の甘さです。そこで実験条件を再整理し、文献を参考に改善策を試しました。その結果、一定の成果を出せました。この経験から、課題分析と柔軟な対応の重要性を学び、貴社でも研究や開発でも○○として応用したいです。
装置のトラブル
実験中に装置の不具合が発生し、データが取れませんでした。原因は操作手順の誤りと装置管理不足です。そこで手順を見直し、装置メンテナンスを徹底しました。その結果、実験を再開でき、安定したデータが得られました。この経験から、準備と確認の重要性を学び、貴社でも安全で再現性の高い実験を心がけます。
論文のリジェクト
投稿した論文が査読でリジェクトされました。原因は考察の浅さと文献整理の不足です。そこで査読コメントを分析し、内容を修正して再投稿しました。その結果、論文が採択されました。この経験から、批判的フィードバックを受け入れ改善する力を学び、今後の研究活動に活かしたいです。
バグの修正
プログラミング課題でコードにバグが多発し、開発が進みませんでした。原因は理解不足とテスト不足です。そこでコードを分割してデバッグを行い、再現性を確認しました。その結果、プログラムが正常に動作するようになりました。この経験から、問題を細分化して着実に解決する力を学び、SE職に就いても開発業務に活かしたいです。
安全管理
化学実験中に安全管理の不備で事故が発生しそうになりました。原因は手順確認不足と危険予知の欠如です。そこで実験手順を再確認し、安全チェックリストを作成しました。その結果、事故を未然に防げました。この経験から、安全意識と手順の徹底の重要性を学び、貴社で開発職に就いた際も研究や実験で活用します。
ESと面接の違い
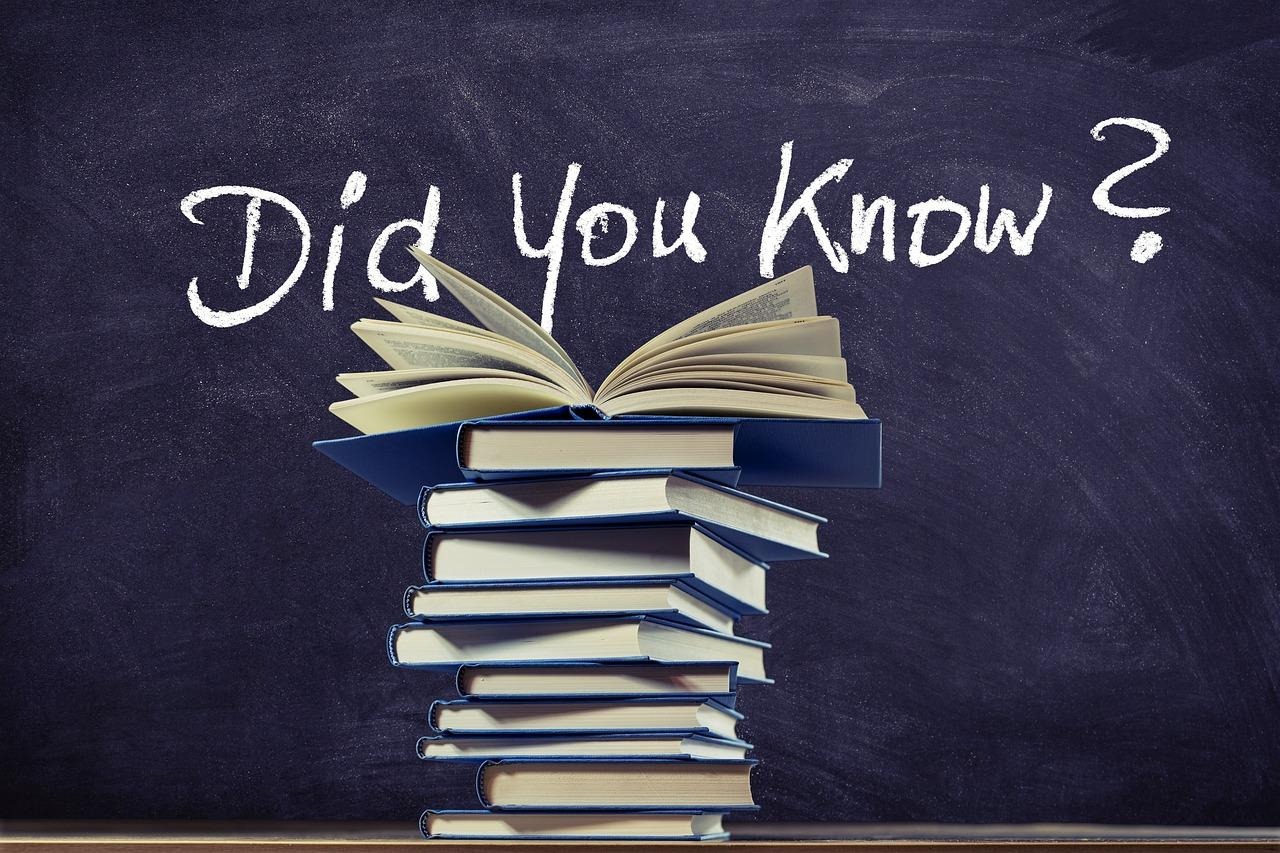
「ESでは文字で正確に伝え、面接では口頭で熱意と具体性を伝える」のように使い分けると効果的です。
ESの書き方
ESの書き方に関して、要点をまとめると以下のとおりです。
| 項目 | ポイント |
| 要約 | ・文章は簡潔にする・1つのエピソードに対して「課題→行動→成果→学び」の流れを意識して書く・長くても200~300字程度に収めるのが基本 |
| 分量 | ・企業によって文字数制限があるため、制限内で必要な情報を盛り込むことが大切・長すぎる文章は読みにくく、短すぎると内容が伝わらない |
| 見出し | ・小見出しや段落分けを使って、読みやすさを意識する・例えば「課題」「行動」「成果」「学び」と区切るだけでも読みやすさが向上する |
面接の話し方
面接は話すスピードや表情、声のトーンも評価対象になります。時間に応じた話し方の目安を整理しました。
・30秒台本(短時間アピール)
「私は〇〇に挑戦し、△△で壁にぶつかりました。しかし□□を行った結果、▽▽を達成しました。この経験から▲▲を学び、今後に活かしたいです。」
・60秒台本(中時間アピール)
「私は〇〇という課題に挑戦しました。最初は△△でうまくいかず挫折しましたが、原因分析を行い□□という対策を取りました。その結果、▽▽を達成できました。この経験から、▲▲を学び、今後の業務でも活かしていきたいと考えています。」
・90秒台本(深掘りアピール)
「私は〇〇に取り組みました。初めは△△で壁にぶつかり、非常に困難でした。原因を分析した結果、□□の課題があると分かり、具体的に◇◇を実践しました。その結果、▽▽を達成できました。この経験から▲▲の重要性を学び、計画性や課題解決力を身につけられました。これらを活かし、貴社では★★に貢献したいと考えています。」
面接では時間に合わせて要点を整理し、声のトーンや表情で自信を伝えることが大切です。
想定深掘りQ&A

「本当に学びはありましたか?再発防止策は?」と聞かれた場合
はい、学びは明確にあり、再発防止策も実行しました。例えば、実験データが思うように得られず失敗した際、原因は手順の確認不足と条件設定の甘さにあると分析しました。その後は手順書を整備し、条件を一覧化して実験前に必ず確認する習慣をつけました。この方法を以後の実験すべてに適用した結果、データの再現性が向上し、同じ失敗は起こらなくなりました。
「なぜその原因に気づけなかった?」と聞かれた場合
当初は原因に気づけませんでした。理由は、複雑なシステム全体を把握せず、目の前のコードの動作だけに注目していたためです。失敗を重ねて初めて、全体構造のどこに不整合があるかを分析する必要があると気づきました。その後は、システム全体のフロー図を作成し、テストケースごとに原因を追跡する方法を導入しました。これにより、同様の問題を早期に特定できるようになりました。
「入社後はどのように活かせる?」と聞かれた場合
入社後は、研究や開発プロジェクトで同じ手順改善や再現性向上の経験を活かせます。具体的には、新規実験や製品開発の立ち上げ時に、手順書の整備や条件管理を徹底して効率的かつ安定した成果を出せると考えています。また、チーム内での情報共有や進捗管理にも活用し、全体の成果向上に貢献したいです。
まとめ
今回は、就活で挫折体験を企業が聞く理由や、ふさわしい内容、例文まで解説してきました。
企業は、できるだけ学生のいい所を見つけたいと思って選考しています。
決して落とそうと思っているわけではなく、人柄や考え方が自社と合うかを判断したいと思い挫折体験を聞いてくるのです。
自分の体験を、しっかりと話せるように整理してみてください。





