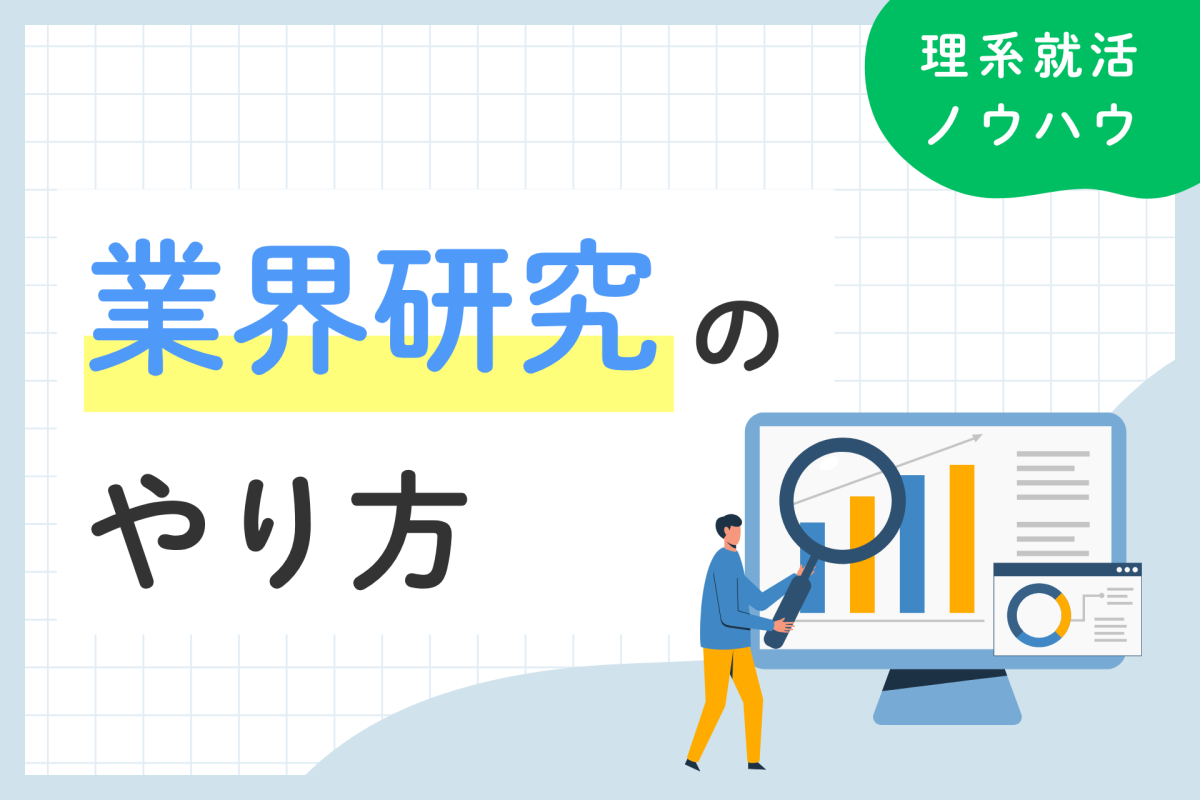こんにちは。理系就活情報局です。
就職活動を進める中で、「業界研究って何をどう進めればいいの?」と疑問を持つ方は少なくありません。この記事では、業界研究の具体的な進め方やその目的、そして知っておくべき業界の8分類についてわかりやすく解説いたします。
業界研究を正しく行うことで、あなたの志望業界が明確になり、就職活動での成功がぐっと近づくはずです。この記事を通じて、ご自身に合った業界を見つけ、その業界への理解を深めるきっかけにしていただければ幸いです。
業界研究とは

業界研究とは、企業を分類する「業界」ごとの仕組みや特徴、最新のトレンドを深く理解するための調査活動を指します。
特に就職活動においては、志望業界や企業選びの土台となる、非常に重要なステップです。その目的を明確に理解し、適切な方法で進めることが、就活成功への鍵となります。
業界研究の意味と目的
業界研究は、特定の業界の仕組み、トレンド、市場規模や成長性など、全体像を把握するための活動です。その目的は、就職活動において志望する業界を絞り込み、自分に適した業界や企業を見つけることにあります。
また、業界内での競合や、各企業の強み・弱みを理解することで、志望動機に説得力を持たせることが可能です。さらに、業界全体の動向を把握することは、企業選びにおけるミスマッチを防ぎ、長期的なキャリア設計にもつなげることができます。
そのため、新卒の就職活動を成功させるためには、業界研究は欠かせないプロセスと言えるでしょう。
業界研究が必要な理由
業界研究が必要な理由は、大きく3つあります。
第一に、自分が志望する業界の全体像を理解し、自分に適しているかを判断できる点です。例えば、業界の市場規模、成長性、平均年収、働き方などを知ることで、長期的なキャリアに対する安心感を得ることができます。
第二に、面接時に説得力のある志望動機を伝えるためです。「なぜその業界なのか」をしっかり説明することで、採用担当者にあなたの意欲を強くアピールできます。
第三に、就職活動中の選択を効率化する役割を果たします。知識が無いまま手当たり次第に企業を検討するのは時間の浪費です。業界研究を通じ、取るべき具体的な選択肢を絞り込むのが、合理的な方法と言えます。
業界研究と業種研究の違い
業界研究と業種研究は混同されがちですが、それぞれ異なる意味と目的を持っています。
業界研究は、企業を事業やサービスで分類した「業界」の市場動向や構造を幅広く理解する活動です。たとえば、金融業界全般やIT・通信業界の全体像を把握するのがこれにあたります。
一方、業種研究は、特定の業種や職種に焦点を当てるものです。たとえば、IT業界内の「システム開発」を手掛ける企業のリサーチなどが該当します。
就職活動においては、まず業界研究で大きな枠組みを理解し、その後に特定の業種や企業について詳細な研究を行うことが効果的です。そのため、まずは業界研究から始め、全体的な視野を広げた上で業種研究へと移行するのが理想的なステップです。
就活成功に繋がる業界研究の重要性
業界研究は、新卒の就職活動を成功させる上で非常に重要な位置づけにあります。
第一に、自分に合った業界を見極めることで、キャリアの方向性を定める助けになります。業界の全体像を理解すれば、成長性や働き方について把握し、誤った選択を防ぐことが可能です。
第二に、面接やエントリーシートで志望動機を述べる際、説得力を持たせることができます。採用担当者に対し、「なぜその業界を志望するのか」を具体的かつ論理的に伝える能力は、内定取得に直結します。
第三に、競合分析や市場動向の把握を通じて、今後のキャリアビジョンを形成することができます。
以上の理由から、しっかりとした業界研究の方法を習得することは、将来の成功に繋がる非常に大切な土台となります。
業界研究のやり方

就職活動を成功させるには、計画的な業界研究が欠かせません。
本セクションでは、業界研究の具体的な進め方や手順について解説します。全体像の把握から情報収集のコツ、そして効果的な記録方法まで、実践的なアプローチを学ぶことで、知識を体系的にまとめる方法が身に付くでしょう。
1. 業界の全体像を把握する
業界研究の第1歩は、業界全体像を「広く浅く」把握することです。
業界全体を理解することで、主要なプレイヤーや基本的な市場構造を知ることができます。具体的には、業界団体のホームページや統計資料、ニュース記事などを活用して業界の規模や特性を調査しましょう。
また、大まかな業界の8分類(メーカー、金融、サービスなど)を念頭に置き、それぞれの特徴を把握することが役立ちます。例えば、メーカーは製品の開発や生産に強みを持つ一方、IT業界や通信業界では技術革新が求められるなど、業界ごとに異なる特性が見えてくるでしょう。
全体像を掴むことは、より深い理解を進めるための確実な土台となります。
2. PEST分析で業界の「外部環境」を理解する
業界研究を成功させるカギの一つは、その業界を取り巻く社会や政治、技術などの大きな流れ(外部環境)を理解することです。
この外部環境をシンプルに整理できるのが「PEST分析」です。 これは、業界の成長性や将来性を予測するために、以下の4つの視点から情報をチェックするフレームワークです。
| 項目 | 視点(何を探るか) | 具体的なチェック例(就活生の視点) |
| Political(政治) | 法律や制度、国の政策が業界に与える影響。 | 「規制緩和や増税の動きは?」「政府が推進する技術(例:環境技術)に該当するか?」など |
| Economical(経済) | 景気や市場動向、物価などが業界に与える影響。 | 「景気によって売上が大きく左右されるか?」「円高・円安の影響は?」「業界の市場規模は伸びているか?」など |
| Social(社会) | 人々の価値観、ライフスタイル、人口構造の変化。 | 「リモートワークは一般化しているか?」「少子高齢化はビジネスチャンスか、リスクか?」「サステナビリティ(持続可能性)への関心は高いか?」など |
| Technological(技術) | 新しい技術開発やインフラの進化が業界をどう変えるか。 | 「AIやIoTなどの導入で仕事のやり方が変わるか?」「競合他社にない革新的な技術を持っているか?」など |
このPEST分析を行うことで、業界全体がこれから伸びるのか、どんなリスクがあるのかを客観的に判断できるようになります。
これは面接で「なぜこの業界を選んだのか」を語る際の、説得力のある根拠になります。
3. 興味のある業界を選定する
業界全体像を把握したら、今度は自分が興味を持つ業界を絞り込むステップに進みましょう。そのためには自己分析が重要です。
自分の興味や価値観、将来のキャリアビジョンを明確にすることで、志望業界が見つかりやすくなります。例えば、社会貢献に関心があるなら、医療や環境関連の業界が適しているかもしれません。
これに加え、複数の業界を比較することも選定の参考になります。いきなり1つの業界に絞り込むのではなく、まずは2〜3の候補をリストアップし、それぞれの魅力や課題を深堀りしてみてください。
こうしたプロセスを通じて、自分に最適な業界を具体的に見極めることが可能になります。
4. ツールを活用する
業界研究を進める際には、効率的な情報収集が鍵となります。特におすすめなのが業界団体の公式サイトや発行されるレポートです。これらには業界の最新動向や課題が詳しく記載されています。
また、就活生向けに提供されている情報ポータルサイトや求人情報サイトも役立ちます。さらに、SNSやオンラインニュースなどのデジタルプラットフォームも情報収集の強力なツールとなります。最近では、YouTubeやPodcastなどで業界専門家が解説するコンテンツも人気があります。
これらのツールを使って多角的な情報を集め、業界に対する理解を深めていきましょう。具体的なツールを活用することにより、業界研究をより充実させることが可能になります。
5. 業界研究ノートを作成する
業界研究を進める際に、収集した情報を効率的に整理するためには、専用の業界研究ノートを作成するのが効果的です。このノートには、業界・業種ごとの基本情報や市場動向、主要企業の一覧などを記録していきましょう。
例えば、気になる業界については「市場規模」「主要プレイヤー」「直面する課題」などの見出しを設け、それぞれを詳しく調べて書き込むと良いでしょう。さらに、調査中に得た気付きを追記することで、志望動機作成や面接対策の材料として有効活用できます。また、情報を視覚化するために図や箇条書きを取り入れると、理解が深まります。ノートを活用することで、自分だけの「業界の教科書」を作り上げることができます。
志望動機の作成につながるフォーマット
集めた情報をただ書き出すだけでなく、就活で使えるように整理することが大切です。ここでは、集めた情報がそのまま志望動機や面接対策につながる、シンプルな研究フォーマットを提案します。この表に沿って情報を埋めるだけで、あなたの「業界の教科書」が完成します。
| 項目 | 具体的な内容(リサーチ結果を記入) | 企業研究・面接への活かし方 |
| 基本情報 | 業界の定義、市場規模、主要なビジネスモデル、平均年収、歴史など。 | 業界を深く理解している証拠として、面接官に信頼感を与える。 |
| 主要プレイヤー | シェアトップ企業、特徴的な競合他社(海外企業も含む)、各社の強み。 | 志望企業が業界内でどんな立ち位置か、なぜその企業を選ぶかを説明する根拠になる。 |
| トレンド・課題 | 業界が今注目している技術(例:AI、DX)、直面している社会的な問題、今後の成長予測。 | 「この業界を選んだ理由」や「将来やりたいこと」を語る際の、説得力ある背景情報になる。 |
| 働く人・環境 | どんな職種があるか、平均的な働き方(ワークスタイル)、キャリアパス。 | 入社後のイメージを具体的に持ち、面接で「入社意欲の高さ」を示すことができる。 |
| 自分との接点 | この業界のどんな点に一番魅力を感じたのか? 自分の価値観や目標とどう繋がるか? | ここが最も重要! 志望動機の核となる部分を言葉にする。 |
研究を進めるときは、「トレンド・課題」を深く掘り下げ、「自分との接点」を明確にすることを意識すると、より良い志望動機が生まれます。
業界の8分類

就職活動を成功させるためには、自分が志望する業界について正確に理解することが重要です。数多くの業界の中から、自分に最適な業界を見つけるためにも、基本的な8分類を知っておくことがポイントです。
ここでは、それぞれの業界の特徴や具体例について詳しく解説します。
1. 製造業界
製造業界は、原材料を加工・生産して製品を作る企業が属する業界です。
この業界には、自動車メーカーや食品メーカー、電子機器メーカーなどが含まれます。主に製造工程や商品の完成度が重視される分野であり、効率的な生産体制や技術革新が競争力の鍵となります。
また、国内市場だけでなく海外市場にも進出しやすい傾向があり、グローバルにビジネスを展開している企業が多いのも特徴です。製造業界で働くことを目指す場合には、その企業が手掛ける商品の特徴や生産プロセス、業界内でのシェアなどを調査することが大切です。
志望動機を明確にするためにも、具体的な企業の取り組みや業界の動向を理解することが欠かせません。
2. IT・通信業界
IT・通信業界は、インターネットや通信サービス、ソフトウェア開発を行う企業で構成されています。
近年では、テクノロジーの進化とともにクラウドサービスやAIの活用が加速し、業界全体が急成長を遂げています。代表的な業種としては、システムインテグレーション、通信キャリア、アプリケーション開発企業などが挙げられます。
この業界では技術革新のスピードが速く、柔軟性や適応力が求められます。また、新卒採用の際には理系だけでなく文系の学生も活躍できるチャンスが広がっています。
業界研究では、業界内のトレンドや将来的な技術の進化などを深掘りし、自分が貢献したい分野を見つけることが重要です。
3. 金融業界
金融業界は、資金を仲介したり運用したりするサービスを提供する企業が所属する業界です。
銀行や保険会社、証券会社はこの業界の代表格で、個人や企業の資産管理を担っています。経済全体の中心とも言える存在であり、安定感と専門性が求められる分野です。
この業界では、顧客対応能力や数字に強い分析力が重要視されるため、新卒採用でも論理的思考力がアピールポイントになります。また、金融業界は他業界とも関連性が深く、経済全体の構造も把握しておく必要があります。
業界研究では、具体的な市場規模や業界動向、主要プレイヤーの事業内容を調査することが鍵となります。
4. 商社・流通業界
商社・流通業界は物資や製品を効率よく流通させる役割を果たしている業界です。
総合商社は、多岐にわたる事業を手がけながら海外市場にも進出しており、グローバルな視点での仕事が可能です。一方、専門商社は特定の分野に特化しており、深い専門知識を生かした提案型営業が強みです。
また、流通に関わる企業では、製品の在庫管理や物流の効率化が重要なテーマとなります。就職活動においては、商社ならではの「モノを動かす」仕組みや、社員がどのように海外企業と交渉しているかなどを調べることが効果的です。
業界研究を通じて、業種ごとの異なる特徴を把握しましょう。
5. サービス業界
サービス業界は、旅行や外食、娯楽など、人々の日常生活を支える幅広い分野から成り立っています。
この業界では、顧客満足度の向上がビジネスの成否を左右する重要な要素です。観光業ではインバウンド需要が高まっており、飲食業界では新たな業態の開発が求められています。
また、映画や音楽といったエンターテインメント業界では、消費者の心をつかむ企画力がカギとなります。
6. 建設・不動産業界
建設・不動産業界は、人々の生活基盤となる「空間」を提供する業界です。
建設業界は、ビルや道路、ダムといったインフラの計画・建設(ゼネコンなど)を担い、不動産業界は、土地や建物の開発(デベロッパー)、売買、賃貸、管理を行います。
この業界の特徴は、扱う金額の大きさやプロジェクトのスケール、そして完成までに長い期間を要することです。景気や金利動向の影響を受けやすく、近年は環境配慮(グリーンビルディング)や地震・災害対策などの技術革新が求められています。
就活では、街づくりへの貢献意欲や、長期的な視点での問題解決能力をアピールすることがポイントになります。
7. インフラ・電力業界
インフラ・電力業界は、人々の生活や経済活動に不可欠な基盤(ライフライン)を提供する業界です。
電気、ガス、水道といったエネルギー供給から、鉄道、航空、海運といった運輸・交通、そして物流まで幅広い分野が含まれます。
この業界の大きな特徴は、公共性・安定性が高いことです。生活に不可欠なサービスであるため、景気の変動を受けにくく安定した事業基盤を持っています。一方で、国の規制や政策の影響を強く受けます。就活生は、社会貢献性の高さや安全・安定供給の責任感を志望動機に結びつけることが重要です。
最近は、再生可能エネルギーへの移行や効率化など、変革期にあるため、その動向を研究しましょう。
8. 医療・福祉業界
医療・福祉業界は、人々の「健康」と「生活の質(QOL)」を支える業界です。
病院やクリニック、介護施設などのサービス提供側と、製薬会社や医療機器メーカーなどの製品開発・提供側で構成されます。
日本においては少子高齢化が進む中で、この業界の役割と市場規模は拡大し続けています。特に、IT技術を活用した医療(遠隔医療、電子カルテなど)や、予防医療分野が成長しています。
この業界では、専門知識はもちろんのこと、倫理観や強い使命感が求められます。業界研究を通じて、自分が「社会のどんな課題を解決したいのか」という熱意と、そのための具体的な役割(職種)を明確にすることが成功の鍵となります。
就職活動の際には、顧客ニーズや市場動向を踏まえながら、働きたい企業が提供するサービスや理念を調査しましょう。どの分野においても、具体的なエピソードを交えた志望動機が求められるため、業界研究を念入りに行うことが成功への秘訣です。
業界研究を効率化するポイント

就職活動を効率的に進めるためには、業界研究を計画的かつ戦略的に行うことが欠かせません。業界研究を効率化するにはスケジュール管理やツール活用の工夫、さらにはインターネットだけに頼らず多角的なアプローチを取ることが必要です。
このセクションでは、業界研究を成功に導くための具体的な方法をご紹介します。
スケジュール管理で業界研究を効率化する
業界研究をスムーズに進めるには、計画的なスケジュール管理が重要です。まず、就職活動全体のスケジュールを把握し、その中で業界研究を行う時間を確保しましょう。例えば、就活スタート初期の1〜2ヶ月間は業界全体を幅広く調査し、その後に絞り込むステップを踏むと効率的です。また、1日1時間や週末のまとまった時間など、無理のないリズムで進めると長続きします。
さらに、タスク管理ツールやカレンダーアプリを活用すると、進捗状況を可視化できて便利です。その際、「どの業界を調査中か」「どの情報を収集済みか」を明確にすることで、抜け漏れを防げます。このような計画的なスケジュール管理により、効率的かつ効果的な業界研究が実現できます。
インターネット以外も活用する
業界研究はインターネットだけに頼らず、他の情報源を活用することでより深い理解が得られます。その一つが、業界研究セミナーや合同説明会への参加です。これらの場では、実際に業界で働く社会人から直接話を聞く機会があり、業界内の雰囲気や具体的な仕事内容を把握することができます。
また、インターンシップも非常に効果的です。インターンでは実際の業務を体験することができ、企業や業界の実情を具体的に理解できます。この経験を通じて、自分に合った業界を見つけるヒントを得ることが可能です。こうしたリアルな場で得られる情報は、インターネットだけでは得られない貴重なものとなります。
業界研究と企業研究を結びつける
業界研究と企業研究は密接に関連しています。それぞれを切り離して行うのではなく、業界研究を基に企業研究を進めていくことで、効率的かつ具体的な情報収集が可能です。例えば、業界全体のトレンドや課題を理解した上で、各企業がどのように対応しているかを調べると、それぞれの企業の強みや差別化ポイントが分かります。
また、企業比較を行う際にも業界研究が役立ちます。収集した業界全体の知識を基に、企業を比較する視点が明確になるため、自分に合った企業選びがしやすくなります。これは志望動機や面接での受け答えにも大いに活きてくるため、業界と企業を結びつけた研究が成功の鍵となります。
志望動機の作成法
業界研究ができたら、その内容をきちんと整理し志望動機の作成に活かすことが重要です。
ここでは、業界研究をもとに志望動機を作成するときに役立つ2つのことをご紹介します。これらを活用して、オリジナルな志望動機を作成できるようにしましょう。
志望動機の作成につながるフォーマット
集めた情報をただ書き出すだけでなく、就活で使えるように整理することが大切です。
ここでは、集めた情報がそのまま志望動機や面接対策につながる、シンプルな研究フォーマットをご紹介します。この表に沿って情報を埋めるだけで、あなたの「業界の教科書」が完成します。
| 項目 | 具体的な内容(リサーチ結果を記入) | 企業研究・面接への活かし方 |
| 基本情報 | 業界の定義、市場規模、主要なビジネスモデル、平均年収、歴史など。 | 業界を深く理解している証拠として、面接官に信頼感を与える。 |
| 主要プレイヤー | シェアトップ企業、特徴的な競合他社(海外企業も含む)、各社の強み。 | 志望企業が業界内でどんな立ち位置か、なぜその企業を選ぶかを説明する根拠になる。 |
| トレンド・課題 | 業界が今注目している技術(例:AI、DX)、直面している社会的な問題、今後の成長予測。 | 「この業界を選んだ理由」や「将来やりたいこと」を語る際の、説得力ある背景情報になる。 |
| 働く人・環境 | どんな職種があるか、平均的な働き方(ワークスタイル)、キャリアパス。 | 入社後のイメージを具体的に持ち、面接で「入社意欲の高さ」を示すことができる。 |
| 自分との接点 | この業界のどんな点に一番魅力を感じたのか? 自分の価値観や目標とどう繋がるか? | ここが最も重要! 志望動機の核となる部分を言葉にする。 |
研究を進めるときは、「トレンド・課題」を深く掘り下げ、「自分との接点」を明確にすることを意識すると、より良い志望動機が生まれます。
業界研究を基に志望動機を練るコツ
業界研究を活用して志望動機を練る際には、業界の特性やトレンド、その中で自身がどう貢献できるかを具体的に組み立てることが重要です。
例えば、志望する業界の現状や課題を理解し、その中で自分のスキルや経験がどのように活かせるかを明確に伝えると効果的です。
また、業界研究の過程で得た情報やエピソードを盛り込むことで、面接官にも「本当にこの業界について深く考えている」という熱意が伝わります。「知っておくべき業界」や「具体的な業界研究のやり方」を活かして、その業界でなぜ働きたいのか、どのような目標を持っているのかを示しましょう。
こうした準備が、説得力のある志望動機を作り上げるポイントとなります。
業界研究ノートは、業界研究を効率化・深化させるために欠かせないものです。TECH OFFERは以下のリンクから無料でダウンロードできます。
業界研究するときの注意点

就職活動で成功を収めるためには、単に業界について調べるだけでなく、調査の進め方や注意点を理解することが重要です。
本節では、業界研究において気をつけるべき点や、成功へ導くコツを詳しく解説していきます。より効果的に進めるためのアドバイスを押さえることで、就職活動を有利に進められるでしょう。
先入観に囚われず広い視野を持つ
業界研究を行う際に、多くの就活生が陥りがちなのが、特定のイメージを前提として業界を評価してしまうことです。
例えば「IT業界は激務である」「金融業界は難しそう」といった先入観が、業界や企業選定の幅を狭めてしまいます。実際には業界内でも多種多様な企業があり、働き方も大きく異なります。また、新卒の募集要項には自分のキャリアに合致する柔軟な働き方を提供している企業も多いです。
そのため、自分の思い込みに囚われず、広い視点で情報収集することが必要です。業界研究・会社研究ではどのような情報を得るべきかを明確にし、具体的なデータやインタビューを基に判断を行うことが成功への近道となるでしょう。
流行や市場の動向に注目する
業界研究を進める際には、現在の流行や市場動向を理解することが重要です。
例えば、IT業界ではAIやDX(デジタルトランスフォーメーション)の台頭、製造業界ではサステナビリティの観点から注目される事業が増えています。このような動向を把握することで、業界全体の方向性だけでなく、その中でどの企業が特に注目されているのかも見えてきます。
トレンドを積極的に追うことが、「知っておくべき業界」の中で自分に合った分野を選ぶヒントに繋がります。また、流行や市場の情報を志望理由に加えることで、面接での説得力を高めることが期待できます。
ニュースサイトや業界雑誌を活用し、最新情報を効率的に取り入れましょう。
調査内容を就活でどう活かすかを明確にする
業界研究を行う目的は、単に知識を増やすことではありません。それをいかにして就職活動に活かすかがポイントです。
例えば、業界の現状と将来性を深く掘り下げ、自身のキャリアプランと結びつけることで説得力のある志望理由が作成できます。
また、企業研究を進める際にも、あらかじめ業界全体の理解を深めておくことで、各企業の特徴や差別化ポイントを見出しやすくなります。
業界研究・会社研究ではどのような情報を得るべきかを確認し、それが面接やエントリーシートでどのように活用できるかを明確にしていきましょう。
業界研究でやりがちな失敗3選
業界研究における代表的な失敗例として、以下の3つが挙げられます。
- ・調査の範囲が狭すぎる
- ・信ぴょう性の低い情報を信じる
- ・調査が抽象的に終わる
これらの問題を防ぐには、広い視点で複数の情報源を活用することが大切です。例えば、インターネットだけでなく書籍やセミナー、さらにはOB・OG訪問なども活用することで、網羅的な情報を得られます。
また、調査した内容が具体的であるかどうかも見直す必要があります。新卒採用では、企業の現状や業界動向を詳しく理解し、志望動機に反映させる力が求められます。調査結果を適切に整理し、自分のキャリアや目標と結びつけることで、業界研究をより実践的なものにできるでしょう。
まとめ
業界研究は就職活動を成功に導くための重要なステップです。本記事では業界研究の具体的なやり方や知っておくべき業界の8分類を具体的に紹介いたしました。
新卒の就職活動において、志望する業界を理解し、企業研究へとつなげることが、効率的で効果的な業界研究の目的となります。一つ一つのステップを大切に進めることで、自分に合った業界を見つけ、説得力のある志望動機を作り上げましょう。これを実施することは、就職活動全体の成功に大きく影響します。