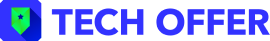研究概要書は理系学生の就活における必須項目です。
とはいえ、
・そもそもなんで必要なのか
・研究概要書をどう書いていけばいいのかわからない
という方も多いと思います。
そこで今回は、研究概要書の書き方とポイントを解説します。
具体的には、
・研究概要書が必要な理由
・研究概要書の書き方の基本
・研究概要書を書く際のポイント
の順番でご紹介します。
書き方の基本とポイントを押さえるだけで、誰でも、企業の意図を汲んだ研究概要書が書けるようになります。
就活を有利に進めるポイントになりますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼就活をスムーズに進めよう▼
TECH OFFERで研究と就活を両立する
そもそも研究概要書とは?

研究概要書とは研究の取り組みや成果を簡潔にまとめたものです。理系学生が書いた経験のある論文と似ています。
ただし、研究概要書は専門知識のある方が読むとは限らないので、「知らない人に向けてわかりやすく伝える」ことが重要です。
企業側から求められるのは主に3種類。
・図などを用いて自由に書くタイプ(A4用紙1~2枚程度)
・文字だけのエントリーシートタイプ(200字、400字など文字指定あり)
・パワーポイントを用いるタイプ
提出する企業により書式は異なりますが、研究概要書の一般的な項目を理解し、ベースをしっかり固めておきましょう。
研究概要書には3種類ある

研究概要書は、研究の目的・方法・結果を明確に伝えるための重要なツールです。
以下に、3つの主要な形式を詳しく説明します。
・文字だけのエントリーシートタイプ
・図などを用いて自由に書くタイプ
・パワーポイントを用いるタイプ
研究内容・応募企業に応じて、上記形式を使い分けましょう。
文字だけのエントリーシートタイプ
文字だけのエントリーシートタイプは、情報を簡潔に伝えられる形式です。
文字だけの形式では、研究の目的・方法・結果などをテキストベースで明確に記載します。
文字形式の利点は情報が具体的に記載されており、採用担当者に意図した情報を伝えやすい点です。
しかし、視覚的な要素がないため複雑なデータ・結果を伝えるのが難しい場合があります。
図などを用いて自由に書くタイプ
図を用いて自由に書くタイプの研究概要書は、視覚的な要素を活用して情報を伝えるタイプです。
図表やグラフを使用して、研究の結果・分析を視覚的に示します。
採用担当者は複雑なデータであっても、直感的に理解しやすくなる点がメリットです。
しかし、文章を通じて伝える割合が少なくなるため重要な情報が伝わらない可能性もあります。
図・グラフを用いる際は、適宜文章で情報を追記する必要があります。
パワーポイントを用いるタイプ
パワーポイントを用いるタイプの研究概要書は、情報を効果的に伝えられる形式です。
スライドを使用して情報を整理し、視覚的な要素を活用します。
スライドの順序・レイアウトを工夫すれば、研究の流れをわかりやすく明確に示せるのがメリットです。
また、動画・音声の挿入も可能で採用担当者は研究の背景・結果をより深く理解できます。
しかし、情報の過剰な装飾がメッセージを曖昧にする可能性があるため、文章・視覚的な要素の適切なバランスを保つのが重要です。
理系就活で研究概要書が必要な3つの理由

企業側の質問意図を理解できていないと、「知りたいのはそこじゃないんだよな」と思われるような的外れな回答になってしまいます。質問意図を理解して、適切な研究概要書を作成しましょう。
研究概要書が必要な理由は3つ。
それは、
①論理的思考力、コミュニケーション力を見るため
②課題解決力を見るため
③面接での質問に利用するため
以下で詳しくご説明します。
①論理的思考力、コミュニケーション力を見るため
社会に出てまず必要になるのが「論理的思考力」「コミュニケーション力」です。
例えば、上司やクライアントとのコミュニケーションの際には、それぞれの相手に合わせて物事を順序立ててわかりやすく説明する必要があります。
企業側は研究概要書を見て、まずこれらを判断します。
研究という専門性の高い内容を、読み手の意図を理解してわかりやすく伝えられるかが重要になります。
・誰が読むのか(専門分野の人か専門外の人か)
・どのように伝えればわかりやすいか
この2点を考えて研究概要書を書くようにしましょう。
②課題解決力を見るため
研究を進めていくと、うまくいかなかったりトラブルが発生したりと課題に直面することがよくあります。
そういったときにどうやって課題に対処したのか、企業はそこから「課題解決力」を読み取ろうとします。
実際に仕事の場面で、プロジェクトが急に変更になってしまったりなどトラブルに見舞われた際に、解決策を考えられるか、臨機応変に対応できるかで仕事の成果は大きく異なります。
そのため、企業は研究概要書から「課題解決力」読み取り、会社に貢献できる人物か判断します。
課題解決力をうまくアピールするためには、
・どのように考えて対処したのか
・どのようなことを感じたのか
・そこからどんなことを学んだのか
を考えて書くと良いでしょう。
課題に対しての自身の考えが重要になります。
また、学んだことが企業・職種にどのように活かせるかまでアピールできると完璧です。
③面接での質問に利用するため
研究概要書は面接での質問によく利用されます。
理系にとっては、学生時代に頑張ったこと=研究というぐらい大きなものですからね。
面接で深堀りされることを意識して、しっかりと説明できるよう準備が必要です。
例えば、
・研究手法や成果の今までとは違うところ
・課題に対してなぜそのように対処したのか
・研究で得た経験が仕事にどう活かせるか
企業側はあなたの研究に対して専門外の場合が多いです。
そのため、研究室内だけではなく外部の友人などに研究概要書を見てもらい、疑問に思ったことを伝えてもらうなどして対策しましょう。
企業が研究概要書でチェックするポイント

企業が研究概要書を評価する際には、いくつかの重要なポイントがあります。以下に、2つのポイントについて詳しく説明します。
・研究内容が募集職種と一致している場合
・研究内容が募集職種と一致していない場合
研究内容が募集職種と一致している場合
研究内容が募集職種と一致している場合、研究が応募者の専門知識・スキルをどの程度反映しているか評価します。
具体的には、研究内容で得た知識・経験が業務での成果にどれだけ直結するかを確認します。
また、研究の質・新しい視点やアイデアをもたらす可能性なども評価の対象です。
研究内容が募集職種と一致していない場合
研究内容が募集職種と一致していない場合、研究を通して身につけた能力を示せているかどうかが重要です。
具体的には、問題解決能力・論理的思考力などビジネスに役立つスキルがあるかを研究内容を通して把握します。
さらに、研究活動を通して応募者の学習意欲・成長の可能性を示せているかどうかも重要なポイントです。
理系就活での研究概要書の書き方7ステップ【大学生〜大学院生向け】

研究概要書の書き方の基本をご紹介します。
7ステップで、
①タイトル
②研究概要
③研究背景
④研究内容
⑤課題とその解決策
⑥研究結果・研究成果
⑦考察、今後の展望、研究から学んだこと
何から書いたらいいのかわからないという方でも、この7ステップを守ればわかりやすい研究概要書が書けるようになりますよ。
▼就活をスムーズに進めよう▼
TECH OFFERで研究と就活を両立する
①タイトル
まずはタイトルを設定しましょう。
理系あるあるだと思うのですが、研究タイトルは教授が設定したものをそのまま使っていませんか。
せっかく内容をわかりやすく書いていても、タイトルが専門的すぎてよくわからないと内容まで読む気がなくなってしまいます。
そうならないために、まずはタイトルから噛み砕いて表現するように。
例えば、
・首都圏における長周期地震動の方位依存性の研究
であれば
・首都圏における大地震の方位による伝播の違いについての研究
のように噛み砕いて表現するようにしましょう。
②研究概要
研究概要は噛み砕いたタイトルをうまく利用し、1文で簡潔にまとめましょう。
・首都圏における大地震の方位による伝播の違いから〇〇を考察しました。
この時、自身の研究内容に加えて今後の展望をイメージできるような表現があるとなお良いです。
③研究背景
研究背景は
・自身がなぜこの研究をしているのか
・この研究にはどのような意義や目的があるのか
に注意してまとめましょう。
具体的には、
・私が地震の研究を始めたのは、東日本大震災で味わった自身の無力さから、少しでも人のためになるような、そのように感じられるような研究がしたいと思ったからです。
各方位で発生した大地震が首都圏に及ぼす影響の差や特徴を明らかにすることで、今後起こると考えられている首都直下型地震への転用や地震速報の精度向上が期待できると考えました。
研究の意義や目的がはっきりしないと、その研究自体の全体像がうまく見えてきません。
漠然とやっているわけではないとアピールするためにも、どんなところに問題意識を持って、どういった考察のもと研究を行っているのか説明できるようにしましょう。
④研究内容
研究内容では、どのような手法で研究を行ったかを記載します。
ただし、ただ研究方法を記載するのではなく
・なぜそのような手法をとったのか
・その手法をとることで何が得られると考えたのか
・既存の手法にはない新規性
などをわかりやすく記載するようにしましょう。
例えば、
・各方位で発生した地震をプログラムを用いて解析し、首都圏における伝播の様子を観測しました。既存の研究で用いていた〇〇というプログラムでは✕✕という問題があり、今回新たに△△というプログラムを使用しました。
⑤課題とその解決策
研究のプロセスで発生した問題や課題があれば、解決策とセットで書くようにしましょう。
発生した問題を記載するのはマイナスポイントなんじゃないかと考える方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。
企業側はここからあなたの課題解決力を評価してくれます。
・研究を進めていくと、解析プログラムが上手く動いてくれない場面が多々ありました。色々試してみた結果、各地震ごとにパラメーターを設定しなければならないことが判明したので、都度パラメーターをプログラムし無事に解析を進めることができました。
ただし、ここでもただ書くのではなくあなたがどのように考えてその行動をとったのか、わかるように記載しましょう。
⑥研究結果・研究成果
研究内容で述べた方法で、実際にどのような結果や成果が出たか記載しましょう。
具体的な数値を用いて定量的に表すことで、より説得力のある結果を示すことができます。
また、その結果から何が明らかになったのかも合わせて記載しましょう。
・研究を通して、首都圏から東で発生した地震は西で発生した地震よりも〇〇%強く伝わることが分かりました。このことから、海底の地盤により地震が強められていることが明らかとなりました。
就活段階でまだ結果が出ていない場合は、その時点までの成果やそこからの自身の仮説を記載すれば問題ありません。
加えて、今後この研究でどのような事を明らかにしていくのかを説明してあげるとより良い内容となります。
⑦考察、今後の展望、研究から学んだこと
最後に研究から得られた結果から考えたことや学んだこと、今後の展望を記載します。
実はここが大事なパートだったりします。
企業側は結果そのものよりも、そこから何を考えたのかに興味を持っています。
何を得て、それが仕事にどう活かせるのか、会社にどのようなメリットをもたらせられるのか、詳しく記載し自身の価値をアピールしましょう。
・動かないプログラムを都度修正し解析を進める過程から、冷静に原因とその対応策を考え解決に進む課題解決力が身に付きました。
また、毎週スケジュールを組み逆算して研究を進める過程から、計画力や遂行力も身に付きました。
これらの能力を活かし、計画的に臨機応変に仕事を遂行して参ります。
理系就活での研究概要書の書き方の5つのポイント

研究概要書の基本の型はわかりましたね。
ここでは、研究概要書を書く際に気を付けるべきポイントを5つご紹介します。
①専門用語は使わず、わかりやすく書く
②文末を揃える
③図やグラフを用いて、わかりやすくまとめる
④研究を通じて学んだこと、気づいたことを書く
⑤面接で聞かれそうな質問を想定しておく
以下で詳しく解説します。
①専門用語は使わず、わかりやすく書く
研究という専門性の高い内容を説明する際には、専門用語を使いがちです。
しかし、研究概要書の内容を見て判断するのは企業の人事担当者と各部門の面接官。あなたの研究分野のスペシャリストであるとは限りません。
そのため、タイトルも含め専門用語の使用はなるべく避け、誰が読んでも理解できるようにしましょう。
とはいえ、あまりに稚拙な表現では読み手も馬鹿にされているのかなと感じてしまいますので、読み手への配慮は必要です。
1つの目安としては、高校の範囲までの言葉であれば使ってもよいでしょう。
また、やむを得ず専門用語を使う際は、その後に語句の説明の一文を加えると非常に丁寧です。
②文末を揃える
研究概要書に限らず文章を書く際に言えることですが、文末は「です・ます」調か「だ・である」調に揃えるようにしましょう。
なんとなくESを書いていると、これらがごちゃ混ぜになっている場合が多いです。
例えば、ES内で志望動機が「です・ます」調なのに研究概要が「だ・である」調など。
・研究概要書のみの場合→「だ・である」の論文調
・ESなどに付随する研究についての説明欄の場合→「です・ます」調
このように覚えておくと、混同せずに書くことができます。
③図やグラフを用いて、わかりやすくまとめる
研究概要書を書く際、図やグラフを用いるのは非常に有効です。
視覚要素が加わることで、研究内容がより理解しやすくなります。また、文字のみの場合に比べて、離脱率が下がる(最後まで集中して読んでくれる)効果もあります。
ただし、手抜きだと思われないように図やグラフの多用や大きさには気を付けましょう。
図やグラフが使えない場合は、箇条書きを利用すると文字のみの場合より理解しやすいですし、離脱率も下がります。
④研究を通じて学んだこと、気づいたことを書く
研究概要書といっても、企業側が求めているのは結果や成果ではありません。
大事なことは研究のプロセスを経て
・自身がどのように考え行動したのか
・どのようなことを学んだのか
ということです。
そのため、研究概要書には学んだことや気づきを盛り込むようにしましょう。
また、学んだことや身に付けた能力が希望する企業や職種でどのように活かせるかをしっかりとアピールすることも重要です。
⑤面接で聞かれそうな質問を想定しておく
始めにも言った通り、研究概要書は面接で深堀りされるケースがほとんどです。
そのため、作成段階であらかじめされそうな質問を予測しておきましょう。
具体的には、
・あなたの研究の既存の研究にはない新しい点は?
・研究で学んだことで希望する企業や職種で活かせそうなことは?
・研究の長期で見た展望は?短期で見た展望は?
このように質問を予め考えて答えを用意しておくことで、面接中にあたふたせず冷静に対応することができます。
研究概要書に関してよくある質問

研究概要書の作成に関する質問は多岐にわたります。以下に、よくある質問を紹介します。
・就活でESの研究内容は何を書くべき?
・研究テーマの書き方はどうすべき?
・研究成果が出てないときはどうすべき?
・履歴書の卒業研究の書き方は?
・研究がまだでESに研究内容を記載する例文は?
研究概要書に関して疑問がある場合は、上記質問への回答を参考にしてください。
就活でESの研究内容は何を書くべき?
就活でエントリーシート(ES)の研究内容に何を書くべきかは、応募する企業・職種によります。
一般的には研究のテーマ・結果などの情報はもちろん、「研究と企業・職種との関連性」または「問題解決能力・論理的思考力など研究を通して培った能力」などを記載するのも重要です。
研究テーマの書き方はどうすべき?
研究テーマを書く際、「テーマを扱った理由」「テーマをどのように探求するか」などを明確にするのが重要です。
採用担当者は研究テーマについて詳しくない可能性も高く、初心者でも分かりやすい言葉で説明しましょう。
他の研究を参考にテーマを決めた場合は、参照したデータをグラフなどで分かりやすく紹介すると採用担当者がより理解しやすくなります。
研究成果が出てないときはどうすべき?
研究成果が出ていないときは、論理的思考力・問題解決能力など研究を通して培ったスキルをアピールするのが重要です。
培ったスキルをアピールする際は、研究活動における具体的なエピソードを交えて解説すると説得力が増します。
さらに、研究を通して学習意欲なども強調すると選考での高評価につながりやすくなります。
履歴書の卒業研究の書き方は?
履歴書の卒業研究の記載方法は、取り組み内容を具体的に書くのが重要です。
特に以下のポイントを明確にして記載すると、採用担当者が卒業研究の内容をわかりやすく把握できます。
・学生時代に何を学んだか
・ゼミでどのような研究をしていたか
・卒業研究のテーマを選んだ理由
上記を一連の流れとしてストーリー立てて説明できれば、採用担当者の印象に残りやすくなります。
研究がまだでESに研究内容を記載する例文は?
研究がまだでESに研究内容を記載する場合は、以下2つのポイントを意識するのが大切です。
・研究がまだであるとハッキリ伝える
・研究予定の内容を分かる範囲で書く
特に研究がまだであることを明確にさせるのがポイントです。
この部分が曖昧だと、研究予定の内容を研究成果だと勘違いされる可能性があります。
具体的な例文は、以下の通りです。
「現時点では具体的な研究はまだスタートしておらず、春に研究室に配属されて以降、研究に関する基礎を学んでいる段階です。研究室の大きなテーマとしては〇〇を掲げています。いずれは〇〇に関する研究を行うため、現時点では〇〇の内、△△の分野に興味を持っています。」
これだけは知っておきたいポイント(まとめ)
今回は、研究概要書の書き方とポイントをご紹介しました。
①企業は研究概要書から「論理的思考力」や「コミュニケーション力」、「課題解決力」を見ている
②研究概要書は専門外の人でも理解できるよう、専門用語を避けわかりやすく書く
③結果や成果が重要なのではなく、そのプロセスで自身が考えたことや感じたことが重要
④研究から得た学びや能力がその企業・職種でどのように活かせるかPRしよう
以上のポイントを参考に、研究概要書を作成してみてください。
読み手を意識した研究概要書が書ければ、企業側はきっと評価してくれますよ。
▼就活をスムーズに進めよう▼
TECH OFFERで研究と就活を両立する