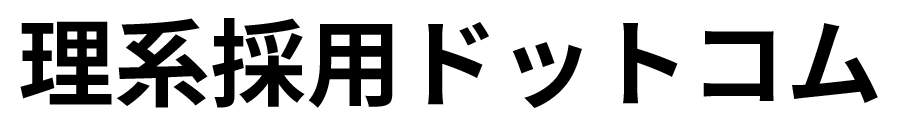目次
「学生が希望する勤務形態や働き方って変わってきている?」「リモートワークを導入しているけど、いまいち学生が集まらない」
そのように考えている採用担当者は多くいます。この記事では勤務形態と働き方で志望度がアップする理由について解説しています。
コロナ禍以前/以降で、学生が希望する勤務形態や働き方が変わりつつあります。どのような希望があるのか、採用側が把握しなければいけません。
採用活動の際に知っておきたい「フルリモートや居住地自由の魅力」や「出社への人気」、「勤務形態や働き方をアピールできるツール」を紹介しているので、ぜひ採用に役立ててください。
勤務形態や働き方は志望動機に大きく影響している

勤務形態や働き方は、志望動機に大きく影響しています。まずは学生がどのような希望を抱いているのか、以下にわけて見ていきましょう。
- フルリモートや居住地自由の魅力は大きい
- 出社機会がある企業も人気
- ハイブリッドワークという選択肢もある
フルリモートや居住地自由の魅力は大きい
株式会社学情が実施したアンケートによると、25卒の就活生が抱くフリモートや居住地自由と記載されている企業への志望度は、以下のような結果が出ています。
- 志望度が上がる:28.6%
- どちらかと言えば上がる:35.7%
合計すると6割を超える学生が、フルリモートや居住地自由という働き方に魅力を感じているのです。「住む場所を自由に選べるのは魅力的」という声もあり、テレワークやリモートワークが普及・定着した結果といえます。
コロナ禍以前よりも働き方が多様化したため、希望する層が増えています。既に導入している企業にとっては、訴求ポイントとして使えるでしょう。
出社機会がある企業も人気
一方で、出社が嫌がられているかというと、そうでもありません。出社の機会がある企業に対しての志望度は、以下のような結果になっています。
- 志望度が上がる:21.6%
- どちらかと言えば上がる:30.5%
こちらも合計すると5割を超えます。「会社の雰囲気に早く慣れるだろうから」「対面でコミュニケーションを取りたい」などポジティブな意見も多くあります。
リモート会議やオンライン商談が当たり前となり、出社しない働き方を前提している企業が増えている中、学生が求めているのは「自分なりの価値を生み出すために、リアルに会って話す機会」です。
デジタルネイティブだからといって、リアルを疎かにしていない点がわかります。
ハイブリッドワークという選択肢もある
転職市場を含め、勤務形態や働き方を問わない企業が求められているのは確かです。アンケート結果からも、需要はあります。一方で、出社して働きたいという需要が高いのも事実です。
そこで導入を検討したいのが、ハイブリッドワークになります。ハイブリッドワークとは、テレワークとオフィスワークと選択して働くワークスタイルのこと。
例えば、週5日勤務のうち、3日は自宅で働き、残りの2日をオフィスで働くといった形です。こうした働き方なら、どちらの需要も満たせます。
WeWorkJapanの「コロナ禍長期化における働き方に関する調査」では、ハイブリッドワークを実施したい従業員の数が全体の約5割に達しています。選択肢として検討する意義は大きいといえるでしょう。
トレンドを意識した採用をする際に知っておきたい面接官の役割

就活生のトレンドを意識した採用活動の導入は、非常に重要です。しかしその前に、まずは面接官の役割を理解しておきましょう。効果的なアプローチをするためにも、以下は必ず意識してください。
- 採用担当者は会社の顔である
- 求職者が社員とコミュニケーションを取れる存在である
- 自分の役割を正確に理解する必要がある
採用担当者は会社の顔である
採用担当者は、学生にとって企業の顔そのものです、対応ひとつで大きく評価を落とす可能性があります。志望度の低下にも繋がるため、企業の顔としての意識を持ちましょう。特に以下は意識したいポイントです。
- 求職者の味方になって安心感を与える
- 事前準備をしっかりする
- 公平な判断ができるように意識する
- 言語感覚を磨く
採用の際は、相手をジャッジするだけでなく、ジャッジされる側としての意識も持ってください。特に、学生だからといって高圧的になったり見下したりするのは、良くありません。勤務形態や働き方が魅力的でも、志望度の低下に繋がります。
求職者が社員とコミュニケーションを取れる存在である
求職者にとって、採用担当者は企業の中でコミュニケーションを取れる存在です。そのため、求職者が欲しい情報を投げられるかどうかも、重要になってきます。
特に意識したいのが、就活生の半数以上が「対面でコミュニケーションを取る機会を持ちたい」と答えていた点です。実際に自分が働く場所を体験したいと考えている層は、非常に多くいます。
採用担当者が求職者に対して自社の社員とコミュニケーションを取れる機会を作れば、それだけでも志望度を上げる要因になります。入社後に「この会社で頑張りたい」というモチベーションアップにも繋がるでしょう。
自分の役割を正確に理解する必要がある
採用担当者は、学生とやり取りする際に、以下を自分の役割として理解しておきましょう。
- 求職者の味方である
- 求職者に気付きを与える存在である
- 求職者に自社の魅力を伝える存在である
- 求職者を見極めて意思決定を促す存在である
どれも面接をするなら重要なものです。採用担当者は、求職者の味方として安心感を与えながら、本音を引き出さなければいけません。
そして、引き出した本音や求職者のキャリアビジョンをもとに、自社でできることを伝えましょう。求職者がキャリアビジョンから逆算して自分に足りないスキルを見出し、自社で働きたいと決断させられれば御の字です。
勤務形態や働き方は、求職者の本音に基づいています。彼らの本音を引き出して自覚させる意味でも、採用担当者の役割は非常に大きいのです。
求職者の志望動機は「高める」を意識しよう

採用担当者が意識すべきなのは、志望動機を「高める」ことです。「測る」ことではありません。求職者が本来持っている志望動機を、いかに高めて自社を選んでもらうかが重要です。
その高める一環として意識したいのが、勤務形態と働き方になります。
採用は、相手を見極める場としてはもちろん、採用選考を通して志望動機を高めていく場でもあります。自社の採用要件に合った求職者と出会った場合は、自社を積極的にアピールし、志望動機を高めるように意識しましょう。
特に就活生は、気になる企業を複数社受けています。受け身になるのではなく、企業側からも働きかけることが大切です。
勤務形態や働き方を正しく伝えて志望度をアップさせる方法

志望度をアップさせるには、勤務形態や働き方を正しく伝えるのが1番です。しかし、ナビサイトだけではなかなか伝えられません。そのような場合には、以下の方法を活用してみましょう。
- 採用サイト
- SNS
- 社員との座談会
- ダイレクトリクルーティング
採用サイト
採用サイトは、近年多くの企業が取り入れている採用ツールです。採用に関係した情報を専門的に掲載します。
採用サイトを作る際は、求職者が欲しいと思う情報を掲載するのがポイントです。勤務形態や働き方は、その中の情報として盛り込みましょう。例えば、以下のような形です。
- フルリモートで自分らしく働いている社員のインタビュー
- ハイブリッドワークを使って自由に働いている社員の姿
他にも、勤務時のタイムスケジュールがあれば、求職者の参考になります。実際に働いている社員の情報があると、入社して働く自分の姿を具体的にイメージできます。導入実績としてのアナウンスとしても機能できるので、一石二鳥の採用ツールです。
◆採用サイトのコンテンツに関して、さらに知りたい方はこちら。
SNS
採用サイトとともに活用したいのが、SNSです。学生のほとんどが使っているため、情報発信ツールとして極めて優秀です。採用サイトと併用すると、より効果に期待できるでしょう。例えば以下のような形で運用してみてください。
- フルリモートで働いている○○さんを紹介 → 採用サイトへのリンク
- ハイブリッドワークで自由に働いている○○さんと対談できる → イベントへの参加誘導
興味のある求職者の誘導をメインに、活用すると良いでしょう。
就活スケジュールに合わせた情報を発信すれば、より親近感を持ってもらいやすい効果もあります。
◆SNSを使った就活生へのアピール方法に関して、さらに知りたい方はこちら
社員との座談会
社員との座談会も効果が大きいイベントです。求職者が希望する勤務形態や働き方を実践している社員との対談は、志望度アップにも繋がります。
また、社員座談会は、自社の魅力をアピールできる場所でもあり、求職者が気軽に自社について質問できる場所でもあります。合同説明会では伝えきれない魅力や情報を発信できるため、興味を持ってくれた層の一押しとして活用できるでしょう。
特に大きいのが、学生が知りたい「普段の会社での過ごし方」です。半数以上の学生が求めている「出社して働く」に関する情報を発信できます。入社後のミスマッチを防ぐ効果もあるため、効果が大きい方法です。
◆社員座談会に関して、さらに知りたい方はこちら
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングもおすすめの採用方法です。自社の魅力を学生に直接伝えられるため、知名度に関係なく採用できます。
特にリモートワークやハイブリッドワークなど、学生が希望する勤務形態・働き方を導入していると、効果が大きくなります。
選考の中で学生が希望する条件や働き方のヒアリングもできるため、自社とマッチしているかの判断もすぐに可能です。勤務形態や働き方が希望と合っていなかったとしても、別の側面から志望度アップに繋がるケースもあります。
効果が非常に大きい採用方法なので、ナビサイトと併用して活用しましょう。
勤務形態や働き方で志望度をアップさせるならダイレクトリクルーティングの『TECH OFFER』
コロナ禍以前と以降で、学生が希望する勤務形態や働き方が大きく変わりつつあります。希望する条件は個人によって異なるため、採用サイトやSNSなど様々なツールを使って発信していきましょう。
中でも理系採用をするならダイレクトリクルーティングの『TECH OFFER』がおすすめです。学生と直接やり取りできるため、希望する勤務形態や働き方をヒアリングしやすくなります。『TECH OFFER』が気になる方は以下のボタンから資料が無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。